がんばろう、日本。
そんなスローガンは、人気のない政府が「戦後最大の国難」を乗り切れば支持率回復が見込めるからと、日本全部を同列に巻き込もうとしているプロパガンダに思える。
日本はひとつになんかならないし、なれない。
当たり前だ。そもそもみんな別々の価値で生きている。
それでもやれる事が何かを考えるべきなのだろう。
違う価値でもやれる何か。
違う思いでもやれる何か。
それが見つからなければ、本当の意味で「日本」の再生などないような気がする。
僕がそんなひねくれた見方をするには理由がある。
たとえばテレビを見ていたり、ネットでブログや掲示板を読んでいると、錯覚なのかもしれないけれど、特定の誰かに向けられているようで、実は社会全体向けられた根強い不信感みたいなものが、にじみ出ているように思えるからだ。
誰も信じない、信じられない、そんな負のスパイラル。
たとえば闇雲に逃げ出した外国人の行動や、福島の名前さえはじめて聞いたような国の政府広報、中途半端な日本語しか知らない外国特派員の報道の方が信じられてしまうほど、この国の政治家や企業、そして科学者や報道は信じられていないらしい。それはまるで自国の放送ではなくBBCやボイス・オブ・アメリカを聞いていた旧共産圏の人たちのようだ。確かにそう思いたくなる気持ちも分からなくはない。政府は常に後手に回り、東電も隠蔽体質から変わろうとしていない。しかしそれでも自由が奪われ、深刻な情報統制下にあった国々と、この国とは違うだろうにと思う。
政府が信じられないと叫ぶジャーナリストは、なぜもっと首相を追い込まないのだろう?
東電のデータがおかしいと思うなら安全な記者クラブに居座らず、許可をとって現地に入り、ガイガーカウンターをもって突撃取材をすればいい。少なくともこの国はそれが許されるくらいに自由なのだから。
僕は「プラハの春」から約三十年たったプラハの町を訪れた事がある。街角の壁にはそれを讃えるように「1968」とその時の年号が落書きがされていた。その時プラハの人々はボイス・オブ・アメリカを信じた。アメリカは自由を愛する人たちを命がけで支援してくれると信じていたのに、アメリカは助けてくれはしなかった。現実は資源もない小国に対し、それだけのリスクを負う気などなかった。アメリカが信じがたい国だと言いたいのではない。今回の震災でも米軍は頼りになった。僕が言いたい事は、国の在り方は結局その国民が責任を負うという事だ。
そんな状態の旧共産圏とは比べられないほど、日本は独立した自由を持っている。今回の問題で噴出したとはいえ、社会への不信や閉塞感は今にはじまった事ではない。結局のところ価値観や判断基準を他人に依存しすぎていた個人のつけが、深刻な不信につながっているように思える。関わり合う人同士の関係性よりも、情報重視に傾いた社会の脆弱さが引き起こした気がする。自分の力でリスクを判断し、結果はどうあれ、それを引き受ける覚悟がないから、誰かに責任を求める。
本当の意味で、自由を行使していないのではないか?
僕にはそう思えてならない。
都市部に住む人たちは、妙に弱肉強食をマーケットや経済効率に例えるような事を言って、あたかも自分たちが競争社会の前線で日々戦っている狩猟採集の民のように思っているように見える。だが実際には雨にも負けず、風にも負けず、ただひたすらに会社という畑を耕す、疑似農業的な生活をしている人の方が多い事に気がついてはいない。たとえば漁師なら海が荒れれば漁を休むが、農家はどんな天候でも人の力で成しうる管理を欠かさない。しかし自然相手ではなく、サービスし合う人間相手の企業では、天災などないから運の悪さを認めようとしない。災いの原因は管理の埒外にある何者かのせいだと考えがちなのだ。だから液状化があったり、天井が落下したりすれば、土地を整備した人や建物を管理していた人が悪いと考えてしまう。
海や土に関わって育った人の多くは、自然の前では人間など無力だとよく知っている。結局のところ最後は運次第。漁師なら運が悪ければ死ぬ事もある。それをよく知っているから、どうあれ責任は自分にあると考える。
僕は小さい頃、貧乏だった(今も裕福ではないが)せいもあって、よく浜にアサリを掘りに行っておかずにしていた。都会の潮干狩りなどとは違う。子どもだから遊び感覚もあったが、生活ともっと結びつく行為だった。よく取れる場所は岬の突端の陰など、簡単に入れる場所にはない。足場の悪い崖から崖を飛び越えるような所もあり、落ちれば運が良ければ大怪我、普通に考えれば死ぬだろうと思える高さと地形だった。そういうところで僕が尻込みをした時、母に言われた。「跳べないと思うなら来るな。跳べると思って落ちたら、その程度の運だったと諦めろ」と。
どっちらが良いとか悪いとか言うつもりはない。
別にそんな事はどうだっていいし、そもそも僕の分析自体が間違っているのかもしれないのだから。
ただ言いたいのは、狭いこの国でも意外に生き方の違いはあり、何事も皆が思っているよりも多様だという事だ。多様であればあるだけ、真実と呼ばれるものの数も増える。価値の数も増えるし、リスクも増える。
その人が絶対的に思える真実や価値にも、すべての人が頷くわけじゃない。そういう中で歴史や社会は作られてきたし、絶対的な権力から開放され、それぞれの価値を認める事が自由の行使のはじまりだ。
だから他人のリスクを嘲るべきではない。
他人の不運を笑うべきでもない。
他人の価値を侮ってはいけない。
そんな複雑で多様なつながりを、単純な情報だけですべてを理解したつもりでいると、澱のように誤解がたまり、不信に変わる。
ひとつになんか、ならなくていい。
無理に見つめ合う必要もない。
ただ同じ方を向く事はできるだろう?
たとえ立っているところは違っても。
「愛するということは、われわれがおたがいに顔を見合うことではなくて、みんなが同じ方向を見ることである」
妻に教えてもらったサン・テグジュペリの言葉だ。
全国放送のテレビをみていると、悪気はないのだろうが、狼狽えたような、落ち着きのないキャスターやコメンテーターの姿に疲れてしまう。それで視聴者に対して冷静にとか、落ち着けとか言っても、無理な話だ。彼らはどこを向いているのだろう?
仙台は今日も静かだ。悲しみはあるが、パニックなんてない。
ローカルラジオや地元放送局のテレビニュースは、ほとんどが手に取れる悲しみと、小さな希望の話であり、ひとりひとり顔の見える話ばかりだ。情報の距離感が求める側と合っている。
仙台市若林区で津波によって家も家族も失った男性が、かつての自宅跡にたたずみながら、チューリップの球根の話をしていた。毎年たくさん植えていたそうだ。その人は津波で流された球根がそこいら中でたくさんの花を咲かせるといいと言っていた。
それはきっと哀しくも美しい光景だ。
今、この町では、遠くで起こっている仮定と不信を重ね合わせた話よりも、そんな身近な話を受け止める事の方が重要なんだと思う。
僕はどこを向くべきかを決めている。
原発の話はこれからも続くし、これからでも出来る。生き残った人たちとの関わりも、まだこれからでいい。
でもひとりひとりの死者たちを悼むのは、やはり今しかできないように思う。
海の底から戻れないままの人たちが、今も一万人はいる。
見つけてあげられたけれど、身元の確認できない無縁者も千人単位でいる。
あの日まで、みんな普通に生きていた。
築五十年の家と聞くと、多くの人が古いと思うだろう。でも僕は今、四十六歳だけど、まだ古い人間とは言われない(多分)。車なんて十年以上乗る人は少ないし、電化製品もせいぜい十年だ。津波でそういうものをたくさん失ったけれど、一番年月を経ているのは人間だ。八十歳のおじいさんは八十年の年月を積み重ねてきたし、二歳の子どもでも父と母の成長と出会いから考えれば、相当な月日が費やされている。つまり人を失うという事が一番多くの過去を失う事になる。町など流されてしまっても、人さえ生きていればまた作る事ができる。
未来を考えるならば、完全にすべてが失われてしまわないよう、欠片だけでもつないでいけるよう、どんな町で、どんな人たちが、どんな風に生きていたのか、僕は知っている限りの事をここに書きとどめるつもりだ。
別にそれが僕の仕事ではないけれど、こうしてやれる事ではある。
震災から一週間になる。
実をいえばここから長い長い停滞がはじまる。一週間目から二週間目までは、それ以外の言葉では表せない。ミクロ単位の前進と言ったら言い過ぎかもしれないけれど、センチ単位の前進という印象で、悪くはなっていないが、復旧を実感するほどでもない。それを象徴するかのように行方不明者の数は一ヶ月たっても、犠牲者は一万人を越え、行方不明者も一万五千人から一向に減らない。
ガソリン不足がひどすぎて、ほとんどの企業は仕事が休みだし、物流もほとんど回復せず、大型スーパーですら店頭販売で、開く時間も不定期や時間限定。個人商店も含めて、何とか少しずつかき集めて何とか成り立っている感じだ。
奇妙な平穏と言ったらいいのだろうか、停滞して何も動かないからやる事がない。東南アジアに行くと、日がな一日ぶらぶらしていて何をしているのか分からない人がいる。昔は日本にもそんなおじさんが結構いた。こうなって思うのは、なるほどあれは停滞していて何もやる事がないのだなと納得できる。僕も今はその仲間入りだ。ガソリンがないし、JRはまだ動かないのでわずか十五キロ先の実家にも行けない。ボランティアをするにも遠くにはいけないから、仙台市のボランティアセンターに登録しても、危険地帯への立ち入りが禁止されており、自衛隊が遺体捜索を追え、安全確認してからでないと仕事がない。太白区のボランティアセンターのある仙台市体育館の前には、たくさんの若い人たちがいたけれど、その熱意が生かされるのはもう少し先らしい。他にもたとえば多賀城市などは、二次災害防止のためなどから地元の人以外のボランティアは受け入れていない。確かにその地域を知らないと、万が一、大きな余震で津波が来た時に逃げられないかもしれないから、それも仕方がないと思う。
ただすでにボランティアを必要としている地域もあるし、決定的に人手が足りないところもある。ガソリンの確保ができる人たちならば、積極的に協力して欲しいけれど、テレビなどで「自己完結型」を言い過ぎるせいなのか、どうも動き出しが鈍いようだ。結局の所、自分で寝る場所と食べ物を確保しろというだけの事で、必ずしも山登りのようにサバイバルで暮らせというのではない。別に車の中でもいいし、山形辺りに宿をとって来る人もいる。もっと近くでも営業している宿があるならそこに泊まったっていいし、やっている食堂があればそこで食べればいい。それだって広い意味で地域経済に貢献しているわけで、ボランティアついでに金を落としていくのは何も悪い事ではない。ボランティアはストイックみたいなイメージは幻想だし、ごく普通に良識のある大人であれば問題はない。実際、デコトラで被災地を回るトラック野郎たちが炊き出しをしてくれたりとか、いろいろなラーメン店が食材持参でやってきてくれたり、疾風のように現れて、疾風のように去っていく月光仮面(古いなあ)のような人たちもいる。とにもかくにもボランティアの人たちには心から感謝だ。
片づけ作業などで汗だらけ埃だらけになっても、仙台市内は市ガスが使えないので、ほとんどの人がシャワーも風呂も入れない状況だ。在庫の燃料がある限りがんばって開店している銭湯も、整理券が早朝からならんで三十分でなくなる。仕方がないからお湯を湧かしてタオルで身体を拭き、髪も少ないお湯でなんとか洗うしかない。
十日目くらいから、髪だけ水洗いしたり、プロパンガスでシャンプーしてくれる美容院が出てきて、髪の長い女性などは大助かりしている。妻も一度、洗ってもらったが、嬉しかったのかとても笑顔だった。僕はちょっと毛が薄くなってきたし、髪も短いから、洗面台で我慢している。
僕の親戚に関しては、とりあえず塩釜と東松島で津波による家屋への浸水で、一階が使えなくなったのが二件あっただけで済んだかに思えたのだが、亡くなった人も判明した。















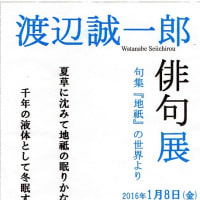










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます