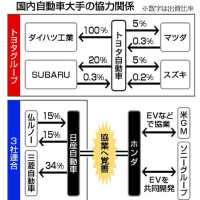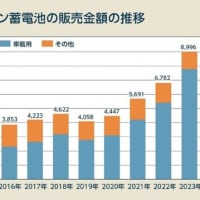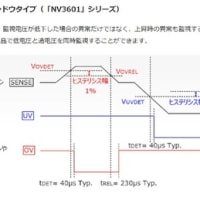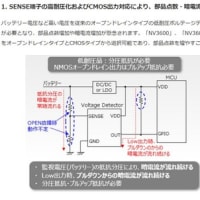まず、この記事を記す切っ掛けとなったのは、何年か前日野セレガ大型観光バスで、通常走行では水温安定しているが、連続高負荷走行するととたんに水温上昇し、水温計がメーターを振り切りそうになり警告音を発するというトラブルに遭遇し、診断した結果として、車体左後部のインタークーラー後ろに設置されたラジエーターの冷却フィンが結構な面積で腐食して脱落してしまっていたことを発見したことによります。(写真参照)
そこで、表題について、愚人のささやかな知識から、古いクルマと現代車における設計思想の違いを記してみます。
まず、一般的な乗用車を前提として、その冷却水だとかエンジンオイルの総容量は確実に減少して来たのです。その理由は、最適設計などというワードで表現される訳ですが、何を求めての最適かと云えば、これらの総量を減少させることで熱容量を減少させ、冷間始動から昇温するまでの暖機時間の短縮にあるのでしょう。現代の排出ガス試験は、冷間始動からの条件が前提となっています。そのため冷間時の燃料増量時間を短縮することにあると思えます。また、ガソリンエンジンの場合、フィードバック制御による理論空燃比運転を行っていますが、O2センサーは一定温以下では活性化できないので、ヒーターを内蔵したり、触媒も排気マニホールド直下に装着したりして、冷間始動後の早期にフィードバック制御が開始される様にしています。
さて、ここからが今回伝えたいことの本論となります。昔からエンジン油圧計はあっても油温計が標準で付いているクルマは少なかったのですが、冷却水温計は水冷エンジンではほとんど装着されていました。仮にエンジン油温計を追加装備し、冷却水温と油温を常時計測出来るクルマに乗って種々の走行条件を変えて走行してみた場合、どのような傾向を示すでしょうか・・・。
平坦路と登坂路の制限速度一定走行を比べれば、スロットル開度はまるで異なる訳です。つまりエンジンで燃焼され発熱される熱量は、スロットル開度が大きい登坂路が段違いに大きくなる訳です。エンジンの燃焼エネルギーを動力に変換する熱効率については、その回転数などで変動しますが、ここでは33%を近似値一定と仮定して考えると、常に燃焼エネルギーの66%は冷却水やエンジンオイルの廃熱や排気ガスのエネルギーとして捨ててる訳です。ところで、冷却水温とエンジン油温の傾向は、平坦路では冷却水温は80度+α程、油温は冷却水温+10℃程度となろうかと想定します。ところが、登坂路を走行し続けると、冷却水温はほとんど変化しませんが、油温は+10℃を離れ、100℃、110℃と昇温していきます。
一般論としては、エンジン油温の安全圏は120℃が上限で140℃を越えると限界だと云われています。これは昇温によって、オイル粘度が低下し油圧が低下したり、油膜が薄くなることにあるのでしょう。しかし、技術的に高温オイル特性を持たせたオイルを作ろうと思えば、例え150、160℃でも油膜性能を落とさないオイルを作ることは可能だろうと思えます。しかし、そんな高温特性に優れたオイルが作られることはあり得ません。それは何故かといえば、エンジンメタルにあるのだろうと思います。現在の4輪車用エンジンでは、クランクシャフトなどの軸受けは、滑り軸受けたる平軸受け(メタルと称す)が使われています。このメタルは、クランクシャフト側が鍛造加工されメタル当り面を表面硬化させ大変硬い状態に対して、メタル表面はケルメット(銅と鉛の合金)をベースとして、表面をホワイトメタル(鉛、錫などの合金)でオーバーレイされているものが一般的です。つまりクランク側の軸に対して、随分柔らかく、しかも素材的に低融点なものなのです。ですから、油温が上がり過ぎると、メタルの冷却も阻害され、最終的にはメタル合金が流れてしまうことになります。こうなるとエンジンは、壊滅的なダメージを受け、走行不能な状態に陥ってしまいます。
ところで、冷却水の温度は走行条件によってほぼ一定温に保持されますが、これはサーモスタットという機構が備えられていることによります。しかし、一部の特殊なエンジンには備えたものもあるらしいですが、エンジンオイル経路にサーモスタットを備えたエンジンはないのが通例です。従って、高負荷連続走行などのエンジン燃焼エネルギーが高まる状態では、油温は上昇してしまうのです。そのことをエンジン設計者はもちろん判っていて、ターボエンジンや高回転エンジンなどには、エンジンオイルクーラーが設置されたりしている訳です。また、レーシングエンジンなどは、オイルパンを浅くしてエンジン重心を下げたいことと共に、別体オイルタンクによりオイル総量を増やすことができるドライサンプエンジンが多用されるのだろうと思います。
しかし、現在エンジンは、オイル容量が減らされた上で、交換インターバルが格段に伸ばされている傾向にあるのですが、化学合成エンジンオイル等の技術発展もあるのでしょうが、過酷な条件ではあると思います。

そこで、表題について、愚人のささやかな知識から、古いクルマと現代車における設計思想の違いを記してみます。
まず、一般的な乗用車を前提として、その冷却水だとかエンジンオイルの総容量は確実に減少して来たのです。その理由は、最適設計などというワードで表現される訳ですが、何を求めての最適かと云えば、これらの総量を減少させることで熱容量を減少させ、冷間始動から昇温するまでの暖機時間の短縮にあるのでしょう。現代の排出ガス試験は、冷間始動からの条件が前提となっています。そのため冷間時の燃料増量時間を短縮することにあると思えます。また、ガソリンエンジンの場合、フィードバック制御による理論空燃比運転を行っていますが、O2センサーは一定温以下では活性化できないので、ヒーターを内蔵したり、触媒も排気マニホールド直下に装着したりして、冷間始動後の早期にフィードバック制御が開始される様にしています。
さて、ここからが今回伝えたいことの本論となります。昔からエンジン油圧計はあっても油温計が標準で付いているクルマは少なかったのですが、冷却水温計は水冷エンジンではほとんど装着されていました。仮にエンジン油温計を追加装備し、冷却水温と油温を常時計測出来るクルマに乗って種々の走行条件を変えて走行してみた場合、どのような傾向を示すでしょうか・・・。
平坦路と登坂路の制限速度一定走行を比べれば、スロットル開度はまるで異なる訳です。つまりエンジンで燃焼され発熱される熱量は、スロットル開度が大きい登坂路が段違いに大きくなる訳です。エンジンの燃焼エネルギーを動力に変換する熱効率については、その回転数などで変動しますが、ここでは33%を近似値一定と仮定して考えると、常に燃焼エネルギーの66%は冷却水やエンジンオイルの廃熱や排気ガスのエネルギーとして捨ててる訳です。ところで、冷却水温とエンジン油温の傾向は、平坦路では冷却水温は80度+α程、油温は冷却水温+10℃程度となろうかと想定します。ところが、登坂路を走行し続けると、冷却水温はほとんど変化しませんが、油温は+10℃を離れ、100℃、110℃と昇温していきます。
一般論としては、エンジン油温の安全圏は120℃が上限で140℃を越えると限界だと云われています。これは昇温によって、オイル粘度が低下し油圧が低下したり、油膜が薄くなることにあるのでしょう。しかし、技術的に高温オイル特性を持たせたオイルを作ろうと思えば、例え150、160℃でも油膜性能を落とさないオイルを作ることは可能だろうと思えます。しかし、そんな高温特性に優れたオイルが作られることはあり得ません。それは何故かといえば、エンジンメタルにあるのだろうと思います。現在の4輪車用エンジンでは、クランクシャフトなどの軸受けは、滑り軸受けたる平軸受け(メタルと称す)が使われています。このメタルは、クランクシャフト側が鍛造加工されメタル当り面を表面硬化させ大変硬い状態に対して、メタル表面はケルメット(銅と鉛の合金)をベースとして、表面をホワイトメタル(鉛、錫などの合金)でオーバーレイされているものが一般的です。つまりクランク側の軸に対して、随分柔らかく、しかも素材的に低融点なものなのです。ですから、油温が上がり過ぎると、メタルの冷却も阻害され、最終的にはメタル合金が流れてしまうことになります。こうなるとエンジンは、壊滅的なダメージを受け、走行不能な状態に陥ってしまいます。
ところで、冷却水の温度は走行条件によってほぼ一定温に保持されますが、これはサーモスタットという機構が備えられていることによります。しかし、一部の特殊なエンジンには備えたものもあるらしいですが、エンジンオイル経路にサーモスタットを備えたエンジンはないのが通例です。従って、高負荷連続走行などのエンジン燃焼エネルギーが高まる状態では、油温は上昇してしまうのです。そのことをエンジン設計者はもちろん判っていて、ターボエンジンや高回転エンジンなどには、エンジンオイルクーラーが設置されたりしている訳です。また、レーシングエンジンなどは、オイルパンを浅くしてエンジン重心を下げたいことと共に、別体オイルタンクによりオイル総量を増やすことができるドライサンプエンジンが多用されるのだろうと思います。
しかし、現在エンジンは、オイル容量が減らされた上で、交換インターバルが格段に伸ばされている傾向にあるのですが、化学合成エンジンオイル等の技術発展もあるのでしょうが、過酷な条件ではあると思います。