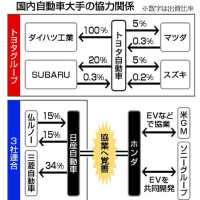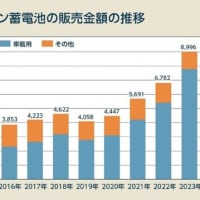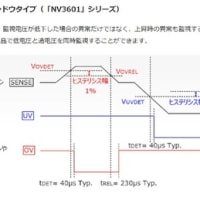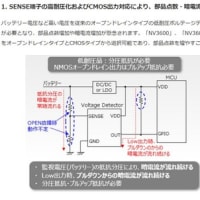「凡百の専門書よりも核心を突いた1冊」取材期間は8年…警察、検察の堕落を描き切った異色の小説『人質の法廷』が炙り出す“この国の実態”
7/16(火) 15:12配信 文春オンライン ジャーナリスト・青木理氏
人質司法とは、否認供述や黙秘している被疑者らを拘留し自白を強要する悪名高き司法制度である。
東京五輪を巡る汚職事件で逮捕・起訴された角川歴彦KADOKAWA前会長は、幾度も体調不良を訴えたが保釈は却下された。拘留期間226日。肉体的・精神的苦痛を受けたとして目下、国賠訴訟を起こしている。過去の冤罪事件を挙げるまでもなく、司法の実態はかくも酷い。
日本の司法制度を取材しつづけるジャーナリストの青木理氏が、「凡百の専門書やノンフィクションよりもはるかに深く現実=事実の核心を突いた一冊」と評した小説がある。作家・里見蘭氏によるリーガルサスペンス『人質の法廷』だ。
物語は、東京都内で発生した冷酷な女子中学生連続殺人事件で幕をあける。逮捕されたのは現場近くに暮らす40代男性。彼の弁護を任された女性弁護士は、男性が自白を強いられたことを知り、冤罪を晴らすために奔走するが……。これだけだと、いわゆる“勧善懲悪”もの、または、弱者のために真実を明かすリーガル・ドラマに思われそうだ。しかし、そんな生易しいストーリーではない。小説ながら、8年にも及んだという取材成果をまとめたという本書には、警察、検察の堕落がこれでもかと描かれている。青木理氏が異色の小説の魅力に迫った。
◇◇◇
刑事司法に満ち満ちた矛盾や不正義とは具体的に何か
事実は小説よりも奇なものだと、英国の詩人は19世紀に評した。いまさらながら言い得て妙、現実の社会は往々にして凡百の小説などよりはるかに怪奇性と複雑性に満ち、矛盾と不正義にも溢れている。本作がテーマとしたこの国の刑事司法はその極北のひとつだと私は思う。
だが、決して言葉遊びではなく、本作はその矛盾と不正義に満ち満ちた刑事司法の現実=事実を小説へと――しかも読み応えのあるエンターテインメント小説へと見事に昇華させている。
では、この国の刑事司法に満ち満ちた矛盾や不正義とは具体的に何か。
挙げはじめればキリはないのだが、さして詳しい注釈も加えずにざっと列挙すれば――①警察に身柄を拘束されるとその警察管理下の留置施設に放り込まれてしまう「代用監獄」、②相変わらず自白偏重の姿勢から脱却できない警察、検察と、密室の中で延々と長時間続けられる苛烈な取り調べ、③被疑事実を否認すれば、起訴後も保釈がなかなか認められず、信じがたいほどの長期勾留が続いてしまう「人質司法」、④警察や検察が捜査の過程で収集した証拠類を独占し、仮に被疑者・被告人に有利な証拠類があっても隠されてしまう陋習、そして⑤各種令状の発付や身柄勾留等の判断を含め、ひたすら検察の言い分に唯々諾々と追随してしまいがちな司法権の砦=裁判所――。
さらにつけ加えるなら、世界的には廃止が圧倒的な潮流となっている死刑制度にいまだ固執し、しかもその運用状況がおそろしく秘密主義的なこと等々もあわせ、いわゆる先進民主主義国の刑事司法ではおよそ考えられないほど後進的な悪弊がいくつも温存されてしまっている。
「制度が正されるまで事件は待ってくれません」
そして本来なら、ここで悪弊の悪弊たる所以をもう少し噛み砕き、わかりやすく解説するべきなのだろうが、その必要を私はいままったく感じない。本作にその大半が盛り込まれ、凝縮して描き尽くされているからである。この点で本作は、悪弊の温存を主導してきた警察や検察といった捜査機関を――同時にそれは強大な国家権力でもあるのだが――平然とヒロイックに描きがちな、まさに凡百のエンターテインメント小説とは明らかな一線を画している。
折しも静岡地裁では袴田事件の再審公判が過日結審し、実に戦後5件目にもなる死刑確定事件での雪冤が果たされるのは確実な状況になっている。鹿児島では、自らの組織の不正をメディアに公益通報した前幹部を口封じで逮捕したとしか思えない警察組織の暴走が現在進行形で引き起こされている。大阪では、地検トップの座に君臨していた元検事正が在職中の準強制性交容疑で逮捕された。だというのに肝心の政治は反応らしい反応を示さず、悪弊の改善に取り組もうという気配さえ皆無に近い。
それでも――。本作の中に印象深い台詞がある。志と熱意に溢れた主人公の新人弁護士を励まし、強力にサポートする〈日本でも指折りの刑事弁護士〉が、被疑者として捕えられて無実を訴える〈増山〉に向けて発した次のような台詞である。
「増山さんは間違った制度の犠牲者なんです。われわれ弁護士はこの日本の刑事司法のシステムそのものと闘って変えていかなくてはならないし、現に闘い続けています。ですが――制度が正されるまで事件は待ってくれません。この間違った現状の中で歯を食い縛り、依頼人のためにベストを尽くすしかないというのも日々の現実です」
たしかにそんな弁護士が――おそろしく数は少ないけれど、現実に存在していることを私は知っている。と同時に、この国の刑事司法システムそのものに改善すべき課題が満ち満ちていて、「変えていかなくてはならない」のが焦眉の課題であることも。
ならば本作は、もとよりフィクションではあるけれど、これも凡百の専門書やノンフィクションよりもはるかに深く現実=事実の核心を突いた1冊として読んでも構わない。いや、多くの人に読まれて現実の課題が課題として広く共有されることを心から願っている。青木 理
#検察の堕落を描き切った異色の小説『人質の法廷』が炙り出す“この国の実態”
7/16(火) 15:12配信 文春オンライン ジャーナリスト・青木理氏
人質司法とは、否認供述や黙秘している被疑者らを拘留し自白を強要する悪名高き司法制度である。
東京五輪を巡る汚職事件で逮捕・起訴された角川歴彦KADOKAWA前会長は、幾度も体調不良を訴えたが保釈は却下された。拘留期間226日。肉体的・精神的苦痛を受けたとして目下、国賠訴訟を起こしている。過去の冤罪事件を挙げるまでもなく、司法の実態はかくも酷い。
日本の司法制度を取材しつづけるジャーナリストの青木理氏が、「凡百の専門書やノンフィクションよりもはるかに深く現実=事実の核心を突いた一冊」と評した小説がある。作家・里見蘭氏によるリーガルサスペンス『人質の法廷』だ。
物語は、東京都内で発生した冷酷な女子中学生連続殺人事件で幕をあける。逮捕されたのは現場近くに暮らす40代男性。彼の弁護を任された女性弁護士は、男性が自白を強いられたことを知り、冤罪を晴らすために奔走するが……。これだけだと、いわゆる“勧善懲悪”もの、または、弱者のために真実を明かすリーガル・ドラマに思われそうだ。しかし、そんな生易しいストーリーではない。小説ながら、8年にも及んだという取材成果をまとめたという本書には、警察、検察の堕落がこれでもかと描かれている。青木理氏が異色の小説の魅力に迫った。
◇◇◇
刑事司法に満ち満ちた矛盾や不正義とは具体的に何か
事実は小説よりも奇なものだと、英国の詩人は19世紀に評した。いまさらながら言い得て妙、現実の社会は往々にして凡百の小説などよりはるかに怪奇性と複雑性に満ち、矛盾と不正義にも溢れている。本作がテーマとしたこの国の刑事司法はその極北のひとつだと私は思う。
だが、決して言葉遊びではなく、本作はその矛盾と不正義に満ち満ちた刑事司法の現実=事実を小説へと――しかも読み応えのあるエンターテインメント小説へと見事に昇華させている。
では、この国の刑事司法に満ち満ちた矛盾や不正義とは具体的に何か。
挙げはじめればキリはないのだが、さして詳しい注釈も加えずにざっと列挙すれば――①警察に身柄を拘束されるとその警察管理下の留置施設に放り込まれてしまう「代用監獄」、②相変わらず自白偏重の姿勢から脱却できない警察、検察と、密室の中で延々と長時間続けられる苛烈な取り調べ、③被疑事実を否認すれば、起訴後も保釈がなかなか認められず、信じがたいほどの長期勾留が続いてしまう「人質司法」、④警察や検察が捜査の過程で収集した証拠類を独占し、仮に被疑者・被告人に有利な証拠類があっても隠されてしまう陋習、そして⑤各種令状の発付や身柄勾留等の判断を含め、ひたすら検察の言い分に唯々諾々と追随してしまいがちな司法権の砦=裁判所――。
さらにつけ加えるなら、世界的には廃止が圧倒的な潮流となっている死刑制度にいまだ固執し、しかもその運用状況がおそろしく秘密主義的なこと等々もあわせ、いわゆる先進民主主義国の刑事司法ではおよそ考えられないほど後進的な悪弊がいくつも温存されてしまっている。
「制度が正されるまで事件は待ってくれません」
そして本来なら、ここで悪弊の悪弊たる所以をもう少し噛み砕き、わかりやすく解説するべきなのだろうが、その必要を私はいままったく感じない。本作にその大半が盛り込まれ、凝縮して描き尽くされているからである。この点で本作は、悪弊の温存を主導してきた警察や検察といった捜査機関を――同時にそれは強大な国家権力でもあるのだが――平然とヒロイックに描きがちな、まさに凡百のエンターテインメント小説とは明らかな一線を画している。
折しも静岡地裁では袴田事件の再審公判が過日結審し、実に戦後5件目にもなる死刑確定事件での雪冤が果たされるのは確実な状況になっている。鹿児島では、自らの組織の不正をメディアに公益通報した前幹部を口封じで逮捕したとしか思えない警察組織の暴走が現在進行形で引き起こされている。大阪では、地検トップの座に君臨していた元検事正が在職中の準強制性交容疑で逮捕された。だというのに肝心の政治は反応らしい反応を示さず、悪弊の改善に取り組もうという気配さえ皆無に近い。
それでも――。本作の中に印象深い台詞がある。志と熱意に溢れた主人公の新人弁護士を励まし、強力にサポートする〈日本でも指折りの刑事弁護士〉が、被疑者として捕えられて無実を訴える〈増山〉に向けて発した次のような台詞である。
「増山さんは間違った制度の犠牲者なんです。われわれ弁護士はこの日本の刑事司法のシステムそのものと闘って変えていかなくてはならないし、現に闘い続けています。ですが――制度が正されるまで事件は待ってくれません。この間違った現状の中で歯を食い縛り、依頼人のためにベストを尽くすしかないというのも日々の現実です」
たしかにそんな弁護士が――おそろしく数は少ないけれど、現実に存在していることを私は知っている。と同時に、この国の刑事司法システムそのものに改善すべき課題が満ち満ちていて、「変えていかなくてはならない」のが焦眉の課題であることも。
ならば本作は、もとよりフィクションではあるけれど、これも凡百の専門書やノンフィクションよりもはるかに深く現実=事実の核心を突いた1冊として読んでも構わない。いや、多くの人に読まれて現実の課題が課題として広く共有されることを心から願っている。青木 理
#検察の堕落を描き切った異色の小説『人質の法廷』が炙り出す“この国の実態”