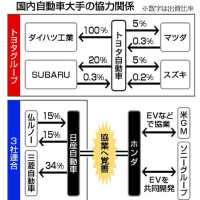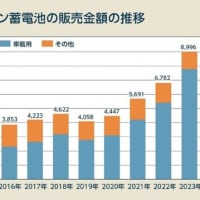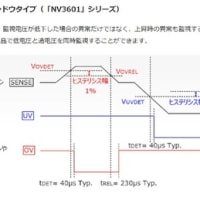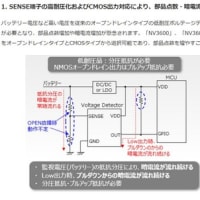今、自動車板金業とか損害保険の調査員(いわゆる技術アジャスター)と云われる方々は、対応単価とレバーレートをどういう解釈をしているのだろう。もしかすると、拙人の意識とは乖離しているのかもしれぬという思いもあり、そもそも導入当時の頃、実際に体験して来たものとして書き留めてみたい。
拙人は、昭和50年代中頃、ある保険会社の専属アジャスタとして業に就くことになった。なお、当時は一般も技術もなく調査員のことを「アジャスター」と命名していた。また、アジャスター制度は昭和50年頃、自研センターの設立と時を同じくして制度化されたが、それ以前は同職のことを「調査人」と称していた。
この昭和50年中頃というのは、自研センターで指数が策定され始め、修理業界に対して実運用が開始されだした時期であった。この指数導入以前の修理費の実態だが、知るところによれば、まず東京地区の大手ディーラー(TP店、TN店などだろう)では、メーカーで策定された工数などはなく、独自にある程度の作業項目について、実額での工賃表を作り運用してきたという実態があった。地方ディーラーでは、この東京の実額工賃表を、参考として物価指数とか人件費などを勘案して、金額を適宜修正して類似の工賃表を作る場合が多かった。
ここで、損保がアジャスター制度および自研センターを設立した目的だが、モーターリゼーションの発達に伴い自動車事故も増えて来たことがある。また、保険会社の収入保険料に占める自動車保険の比率も50%を超え、自動車保険が損害保険の主力商品となって行き、この支払保険金が損保の経営を左右することが明らかなこととして認知されたことがある。つまり、損保側に立てば、交通事故でも支払件数や総額でも圧倒的に多い物損事故の損害査定を適正化することで、無闇に保険料を上げないで、保険会社の経営を健全化したいと云うことだろう。なお、当時は保険料率算定会(現在算定機構)という保険会社の共同集計組織があり、保険料と支払保険金の比率(ロスレシオ)分析をし、独禁法除外で、保険料を上げることができた。
ここで自研センターの設立趣旨だが、業務の半分をアジャスターの研修教育施設としたことだろう。これにより、従来の調査人時代は、属人的な経験と勘に頼る業務を、基礎知識から体系化すると共に、技能ランクを設定し、技能向上を促す制度を行いつつ、対応する研修を実施し出した。もう一つの目的に、従来の金額ベースの工賃表を脱却し、科学的・合理的な工数表を作りたいということがあった。この工数表作りについては、標準作業時間表という形で当初リリースした。つまり、作業者、対象者、使用工具、工場設備など、標準となる一般工場の条件を設定し、その標準的な作業時間表を作ったのだった。
ところが、この標準作業時間というのは、まったく市場で受けいられなかった。それはなぜという問題だが、従来の金額ベースの工賃表は、当時は車種も少なかったのだが、例えば、カローラ、コロナ、クラウンと3車種を並べてみると、ほとんど同構造で固定ボルトの数も同じにも関わらず、その3車のいわゆる車格に応じて料金が設定されていたのだ。これは、科学的な値というより、多分に政策的な、商習慣的な要素が加味されてのことだろう。つまり、カローラより2倍ほどは車両価格の高いクラウンは、例え同じ作業量であっても、より高い整備料金でも付加価値として認めうるだろうといったものだろう。
ここで自研センターでは、標準作業時間をベースにしながらも、一部の作業(これは構造的から車格での差異がない様な作業)に、あえて車格という要素を付加しつつ、名称を指数という名前に変更したのだ。
なお、指数というのは無名数で単位が付かないことを云うのだが、現実には工数と同様にこれに単価を乗じれば作業工賃となる。この自研センターでの指数は、対応する車種も逐次増やしつつ、毎年改定する金額ベースの工賃表より使い勝手が良いこともあったのだろう、市場に普及していったのだった。
さて、やっと対応単価のことに触れるところが来た。この対応単価だが。元々は指数対応単価と呼称していたのだ。つまり指数値に乗じる単価で、レバーレートと類似のものだ。なぜ、旧来からあったレバーレートと別に指数対応単価ができたのかだが、当初は指数の普及を目的に指数を使用する場合には、例としてレバーレート+100円を指数対応単価にしましょうという導入促進的な施策が取られたのだった。
なお、後刻に単に対応単価と呼ぶ様になったのは、これは独禁法絡みで、あらぬ疑念を抱かれたくないという思いが上層部にあったのだと想像する。また、同様に、車格要素を含んだ指数は、純時間とはならないから、指数は時間を元にはしているが純時間ではないという自研センターでの説明がなされていた。しかし、これも独禁法との関わりを怖れ、指数は科学的に求めた時間であると説明が変化したところが面白い。さらに、これは確かめていないが、最近はまた、指数は純時間ではないという説明がされているということらしい。
付記
バブル崩壊後、20年もしくは30年というもの、我が国経済の消費者物価はほとんどインフレの傾向はなく、むしろデフレの傾向すらある。とはいうものの、ものによっては値上がり著しい原材料とか半製品、処理費といったものがある。具体的に上げれば、原油の値上がりによる関連製品の値上げだろう。燃料費もだが、塗料等石油化学製品の値上げは目立つ。一方、処理費として、スクラップ鉄などは上がり処理理として増えないが、樹脂部品や埋立ゴミに類する産業廃棄物処理費の値上がりは無視し得ないほど工場経営に影響を与えつつある。この産業廃棄物処理費については、本来レバーレートの自社算出において、原価部分として工場費に算入して計算すべきものだろう。ところで、およそ20年くらい前だったと思うが、当時対応単価の協定に際して、産業廃棄物処理費の問題が適され、当時の対応単価に+10円が付加されたと説明を受けた覚えがある。しかし、この20年、産業廃棄物はますます増え続け、容積当たりに処理費も値上がりしているが、+10円が妥当性あるとは到底思えない。
拙人は、昭和50年代中頃、ある保険会社の専属アジャスタとして業に就くことになった。なお、当時は一般も技術もなく調査員のことを「アジャスター」と命名していた。また、アジャスター制度は昭和50年頃、自研センターの設立と時を同じくして制度化されたが、それ以前は同職のことを「調査人」と称していた。
この昭和50年中頃というのは、自研センターで指数が策定され始め、修理業界に対して実運用が開始されだした時期であった。この指数導入以前の修理費の実態だが、知るところによれば、まず東京地区の大手ディーラー(TP店、TN店などだろう)では、メーカーで策定された工数などはなく、独自にある程度の作業項目について、実額での工賃表を作り運用してきたという実態があった。地方ディーラーでは、この東京の実額工賃表を、参考として物価指数とか人件費などを勘案して、金額を適宜修正して類似の工賃表を作る場合が多かった。
ここで、損保がアジャスター制度および自研センターを設立した目的だが、モーターリゼーションの発達に伴い自動車事故も増えて来たことがある。また、保険会社の収入保険料に占める自動車保険の比率も50%を超え、自動車保険が損害保険の主力商品となって行き、この支払保険金が損保の経営を左右することが明らかなこととして認知されたことがある。つまり、損保側に立てば、交通事故でも支払件数や総額でも圧倒的に多い物損事故の損害査定を適正化することで、無闇に保険料を上げないで、保険会社の経営を健全化したいと云うことだろう。なお、当時は保険料率算定会(現在算定機構)という保険会社の共同集計組織があり、保険料と支払保険金の比率(ロスレシオ)分析をし、独禁法除外で、保険料を上げることができた。
ここで自研センターの設立趣旨だが、業務の半分をアジャスターの研修教育施設としたことだろう。これにより、従来の調査人時代は、属人的な経験と勘に頼る業務を、基礎知識から体系化すると共に、技能ランクを設定し、技能向上を促す制度を行いつつ、対応する研修を実施し出した。もう一つの目的に、従来の金額ベースの工賃表を脱却し、科学的・合理的な工数表を作りたいということがあった。この工数表作りについては、標準作業時間表という形で当初リリースした。つまり、作業者、対象者、使用工具、工場設備など、標準となる一般工場の条件を設定し、その標準的な作業時間表を作ったのだった。
ところが、この標準作業時間というのは、まったく市場で受けいられなかった。それはなぜという問題だが、従来の金額ベースの工賃表は、当時は車種も少なかったのだが、例えば、カローラ、コロナ、クラウンと3車種を並べてみると、ほとんど同構造で固定ボルトの数も同じにも関わらず、その3車のいわゆる車格に応じて料金が設定されていたのだ。これは、科学的な値というより、多分に政策的な、商習慣的な要素が加味されてのことだろう。つまり、カローラより2倍ほどは車両価格の高いクラウンは、例え同じ作業量であっても、より高い整備料金でも付加価値として認めうるだろうといったものだろう。
ここで自研センターでは、標準作業時間をベースにしながらも、一部の作業(これは構造的から車格での差異がない様な作業)に、あえて車格という要素を付加しつつ、名称を指数という名前に変更したのだ。
なお、指数というのは無名数で単位が付かないことを云うのだが、現実には工数と同様にこれに単価を乗じれば作業工賃となる。この自研センターでの指数は、対応する車種も逐次増やしつつ、毎年改定する金額ベースの工賃表より使い勝手が良いこともあったのだろう、市場に普及していったのだった。
さて、やっと対応単価のことに触れるところが来た。この対応単価だが。元々は指数対応単価と呼称していたのだ。つまり指数値に乗じる単価で、レバーレートと類似のものだ。なぜ、旧来からあったレバーレートと別に指数対応単価ができたのかだが、当初は指数の普及を目的に指数を使用する場合には、例としてレバーレート+100円を指数対応単価にしましょうという導入促進的な施策が取られたのだった。
なお、後刻に単に対応単価と呼ぶ様になったのは、これは独禁法絡みで、あらぬ疑念を抱かれたくないという思いが上層部にあったのだと想像する。また、同様に、車格要素を含んだ指数は、純時間とはならないから、指数は時間を元にはしているが純時間ではないという自研センターでの説明がなされていた。しかし、これも独禁法との関わりを怖れ、指数は科学的に求めた時間であると説明が変化したところが面白い。さらに、これは確かめていないが、最近はまた、指数は純時間ではないという説明がされているということらしい。
付記
バブル崩壊後、20年もしくは30年というもの、我が国経済の消費者物価はほとんどインフレの傾向はなく、むしろデフレの傾向すらある。とはいうものの、ものによっては値上がり著しい原材料とか半製品、処理費といったものがある。具体的に上げれば、原油の値上がりによる関連製品の値上げだろう。燃料費もだが、塗料等石油化学製品の値上げは目立つ。一方、処理費として、スクラップ鉄などは上がり処理理として増えないが、樹脂部品や埋立ゴミに類する産業廃棄物処理費の値上がりは無視し得ないほど工場経営に影響を与えつつある。この産業廃棄物処理費については、本来レバーレートの自社算出において、原価部分として工場費に算入して計算すべきものだろう。ところで、およそ20年くらい前だったと思うが、当時対応単価の協定に際して、産業廃棄物処理費の問題が適され、当時の対応単価に+10円が付加されたと説明を受けた覚えがある。しかし、この20年、産業廃棄物はますます増え続け、容積当たりに処理費も値上がりしているが、+10円が妥当性あるとは到底思えない。