平成27年2月3日(晴れ)
今日はねぎ部会の総会が岩手県の温泉でやることになって、折角なので近くの体験工房で味噌作りを体験してみました。
部会の総会と言っても、議案は役員である自分たちが作っているし、議論する内容は余り無いんだけど、懇親会がメインでこれを楽しみにしている爺さん、婆さん会員も多いし、市場関係者もわざわざ東京から毎回来るんで役員なので自分も参加したんでこの件は別途、掲載します。
ということで、どうせ飲み会なら近場でやってほしかったんだけど隣県まで足伸ばすので時間がもったいないし、皆は旅館の送迎バスで行ったけど、自分はマイカーで行って別行動し、岩手の農家さんの冬作業等を個人見学したり、体験教室を経験したりとプラスアルファが自分の生活感なので自分で計画を立てて有意義な二日間にしました。
先ずは、旅館の近くの町で一日体験工房というのをやっていて、前にもそば打ち体験、豆乳うどん作り体験を経験していて、折角なので今回は味噌づくり体験(費用2500円)をやってみました。本来なら2名以上だけど、電話したら1名でも良いということなのでお願いしました。
会議は14時からだったんで味噌作り体験は午前中にセッティングしました。
体験場は本場の味噌屋さんの工場内に教室用の部屋がつくられてあって、そこで社長さん?が自ら先生を務めてくれました。
行ったら、既にゆで豆が置いてあって作業出来るように準備してありました。

材料は以下になります。
①煮大豆(ミヤギシロメ) 2kg ⇒ 大豆の段階では1kg 一昨日か昨日にぬるま湯に大豆を売るかしてか茹でるそうです。茹で加減加減は豆を手で潰しと2個に分かれるので判れた表面は平らであれば良い水分量と茹で加減だそうです。
②米麹 1kg ⇒ 良い麹は塊があったら、その塊を崩した時に中の米まで麹になっていれば良い麹、麹によっては毛羽立っているのがあるけど、麹に関してはその毛羽立っているところは全く意味無いそうです。麹の見方が判りましたね。
③天日塩 0.5kg ⇒ 自然塩がやはり良いそうです。科学塩は味が出ないから駄目ということでした。
④種水(魔法の水と言ってましたが、普通の水道水でぬるま湯) 0.7kg これが無いと良い味噌が出来ないらしい。
手順(一人作業で手が豆などで濡れているので写真は取れませんでしたので悪しからず)
①煮豆を大きめの器の中で手でつぶします。つぶつぶがほとんどなくなる位潰しますが、潰し残しがあっても麹を投入して撹拌するときも潰せますし、多少、つぶつぶ感があれば手作り感が出るかも!
②次に麹を全部投入して手で撹拌します。
③塩を投入し、手で撹拌します。
④種水を入れて撹拌をしばらくやると生地がしっとりしてきます。これで生地は出来上がりです。
⑤生地を桶に入れます。中に空気が入らない様に撹拌の器から桶に移します。そしてヘラで表面を丸く滑らかにします。
⑥桶の生地の上に薄手のビニールを被せて生地とビニールの間に空気が入らない様にヘラで置けと生地の間にビニールを差し込んでいきます。


⑦生地をすっぽりビニールで覆いかぶせた状態です。完成です。これで4kgの味噌の元が出来上がりました。
※麹100%でこの量であれば盛岡市内のデパートで1200円~1600円で販売されているそうです。楽しみだなあーーー!
⑧落としブタをします。これは自宅に帰ってから重石(0.8kg位)をするためです。

⑨桶に材料、量、作業日、作業者を記録した紙を張り付けて、本日の体験終了です。
概ね1時間位で完成できます。まだ、味噌の匂いはしませんが、煮豆と麹の合わさった凄く爽やかで良い匂いがします。

ということで自宅に持って帰ったところです。概ね1年位で味噌として食せます。1年半位経った頃が一番美味しいということなので楽しみです。

講師さん、お話上手でお味噌に関することをいろいろと教えてくれました。慣れてますね。
何件か記載しておきましょうか。
①麹には米麹、豆麹、麦麹の3種類があり、米麹はお酒やお味噌などに沢山使われていて、ほとんどが米麹が使われている。豆麹は八丁味噌に使われている。麦麹は九州方面で白味噌に使われている。
②味噌作りにおける麹の役割 ⇒ 分解作用と発酵作用
③発酵と熟成の違い ⇒ 分解作用と発酵作用がバランス良く行われることを熟成という
ウイスキーとワインの発酵と熟成の違いなど沢山の事を話して頂きましたが、長くなるので今回はここまで。
楽しかったね。
この2日間、色んな事を経験してきたので、次回は冬農家さん巡りについて、掲載します。
頑張っているんで、プチットお願います。
↓↓↓
百姓の場合はこちら

登山の場合はこちら
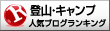
今日はねぎ部会の総会が岩手県の温泉でやることになって、折角なので近くの体験工房で味噌作りを体験してみました。
部会の総会と言っても、議案は役員である自分たちが作っているし、議論する内容は余り無いんだけど、懇親会がメインでこれを楽しみにしている爺さん、婆さん会員も多いし、市場関係者もわざわざ東京から毎回来るんで役員なので自分も参加したんでこの件は別途、掲載します。
ということで、どうせ飲み会なら近場でやってほしかったんだけど隣県まで足伸ばすので時間がもったいないし、皆は旅館の送迎バスで行ったけど、自分はマイカーで行って別行動し、岩手の農家さんの冬作業等を個人見学したり、体験教室を経験したりとプラスアルファが自分の生活感なので自分で計画を立てて有意義な二日間にしました。
先ずは、旅館の近くの町で一日体験工房というのをやっていて、前にもそば打ち体験、豆乳うどん作り体験を経験していて、折角なので今回は味噌づくり体験(費用2500円)をやってみました。本来なら2名以上だけど、電話したら1名でも良いということなのでお願いしました。
会議は14時からだったんで味噌作り体験は午前中にセッティングしました。
体験場は本場の味噌屋さんの工場内に教室用の部屋がつくられてあって、そこで社長さん?が自ら先生を務めてくれました。
行ったら、既にゆで豆が置いてあって作業出来るように準備してありました。

材料は以下になります。
①煮大豆(ミヤギシロメ) 2kg ⇒ 大豆の段階では1kg 一昨日か昨日にぬるま湯に大豆を売るかしてか茹でるそうです。茹で加減加減は豆を手で潰しと2個に分かれるので判れた表面は平らであれば良い水分量と茹で加減だそうです。
②米麹 1kg ⇒ 良い麹は塊があったら、その塊を崩した時に中の米まで麹になっていれば良い麹、麹によっては毛羽立っているのがあるけど、麹に関してはその毛羽立っているところは全く意味無いそうです。麹の見方が判りましたね。
③天日塩 0.5kg ⇒ 自然塩がやはり良いそうです。科学塩は味が出ないから駄目ということでした。
④種水(魔法の水と言ってましたが、普通の水道水でぬるま湯) 0.7kg これが無いと良い味噌が出来ないらしい。
手順(一人作業で手が豆などで濡れているので写真は取れませんでしたので悪しからず)
①煮豆を大きめの器の中で手でつぶします。つぶつぶがほとんどなくなる位潰しますが、潰し残しがあっても麹を投入して撹拌するときも潰せますし、多少、つぶつぶ感があれば手作り感が出るかも!
②次に麹を全部投入して手で撹拌します。
③塩を投入し、手で撹拌します。
④種水を入れて撹拌をしばらくやると生地がしっとりしてきます。これで生地は出来上がりです。
⑤生地を桶に入れます。中に空気が入らない様に撹拌の器から桶に移します。そしてヘラで表面を丸く滑らかにします。
⑥桶の生地の上に薄手のビニールを被せて生地とビニールの間に空気が入らない様にヘラで置けと生地の間にビニールを差し込んでいきます。


⑦生地をすっぽりビニールで覆いかぶせた状態です。完成です。これで4kgの味噌の元が出来上がりました。
※麹100%でこの量であれば盛岡市内のデパートで1200円~1600円で販売されているそうです。楽しみだなあーーー!
⑧落としブタをします。これは自宅に帰ってから重石(0.8kg位)をするためです。

⑨桶に材料、量、作業日、作業者を記録した紙を張り付けて、本日の体験終了です。
概ね1時間位で完成できます。まだ、味噌の匂いはしませんが、煮豆と麹の合わさった凄く爽やかで良い匂いがします。

ということで自宅に持って帰ったところです。概ね1年位で味噌として食せます。1年半位経った頃が一番美味しいということなので楽しみです。

講師さん、お話上手でお味噌に関することをいろいろと教えてくれました。慣れてますね。
何件か記載しておきましょうか。
①麹には米麹、豆麹、麦麹の3種類があり、米麹はお酒やお味噌などに沢山使われていて、ほとんどが米麹が使われている。豆麹は八丁味噌に使われている。麦麹は九州方面で白味噌に使われている。
②味噌作りにおける麹の役割 ⇒ 分解作用と発酵作用
③発酵と熟成の違い ⇒ 分解作用と発酵作用がバランス良く行われることを熟成という
ウイスキーとワインの発酵と熟成の違いなど沢山の事を話して頂きましたが、長くなるので今回はここまで。
楽しかったね。
この2日間、色んな事を経験してきたので、次回は冬農家さん巡りについて、掲載します。
頑張っているんで、プチットお願います。
↓↓↓
百姓の場合はこちら
登山の場合はこちら















