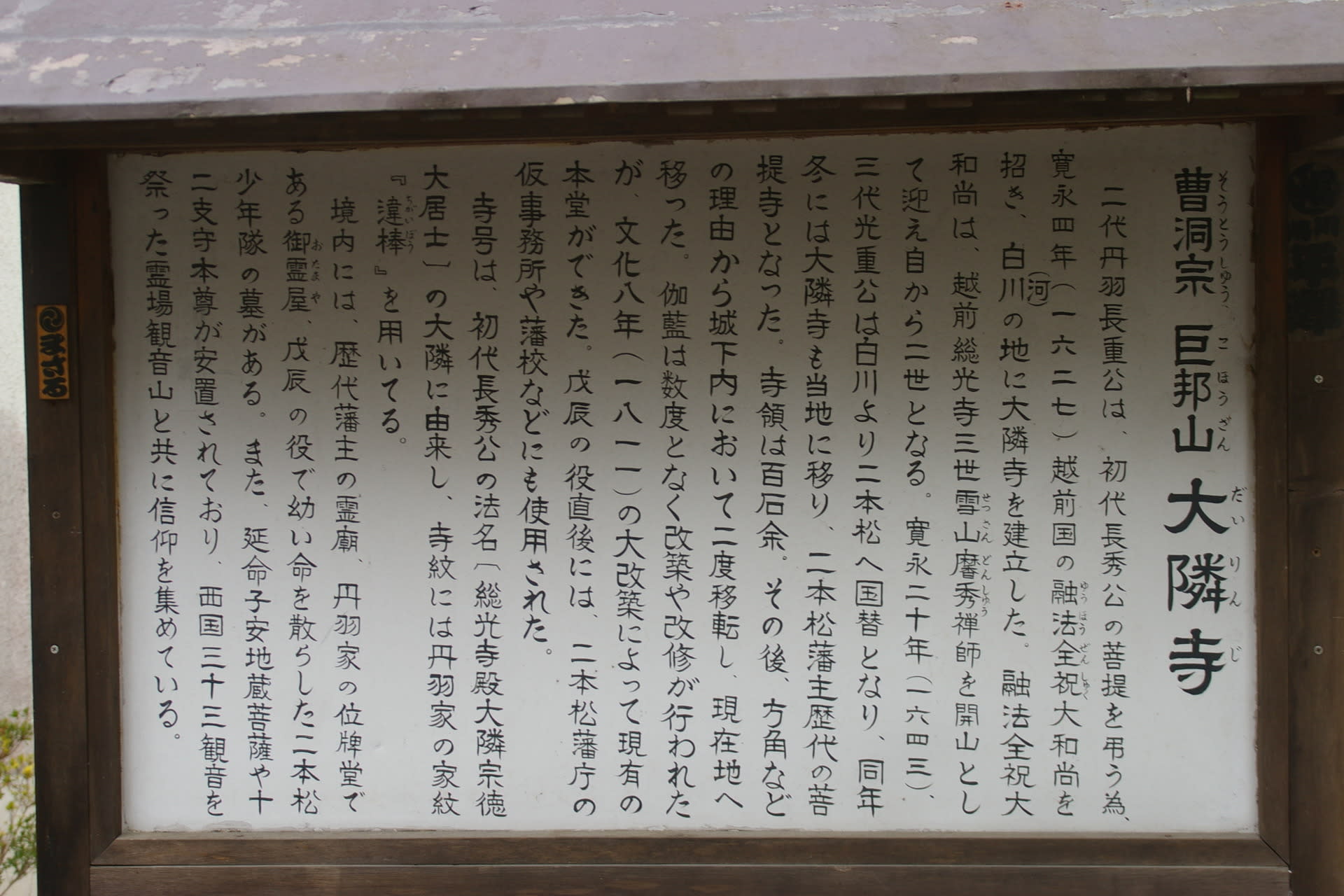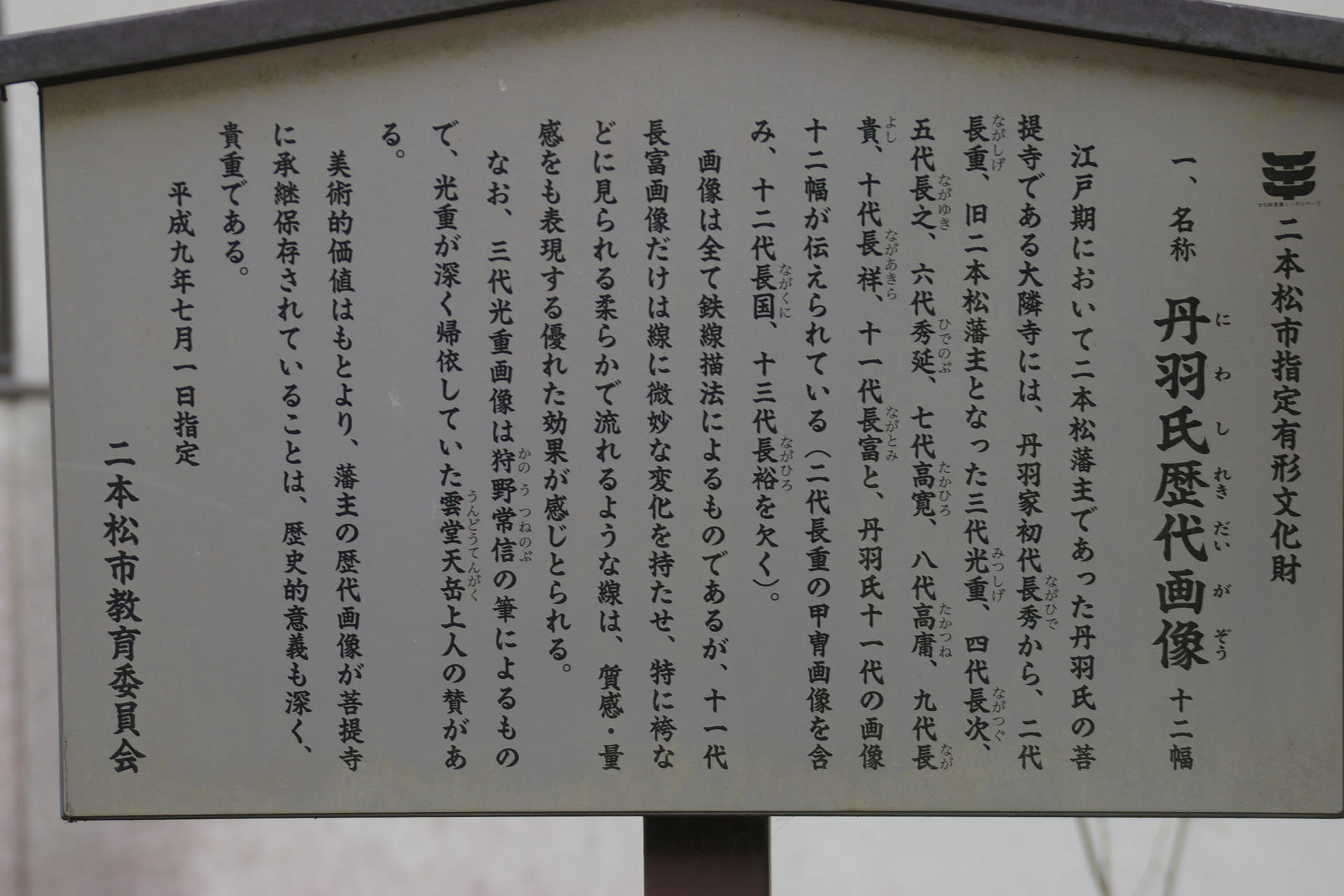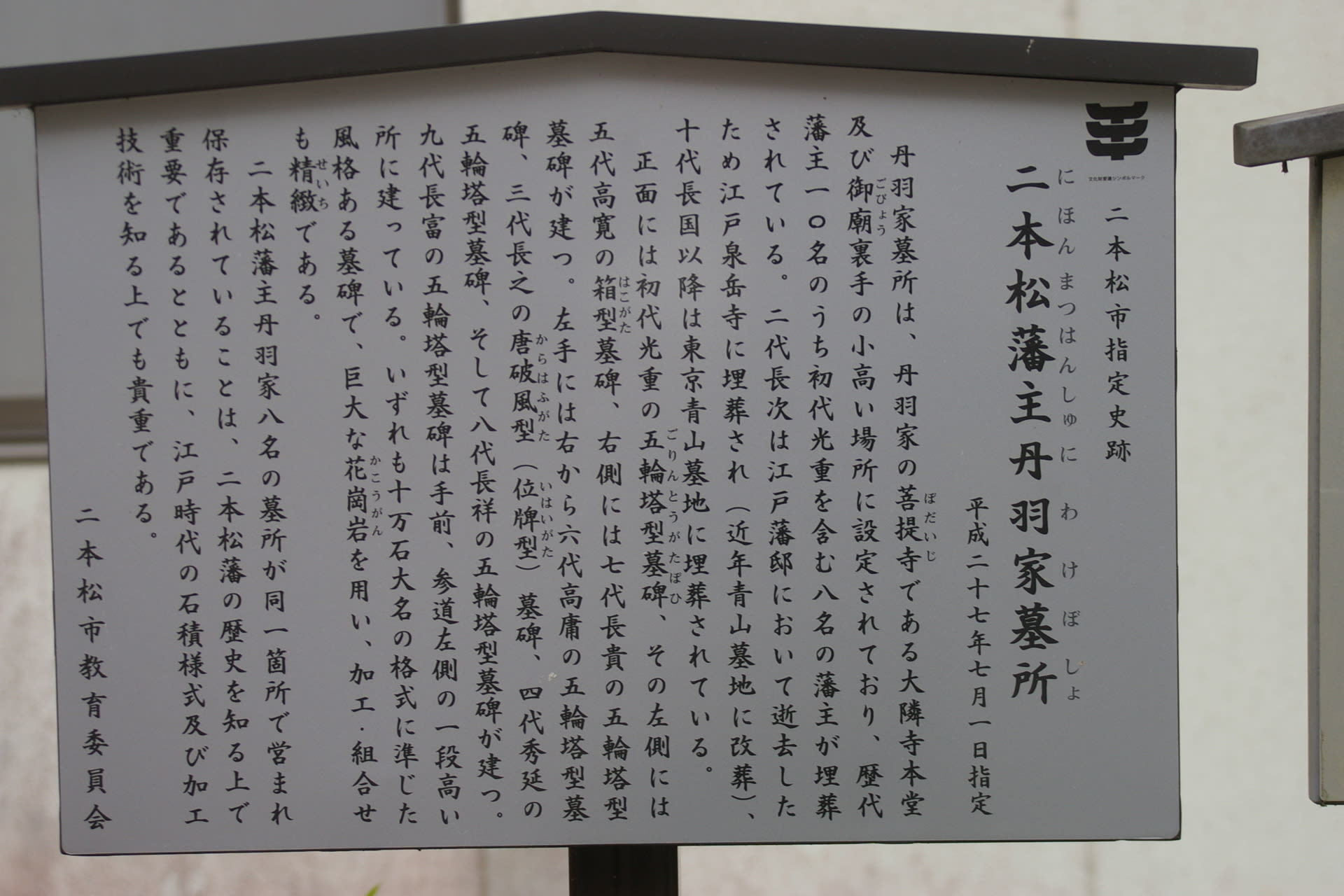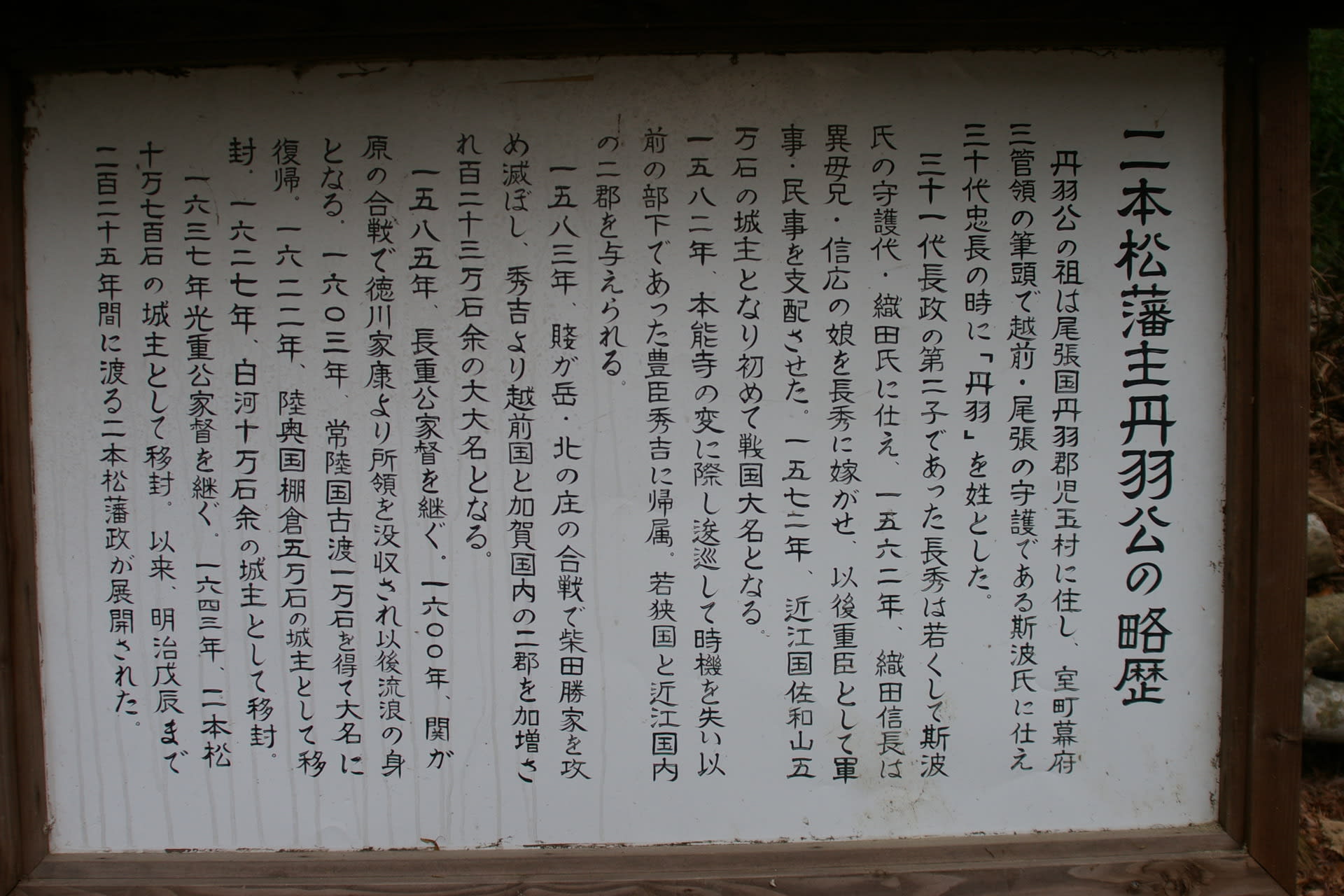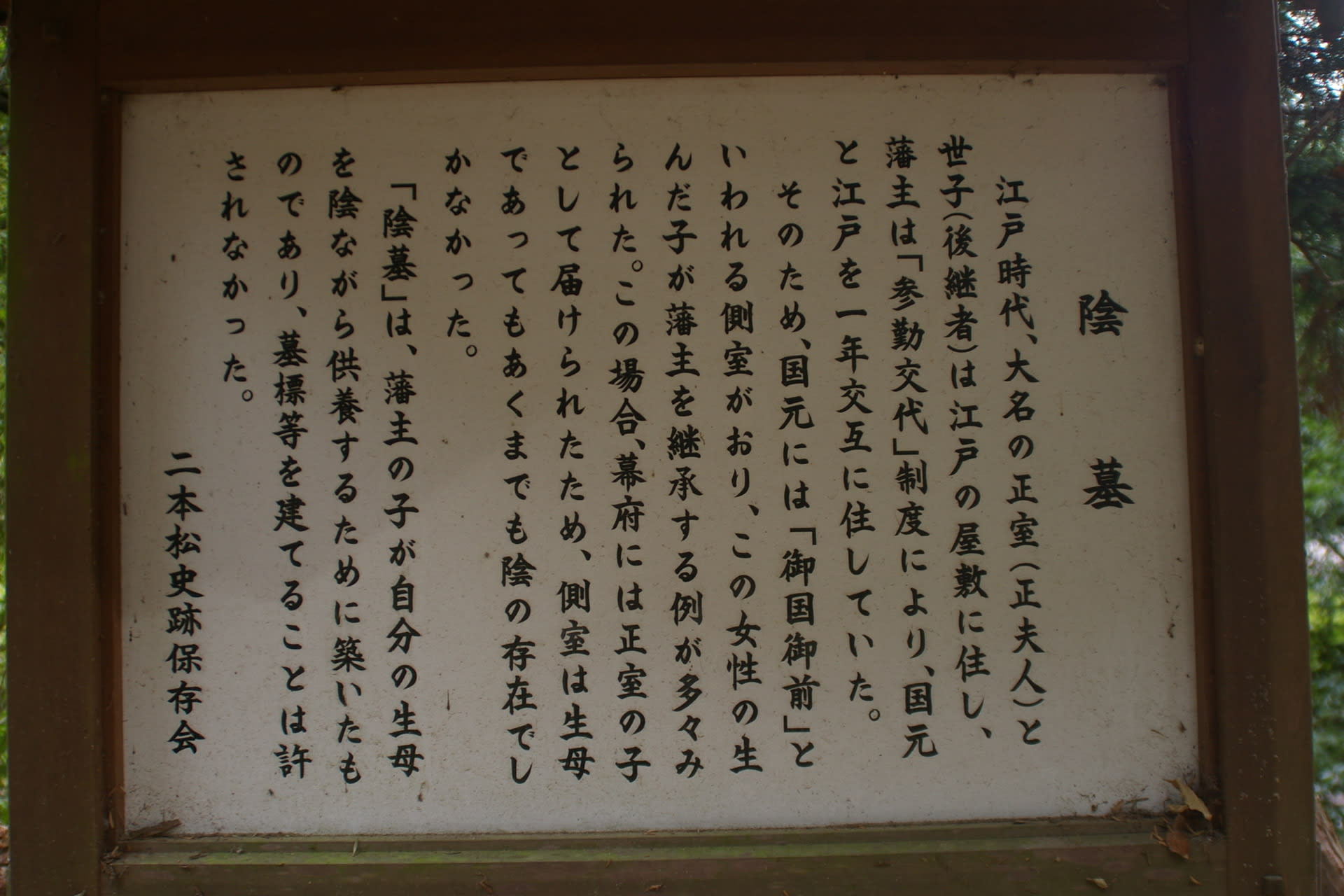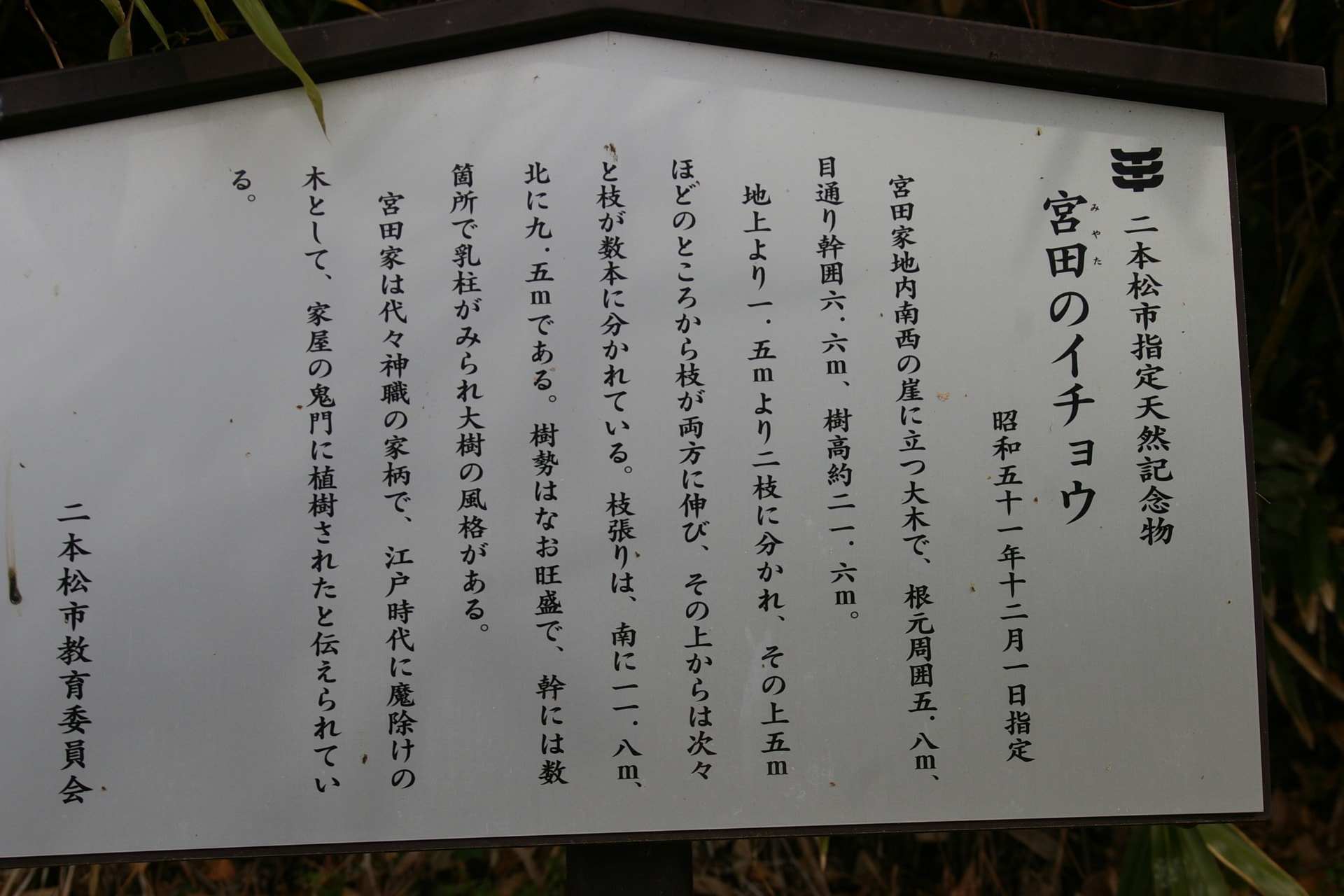初原地区は、大子町役場の北西約9kmのところ
国道461号線から県道205号線を北へ進み
約4kmのところで右手に顕著なイチョウの大木が見えます
県道の広いところに 車を置かせて頂きました
車を置かせて頂きました

熊野神社入り口鳥居です



境内の真ん中に大イチョウが在ります

石碑にイチョウを読んだ歌が彫られています ”銀杏の黄 ゆるうぬ根・り 神思う”





鳥居下から見上げました
説明版等がありませんでしたので、実際に計測してみました
目通り幹回り4,8mの大木です
ギンナンが見当たらないので雄木のようです

社殿代わりの屋根の下に祠が並びます


両端の祠です
では、次へ行きましょう

国道461号線から県道205号線を北へ進み
約4kmのところで右手に顕著なイチョウの大木が見えます
県道の広いところに
 車を置かせて頂きました
車を置かせて頂きました
熊野神社入り口鳥居です




境内の真ん中に大イチョウが在ります


石碑にイチョウを読んだ歌が彫られています ”銀杏の黄 ゆるうぬ根・り 神思う”






鳥居下から見上げました

説明版等がありませんでしたので、実際に計測してみました
目通り幹回り4,8mの大木です

ギンナンが見当たらないので雄木のようです

社殿代わりの屋根の下に祠が並びます



両端の祠です

では、次へ行きましょう