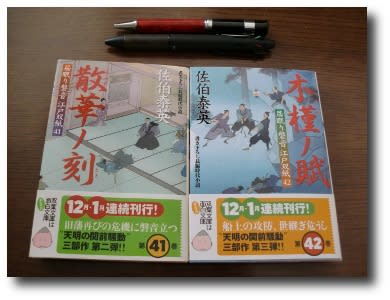前巻では、豊後関前藩の国家老にして坂崎磐音の父親である坂崎正睦が江戸に密行し、江戸家老一派に拉致されたところを救出されるというお話でした。背景にあったのが江戸家老一派の阿片抜け荷であり、さらに背後には田沼意次・意友父子がいるというのですから、ずいぶんとまあ、ご都合主義も甚だしい展開ではありますが、そこはそれ、大江戸エンターテインメントですから(^o^)/
第1章:「睨み合い」。父正睦を救出した磐音は、小梅村の尚武館坂崎道場で弟子たちを指導している毎日です。正睦と速水左近の対談を通じて、一定の目処をつけた上で、懸案解決に向け、磐音は宮戸川の鰻を手土産に、豊後関前藩の江戸屋敷に赴きますが、お代の方の変わりように驚くばかりです。でも、伝えるべき情報はきちんと伝えます。これ、大事。
第2章:「世継ぎ」。磐音は中居半蔵と会い、藩主実高とお代の方夫婦の離間の経緯を告げられます。磐音らが紀州の隠れ里で田沼意次・意知一派の追求をしのいでいたとき、世継ぎのない藩の行く末を思う弱みを突かれ、正室に無断で側室を置いたことが決定的でした。それは、江戸家老・鑓兼参右衛門のたくらみであり、お代の方を籠絡することで藩政の実権を握ろうとするものです。中居半蔵は、国家老・坂崎正睦と会い、反撃の策を練ります。その第一歩は、坂崎正睦がお代の方に対面することでした。
第3章:「堀留の蝮」。組織の職階上は、江戸家老よりも国家老のほうが上位です。このあたりは、本社の専務取締役と支社長との関係のようなものでしょうか。中居半蔵の後任が決まらない物産方の組頭を、国家老の職権で稲葉諒三郎を任命、正式には藩主・実高の上府の際に追認を得ることとして、物産事業はようやく再開されます。深刻な話を中和しようと、武左衛門の放浪のエピソードが挿入されますが、どうもあまり面白くありません。むしろ、物産事業を妨害するやくざ者たちを撃退する利次郎の活躍のほうが面白い(^o^)/
第4章:「祝い着」。紀伊藩剣術指南を藩主直々に命じられた関係で、紀伊、尾張、関前など各藩から尚武館道場に修行に通う者が増加します。縫箔の修行中のおそめは京都に修行に上ることとなり、赤子の祝い着を持参し、小梅村を訪れます。時の流れは、少年と少女を頼もしい若者に変えています。一方、弥助と霧子の調べにより、鑓兼参右衛門と田沼一派との密談内容が判明し、坂崎正睦は速水左近、中居半蔵らと連携をとりながら、藩主・実高の名代として藩邸に乗り込むこととなります。もちろん、磐音は実高の意を体し、護衛として随行します。
第5章:「再びの悲劇」。この章は、江戸屋敷に巣食う鑓兼一派と対決し、勝利を収め、事態の収拾に苦慮する内容ですが、子を持つ・持たぬが自由ではなかった時代が舞台とはいえ、正室お代の方がいささか哀れです。
ところで、国家老がこんなに長期間国元を空けていて、関前藩の行政は大丈夫なのでしょうか。藩主がいるわけだから、最終決裁は大丈夫なのでしょうが、まさか藩主が自ら実務を取り仕切るわけはないので、組織上の代理、補佐役の存在が注目されるところです。
第1章:「睨み合い」。父正睦を救出した磐音は、小梅村の尚武館坂崎道場で弟子たちを指導している毎日です。正睦と速水左近の対談を通じて、一定の目処をつけた上で、懸案解決に向け、磐音は宮戸川の鰻を手土産に、豊後関前藩の江戸屋敷に赴きますが、お代の方の変わりように驚くばかりです。でも、伝えるべき情報はきちんと伝えます。これ、大事。
第2章:「世継ぎ」。磐音は中居半蔵と会い、藩主実高とお代の方夫婦の離間の経緯を告げられます。磐音らが紀州の隠れ里で田沼意次・意知一派の追求をしのいでいたとき、世継ぎのない藩の行く末を思う弱みを突かれ、正室に無断で側室を置いたことが決定的でした。それは、江戸家老・鑓兼参右衛門のたくらみであり、お代の方を籠絡することで藩政の実権を握ろうとするものです。中居半蔵は、国家老・坂崎正睦と会い、反撃の策を練ります。その第一歩は、坂崎正睦がお代の方に対面することでした。
第3章:「堀留の蝮」。組織の職階上は、江戸家老よりも国家老のほうが上位です。このあたりは、本社の専務取締役と支社長との関係のようなものでしょうか。中居半蔵の後任が決まらない物産方の組頭を、国家老の職権で稲葉諒三郎を任命、正式には藩主・実高の上府の際に追認を得ることとして、物産事業はようやく再開されます。深刻な話を中和しようと、武左衛門の放浪のエピソードが挿入されますが、どうもあまり面白くありません。むしろ、物産事業を妨害するやくざ者たちを撃退する利次郎の活躍のほうが面白い(^o^)/
第4章:「祝い着」。紀伊藩剣術指南を藩主直々に命じられた関係で、紀伊、尾張、関前など各藩から尚武館道場に修行に通う者が増加します。縫箔の修行中のおそめは京都に修行に上ることとなり、赤子の祝い着を持参し、小梅村を訪れます。時の流れは、少年と少女を頼もしい若者に変えています。一方、弥助と霧子の調べにより、鑓兼参右衛門と田沼一派との密談内容が判明し、坂崎正睦は速水左近、中居半蔵らと連携をとりながら、藩主・実高の名代として藩邸に乗り込むこととなります。もちろん、磐音は実高の意を体し、護衛として随行します。
第5章:「再びの悲劇」。この章は、江戸屋敷に巣食う鑓兼一派と対決し、勝利を収め、事態の収拾に苦慮する内容ですが、子を持つ・持たぬが自由ではなかった時代が舞台とはいえ、正室お代の方がいささか哀れです。
ところで、国家老がこんなに長期間国元を空けていて、関前藩の行政は大丈夫なのでしょうか。藩主がいるわけだから、最終決裁は大丈夫なのでしょうが、まさか藩主が自ら実務を取り仕切るわけはないので、組織上の代理、補佐役の存在が注目されるところです。