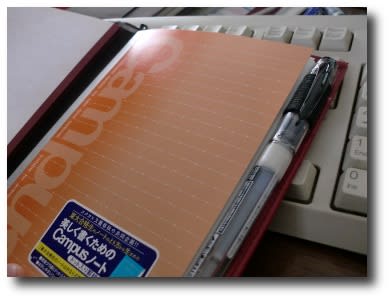プラチナ万年筆で発売している廉価万年筆プレッピー(Preppy)で、同社の古典ブルーブラック・インクを試してみたいと考えました。古典ブルーブラック・インクというのは、酸と鉄(II)イオンを含むもので、青色の染料のせいで筆記時には青く見えますが、鉄(II)イオンが空気酸化されて鉄(III)イオンになり、これが没食子酸などと反応して黒く変色し固着する、という仕組みではなかったかと思います。粘度を調整する等の目的で、タンニン酸なども加えるようですが、昔は耐水性・耐光性が重視され、インクと言えばこの古典ブルーブラックが主流だったはずです。
いつのまにか筆記具の主流はボールペンに移行し、詰まりやすく扱いの難しい古典ブルーブラック・インクは次第に使われなくなり、染料インクに変わっていきました。パイロットもセーラーも、というわけです。ところが、国産ではプラチナが依然として古典ブルーブラックを販売し続けているとのこと。では、その色と変化、書き味を試してみようと、同メーカーで唯一持っている万年筆「プレッピー」をご指名、という経過です。
もともとこのプレッピーは、黒インク・カートリッジで使っていたものです。インクを使いきったので、水洗いしてブルーブラックのカートリッジに替えようと思ったのですが、なぜかプレッピーは水洗いがスムーズに進みません。インクがなかなか水中に出てきません。どうも、ペン軸が普通の構造ではないのでは?と疑ってしまいます。
そんなわけで、中途半端な洗浄になってしまったためでしょうか、どうもインクフローがよろしくない。乾燥も遅く、水分が残っているのか色も薄く感じます。ペン先の細さ(0.3mm)のせいかと思っていましたが、どうもそれだけではなさそうです。プレッピーで古典ブルーブラック・インクを試すには、根気強く使ってみる必要がありそうだ、と覚悟を決めて、辛抱強く使いつづけました。インク・カートリッジが半分ほどの残量になったころには、色の水っぽい薄さもなくなり、本来のインク特性とみなしてもよかろうと判断しました。
で、プレッピーで使ってみた古典ブルーブラック・インクの特徴は:
(1) 色の点からは、青が強めのブルーブラックだと感じます。
(2) ペン先の細さもあるのでしょうが、パイロットと比較すると、インクフローは渋い傾向です。
(3) 各種の用紙に使ってみて、裏抜けしにくい傾向は長所だと思います。
(4) 細字なのにインクが乾くのに時間がかかる傾向があり、書いてすぐにノートを閉じると、反対のページにインクが写ってしまいます。
なるほど、万人向けとは言いにくいが、確かな長所を持った個性的なインクです。うっかり放置すると詰まってしまう可能性があり、高価な万年筆をおシャカにする危険なインクですが、プレッピーのような廉価万年筆との組み合わせであれば、使ってみてもよいかと考えました。とくに、裏抜けするコクヨのドット罫線ノートには、古典ブルーブラック・インクを入れたプレッピーを専用ペンにしてしまうのが良いようです。
いつのまにか筆記具の主流はボールペンに移行し、詰まりやすく扱いの難しい古典ブルーブラック・インクは次第に使われなくなり、染料インクに変わっていきました。パイロットもセーラーも、というわけです。ところが、国産ではプラチナが依然として古典ブルーブラックを販売し続けているとのこと。では、その色と変化、書き味を試してみようと、同メーカーで唯一持っている万年筆「プレッピー」をご指名、という経過です。
もともとこのプレッピーは、黒インク・カートリッジで使っていたものです。インクを使いきったので、水洗いしてブルーブラックのカートリッジに替えようと思ったのですが、なぜかプレッピーは水洗いがスムーズに進みません。インクがなかなか水中に出てきません。どうも、ペン軸が普通の構造ではないのでは?と疑ってしまいます。
そんなわけで、中途半端な洗浄になってしまったためでしょうか、どうもインクフローがよろしくない。乾燥も遅く、水分が残っているのか色も薄く感じます。ペン先の細さ(0.3mm)のせいかと思っていましたが、どうもそれだけではなさそうです。プレッピーで古典ブルーブラック・インクを試すには、根気強く使ってみる必要がありそうだ、と覚悟を決めて、辛抱強く使いつづけました。インク・カートリッジが半分ほどの残量になったころには、色の水っぽい薄さもなくなり、本来のインク特性とみなしてもよかろうと判断しました。
で、プレッピーで使ってみた古典ブルーブラック・インクの特徴は:
(1) 色の点からは、青が強めのブルーブラックだと感じます。
(2) ペン先の細さもあるのでしょうが、パイロットと比較すると、インクフローは渋い傾向です。
(3) 各種の用紙に使ってみて、裏抜けしにくい傾向は長所だと思います。
(4) 細字なのにインクが乾くのに時間がかかる傾向があり、書いてすぐにノートを閉じると、反対のページにインクが写ってしまいます。
なるほど、万人向けとは言いにくいが、確かな長所を持った個性的なインクです。うっかり放置すると詰まってしまう可能性があり、高価な万年筆をおシャカにする危険なインクですが、プレッピーのような廉価万年筆との組み合わせであれば、使ってみてもよいかと考えました。とくに、裏抜けするコクヨのドット罫線ノートには、古典ブルーブラック・インクを入れたプレッピーを専用ペンにしてしまうのが良いようです。