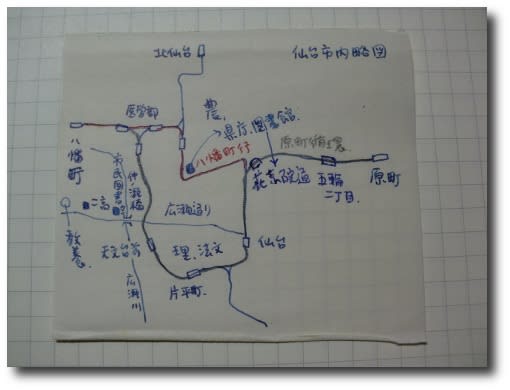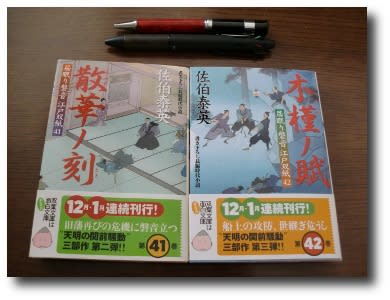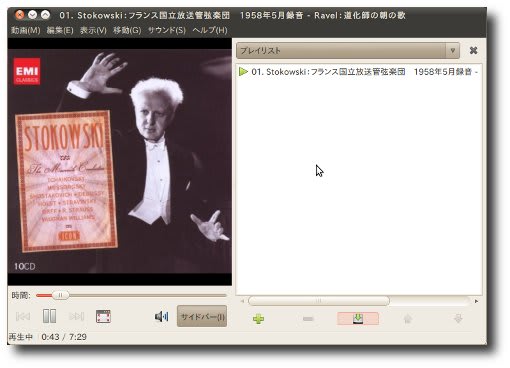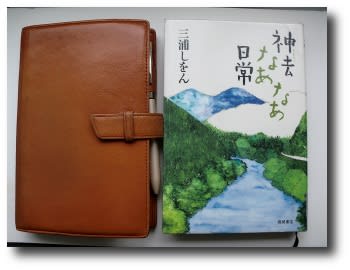ふだんテレビを見ない生活をしているものですから、教育テレビがいつ頃「Eテレ」などという妙ちきりんな名前に変わったのか、とんと気づきませんでしたが、さすがに内容は面白そうな番組をときおり見かけます。たまたま書店で、NHKテレビテキストに「100分de名著」なるシリーズがあり、この2月は佐藤賢一さんがデュマの『モンテ・クリスト伯』を取り上げるということを知りました。
当方、『モンテ・クリスト伯』は長年の愛読書(*1)でありますし、父デュマ将軍を描いた佐藤賢一さんの『黒い悪魔』を、先ごろ面白く読んだばかり(*2)です。毎週水曜日の午後11時から11時25分までという放送時間は、早朝に起床することが必要な当方の生活スタイルからはいささか無理があります。でも、再放送(5:30~5:55)および再々放送(0:25~0:50)ならば見ることができそうです。たまに興味を持ったテレビ番組はおもしろいことが多いので、これは楽しみです。
(*1):デュマ『モンテ・クリスト伯』を読む~「電網郊外散歩道」連載全14回
~(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13),(14)
(*2):佐藤賢一『黒い悪魔』を読む~「電網郊外散歩道」2012年12月
当方、『モンテ・クリスト伯』は長年の愛読書(*1)でありますし、父デュマ将軍を描いた佐藤賢一さんの『黒い悪魔』を、先ごろ面白く読んだばかり(*2)です。毎週水曜日の午後11時から11時25分までという放送時間は、早朝に起床することが必要な当方の生活スタイルからはいささか無理があります。でも、再放送(5:30~5:55)および再々放送(0:25~0:50)ならば見ることができそうです。たまに興味を持ったテレビ番組はおもしろいことが多いので、これは楽しみです。
(*1):デュマ『モンテ・クリスト伯』を読む~「電網郊外散歩道」連載全14回
~(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13),(14)
(*2):佐藤賢一『黒い悪魔』を読む~「電網郊外散歩道」2012年12月