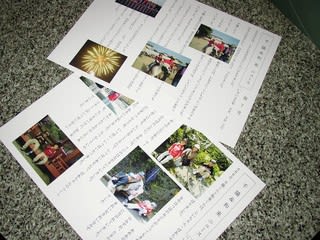孫達の歓声を聞きながらタマネギを収穫したのがおととい。秋のサツマイモ収穫の歓声を期待してタマネギの後の畑作りに精を出したのが昨日。
そして今日は、朝一番に皮膚科に駆け込む羽目になった。憂鬱この上ないおはなし。
サツマイモ苗を100本、量販店に予約した。来週中にはどうしても植え付けをしなければならない。そんな必要に迫られてタマネギの後の畑作りをしていたら、突然左上腕部にヒリヒリっと何かイヤーな予感。「毛虫にやられたか…!」
道具もなにも放り投げ一目散に家の中。先ずヒリヒリ部分をガムテープでペタペタ貼っては剥がすおまじない。(毛虫の毛が肌に付いているのを吸着させるため)
次はシャワーで思いっきり洗い流す。これでOK…と思いきや、毛虫はそんなに甘くない。あれよあれよという間に左腕を覆う発赤。一晩は市販のかゆみ止めで応急処置。
夜中から今朝方にかけて、眠らせてもらえないほどの痒みと痛み。やっとこらえて一夜を明かし、何はともあれ皮膚科に駆け込んだというお粗末。
実は今夜、自分で計画、一次会・二次会の予約まで全て手配してある職場の懇親会。しかも瀬戸内海の潮風に吹かれる露天風呂付き。
何が何でも行かねばならぬ。皮膚科の先生からもOKのお墨付きを取り付けた。
間もなくお迎えが来る。この楽しみを毛虫なんかに邪魔されてなるものか。ユーウツなど吹き飛ばし、呑んでしゃべってマイクを持って……いつものパターンを想像してはみるものの、毛虫の奴めよくぞここまで美味しくもない老化皮膚を食い荒らしたものだ。それとも、毛虫にとってはまだ賞味期間中と認めてくれるのか。
いずれにしても、これからしばらくは皮膚科の出番の時期らしい。特にドクガやチャドクガの毛虫には充分ご注意あれとのこと。面の皮も薄いが腕の皮はもっと薄いと思われる人も、面の皮だけは厚い人も毛虫にはご用心あそばせ。虫が好かぬといって無視出来ればいいが、虫も殺さぬ顔をしていると虫が寄ってきて、遊蛾などと言ってはいられませんですぞ。
(写真:みっともない上腕発赤に替えて、ユーウツを表現する曇り空)
そして今日は、朝一番に皮膚科に駆け込む羽目になった。憂鬱この上ないおはなし。
サツマイモ苗を100本、量販店に予約した。来週中にはどうしても植え付けをしなければならない。そんな必要に迫られてタマネギの後の畑作りをしていたら、突然左上腕部にヒリヒリっと何かイヤーな予感。「毛虫にやられたか…!」
道具もなにも放り投げ一目散に家の中。先ずヒリヒリ部分をガムテープでペタペタ貼っては剥がすおまじない。(毛虫の毛が肌に付いているのを吸着させるため)
次はシャワーで思いっきり洗い流す。これでOK…と思いきや、毛虫はそんなに甘くない。あれよあれよという間に左腕を覆う発赤。一晩は市販のかゆみ止めで応急処置。
夜中から今朝方にかけて、眠らせてもらえないほどの痒みと痛み。やっとこらえて一夜を明かし、何はともあれ皮膚科に駆け込んだというお粗末。
実は今夜、自分で計画、一次会・二次会の予約まで全て手配してある職場の懇親会。しかも瀬戸内海の潮風に吹かれる露天風呂付き。
何が何でも行かねばならぬ。皮膚科の先生からもOKのお墨付きを取り付けた。
間もなくお迎えが来る。この楽しみを毛虫なんかに邪魔されてなるものか。ユーウツなど吹き飛ばし、呑んでしゃべってマイクを持って……いつものパターンを想像してはみるものの、毛虫の奴めよくぞここまで美味しくもない老化皮膚を食い荒らしたものだ。それとも、毛虫にとってはまだ賞味期間中と認めてくれるのか。
いずれにしても、これからしばらくは皮膚科の出番の時期らしい。特にドクガやチャドクガの毛虫には充分ご注意あれとのこと。面の皮も薄いが腕の皮はもっと薄いと思われる人も、面の皮だけは厚い人も毛虫にはご用心あそばせ。虫が好かぬといって無視出来ればいいが、虫も殺さぬ顔をしていると虫が寄ってきて、遊蛾などと言ってはいられませんですぞ。
(写真:みっともない上腕発赤に替えて、ユーウツを表現する曇り空)