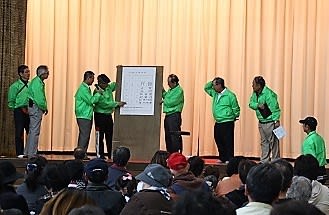あたたかき 十一月も すみにけり 中村 草田男
今年の11月は、格別あたたかきわけでもなかった。むしろ平年に比べると寒い方の部類かもしれない。
そんな11月も今日でおしまい。12枚あった暦もいよいよ1枚を残すのみ。
明日から師走。その名を聞くだけでなんとなく気ぜわしさを覚える今年最後の1か月となる。
1年を総括するにはいささか時期尚早の感もあるが、一つ大きな転機を迎えた業界もある。
それが日本の国技と呼ばれる「大相撲」の世界。特にこの1年を締めくくるべく本場所九州場所の最中に持ち上がった横綱による平幕力士への暴行事件。今さらすったもんだの経緯や、だれがどうした、なんと言ったなどは述べるまでもなく、先刻ご承知のことであろう。
日本放送協会という名の公共放送NHKでさえ、他に重要なニュースはないのか?と一喝したくなるほどの過熱ぶりで、「横綱暴行事件」を連日連夜トップニュースとして取り上げた。国会審議も予算委員会も、北朝鮮ミサイルも、かすんでしまうほどの報道量であった。
だから、それにWAをかける民間の午後番組など、これでもか、これでもか・・・と映像や画像を繰り返す。
挙句の果ては、相撲界の勢力争いがちらり。横綱審議委員会の確固たる結論も出ない。という何もかもイマイチ釈然としない中で「結論ありき」のように当事者の横綱日馬富士は引退した。このことに対しては賛否両論が拮抗。小生自身も賛否相半ばである。
但し、暴力はダメという信念だけはゆるぎない。そして、相撲は日本の国技と言うからには、外国人であろうと、地位が何であろうと、人間的なマナー・品格・お相撲さんと言う憧れの世界であることなどを、誰がどのように指導、協育しているのか、そこが知りたい。
何かことが発覚したらそこで、付け焼刃的対処を講じる。そこにこそ問題あり。
事件や問題が発覚する前に、そういったことを予知しながら、危機管理をするのが八角理事長の手腕である。
根元を断つ対策を講じ、難題や軋轢が発覚しないよう、八角理事長に改めて物申したい、一相撲ファンである。