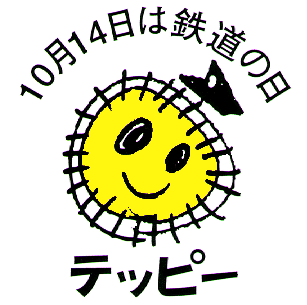夕焼け雲と共に去りゆく10月
冷えた空気がとても爽やかで、絵に描いたような晩秋の陽射しで迎えた10月最後の朝。
お昼前には一天にわかにかき曇り、時雨と言うには余りにも大粒の、音を立てる雨が落ちて来た。それも束の間、寒さだけを置いて雨雲は遠ざかる。
夕方には、西の空をあかねに染める夕焼けショー。夜に入れば、立待月と言われる17夜の月が孤光を放つ。去りゆく10月との別れを惜しんでいるように。
遠く海外では、ハローウィンのお祭りに思い思いの仮装や、カボチャの彫刻で賑わっていることだろう。幼い孫やその両親が、楽しい一夜を過ごすことを願う人も少なくない。
明日からいよいよ11月。第2回目をキックオフした岩国検定試験実施まで1カ月。
昨年から今年前半にかけて、畑づくりとも言うべき検定用テキスト作りの下地を練り上げて来た。元肥を入れ、草取りを欠かさず何度となく耕す。
また肥やしを入れるまた耕す。そうして作り上げた畑にタネを蒔いた。テキストブックという花はたちまち皆さんの手に渡り、それぞれに飾ってもらった。
ところが肝心な検定試験受験という実が多く実ってくれていない。今のところ。
テキストブックという花を愛でることで、おおよそ岩国のことは理解したということなのだろうか。そりゃないぜよ皆様方よ。せっかくいいテキストを手にして勉強されたのなら、その実力のほどを是非試してみては如何でしょう。100点取れたら免許皆伝。それ以外は今一度テキストブックの読み直し。そうすることで本当の「いわくに通」と言える資格を得られるんよ。花泥棒は罪を問わない日本の文化を知ってはいるが、ここでは花だけを持ち逃げしないで~~。一緒に実を結ばせてみましょうよ。
と、アカネの夕日に願かけしてみた。やはり昇る朝日の方がご利益あるのかな~。
でも季節は秋。となれば夕日の値打ちが最も高く評価されるのは今である。
なんだかんだ言いながら、いよいよ追い込みの細かい作業を一つ一つ乗り越えて、万全の態勢を整えるのが我らの仕事。
受験申込期限11月15日。この半月でどのような実が生るか。乞うご期待!!
みなさ~~ん、お待ちしていますよ~~~!!














 鞍馬駅の壁に赤天狗と烏天狗が
鞍馬駅の壁に赤天狗と烏天狗が