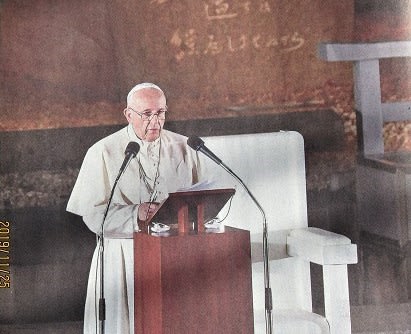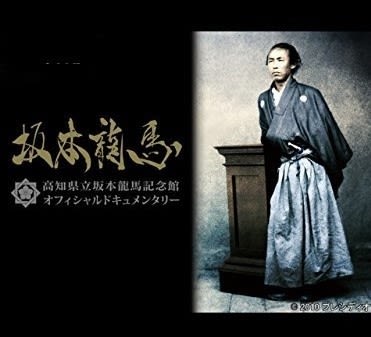庭のサザンカのつぼみが膨らみ、真っ紅な花を咲かせ始めると、1枚余分に羽織る物が欲しくなる。
気がつけば11月も今日がつごもり。明日から師走の風となるのだから、キュッと身の締まる寒さを覚えるのも無理はない。
ただ、日本列島は縦長に広いので、中国地方でも瀬戸内海に面した九州寄りの我が住む町は、まだまだこの程度の寒さで済んでいる。
今夕のテレビに映し出される秋田県のある町などは、家々の屋根も畑も、すでに雪景色であった。
そしていよいよ暦も残すところ1枚になってしまった。
月が変わればいよいよ忘年会のシーズンである。
有り難いことに、三連チャンを含めてすでにいくつかの予定が組まれている。
お声をかけてもらえるうちが花、という信条に基づいて、ダブらない限り出席する方向でご返事をしている。
などと言うと声を掛けられる側にばかりいるようであるが、実はそうでもない。忘年会の回数が少なければ、こちらから声を掛けて主催者に廻ることも多い。
いずれにしても、かつて繁華な夢舞台であった駅前の賑わいが、いつの間にか寂れたゴーストタウンと化している現状に淋しさを覚える。
知った顔に2度も3度も出会っていた若い頃を思い起こすと、駅前が賑わい、帰りのタクシーを待たされることこそが、町の活気の原点であったと思っている。
そんな遠い、しかも錯覚かもしれない昔を今もって追いかけていたら「歳を考えて」などと叱られるかもしれない。
が、あまり景気のいい話が聞かれない現状では、どうしても活気のある話は、たとえ少しでも心地よく耳に馴染む。
霜月つごもりまでは色んなことがあった今年。せめて残りの1ヶ月は穏やかで、少しは耳に馴染む話が聞ける年で終わりたいものだ。