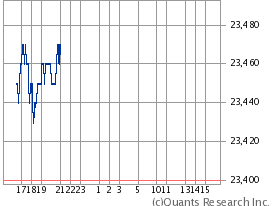(海洋または大気に放出か トリチウム水処分 近く提言まとめへ)

① ""海洋または大気に放出か トリチウム水処分 近く提言まとめへ””
2019年11月18日 20時43分 福島第一
👤👥 福島第一原子力発電所にたまり続けるトリチウムなどを含む水の処分方法について、 国の有識者会議では海洋か大気に放出する案を中心に今後、議論が交わされる見通し となりました。
国は近く提言をまとめたいとしていますが委員からは風評被害の影響などの議論が不足しているとの意見もだされ、会議の行方が注目されます。
福島第一原発で出る汚染水を処理したあとの水には、取り除くのが難しいトリチウムなどの放射性物質が含まれ、構内のタンクには現在およそ117万トンの水が保管され、毎日170トン前後、増え続けています。
18日、都内で開かれた国の有識者会議では東京電力が今後、環境中に放出した場合の水の総量とトリチウムの量について試算した結果を初めて示しました。
それによりますと、2035年まで保管を続けたあと放出する場合、貯蔵量は今の1.7倍に増えますが、トリチウムの総量はおよそ13%減るなどとしました。
また国と東京電力は海洋と大気に放出した場合の人への影響の試算も示し、いずれの方法でも被ばく量は通常、自然界から浴びる量よりも十分に小さいとしたうえで、海洋に放出したほうが、大気に出した場合に比べ、半分以下になるとしました。
🏢 経済産業省は、論点の整理は進んできたため、早ければ次回の会合で提言をまとめたいとしていて、実績がある海洋放出と大気放出の案を中心に議論が進む見通しとなりました。
一方、一部の委員からは風評被害の影響などについて議論が不足しているという意見が出され、会議の行方が注目されます。
初の試算結果「トリチウム水の総量とトリチウムの量は」

トリチウムなどを含んだ水は原子炉の中に残る核燃料を冷やしたあとに汚染されて出てくる水を処理したもので、その発生量は事故以降8年半余りの間、徐々に減ってきているものの、現時点でも毎日170トン前後発生していて、貯蔵量は117万トンにまで増え、タンクの基数もおよそ1000基に達しています。
一方、放射性物質のトリチウムは時間と共に放射線を出す力が弱まり、放射性物質としての能力が無くなっていく性質があります。
こうしたことを踏まえて、国と東京電力は18日、現在のトリチウム量のほか、来年2020年、その5年後の2025年、2030年、2035年のそれぞれの時期まで貯蔵を続け、放出を待った場合の水の総量とトリチウムの量の試算結果を初めて示しました。
それによりますと、 ▽先月末時点の(10月まつ)貯蔵量117万トンの水に含まれるトリチウム量は856兆ベクレルと推定されるということです。
この856兆ベクレルというトリチウムの量は福島の事故前、国内すべての原発から海に出ていたトリチウムの1年間(5年平均)の量の2.2倍ほどにあたるということです。
また、海外と比較しますと、韓国の原発から去年1年間に海に出された量の(2018年)およそ4.2倍にあたるということです。
試算では、
▽仮に2025年までタンクに保管し続けて放出する場合の総量は現時点より33万トン増加し、150万トンとなります。またトリチウムの総量はおよそ870兆ベクレルまで増加するということです。
▽2030年まで保管し続けて放出する場合は水の総量は175万トンまで増えます。一方、トリチウムの総量は減衰が進んだことでおよそ820兆ベクレルに減ります。
▽さらに2035年に放出した場合は、総量は200万トンとさらに増加します。一方、トリチウムの量はさらに下がりおよそ740兆ベクレルと試算されるということです。
試算の結果、一定期間、保管すると、 ▽タンクでの水の貯蔵量は増加する一方で、▽トリチウムの量は低下していくことになります。
ただしタンクの増設を巡っては、東京電力は現在の計画では3年後の2022年夏ごろにいっぱいになるとしていて、その後も増設を続けるためには、 ▽いずれ原発の敷地の外に設置することが必要になるほか、 ▽タンクの老朽化などの問題も出てくるとして、長期のタンク保管には否定的な見解を示していて、国は難しい選択を迫られています。
海に放出「自然界で被ばくする量と比べて最大およそ3400分の1」

18日の会合では、これまで実績のある
▽海に放出する方法と ▽水蒸気にして大気に放出する方法について、
被ばくする量の試算結果も示され、国と東京電力はいずれの方法でも影響は十分に小さいと評価しています。
試算は国連科学委員会のモデルに基づいて行われました。
このうち、海への放出では、100年間にわたって、毎年およそ860兆ベクレルのトリチウムをほかの放射性物質とともに薄めて放出したとの条件を置いて計算したということです。
そして砂浜での被ばくや魚介類の摂取による被ばくを試算したところ、年間の被ばく量は一般の人が通常、自然界で被ばくする量と比べて最大およそ3400分の1になったということです。
また、同じように100年間、毎年およそ860兆ベクレルのトリチウムなどを大気に放出する場合は、5キロ離れた地点での年間の被ばく量が一般の人の自然界での被ばく量と比べておよそ1600分の1になったということです。
これについて経済産業省と東京電力は実際のトリチウムの量よりもはるかに多い量で試算した結果だとしたうえで、
▽いずれの方法でも被ばく量は一般の被ばく量と比較して十分に小さく、▽海への放出は大気への放出と比べて半分以下の影響となることがわかったと評価しています。
※ 経済産業省と東京電力 ➡ 今までの経緯を見ていて凡太郎は原子力行政においては、一番信用をおけない組織と会社だと考えています。
有識者「まだ未知の状況。かなり慎重に議論しないといけない」
👤 国の有識者会議の会合のあと、委員を務める福島大学の小山良太教授は「技術的、科学的にできることはわかってきたが、実際には社会や地域、あるいは海外でどういう影響が起きるのか、まだ未知の状況にある。
地域の産業の復興がようやく進んできている段階でもあるので水を海などに放出し、処分するというのはかなり慎重に議論しないといけない」と話し、風評被害の影響を含めてさらに議論を深める必要があるとしています。
NPO「タンク増設し長期保管、放射能が減るメリットも」
国の有識者会議が海洋放出と大気放出の案を中心に議論を進めるとしていることについて、原子力政策に提言を続けているNPO法人・原子力資料情報室の伴英幸共同代表は、選択肢を絞り込むにはまだ議論が足りていないとしたうえで、「例えばタンクを増設して長期に保管する選択肢は、放射能が減るメリットがあり、地元の住民などからも求められていると思う。
タンクをつくるには原発の敷地にスペースが確保できないといったネガティブな議論が先行していて、ほかの選択肢を掘り下げる議論になっていない。会議全体が基準以下に薄めて環境中に流せばよい、という方向に安易に向かっているのではないか」と話しています。