
二十四節気の夏至(昼が最も長く、太陽の南中高度が最北に達する)には、72候の乃東枯6/21~25、菖蒲華6/26~7/1、半夏生7/2~6の3候の節気で、今日7/2は葉が半分白くなる半夏生が見えるころの始まりの日であり、薬草半夏(からすびしゃく)の生えるころでもある。
また、農作業が一段落し、半夏雨といって大雨が降るので、この5日間を休みとしていた。働き者を戒めるためにも、近畿や福井地方では、毒気が舞うから、井戸に蓋をし、外の野菜は食べず、玄米餅やうどん、タコやサバを食べて過ごす風習があった。我が家でも昨夜はサバの味噌煮を、今日も頂く。
この半夏生は夏至が過ぎると葉の表面が白く変化し花弁の役を果たすドクダミ科多年性落葉草本植物であり、地域では絶滅危惧種で、これと似た葉を持つものに、落葉蔓性木本のマタタビがある。33歳過ぎた頃の我妻もこのマタタビの実には病でお世話になった。
夏梅ともよばれるマタタビは、猫が恍惚を感じることで一般に知られており、葉は細かい鋸の楕円形が互生し、葉柄があり、6月から白い2cm位の花をつける。虎なども恍惚するし、猫はイヌハッカにも恍惚する。こんなことから、うっとりしていることで「ねこにまたたび」の言葉が生まれた。写真左マタタビ(6/15撮影)で葉柄の左下に白い花が見える、右が半夏生。
また、農作業が一段落し、半夏雨といって大雨が降るので、この5日間を休みとしていた。働き者を戒めるためにも、近畿や福井地方では、毒気が舞うから、井戸に蓋をし、外の野菜は食べず、玄米餅やうどん、タコやサバを食べて過ごす風習があった。我が家でも昨夜はサバの味噌煮を、今日も頂く。
この半夏生は夏至が過ぎると葉の表面が白く変化し花弁の役を果たすドクダミ科多年性落葉草本植物であり、地域では絶滅危惧種で、これと似た葉を持つものに、落葉蔓性木本のマタタビがある。33歳過ぎた頃の我妻もこのマタタビの実には病でお世話になった。
夏梅ともよばれるマタタビは、猫が恍惚を感じることで一般に知られており、葉は細かい鋸の楕円形が互生し、葉柄があり、6月から白い2cm位の花をつける。虎なども恍惚するし、猫はイヌハッカにも恍惚する。こんなことから、うっとりしていることで「ねこにまたたび」の言葉が生まれた。写真左マタタビ(6/15撮影)で葉柄の左下に白い花が見える、右が半夏生。














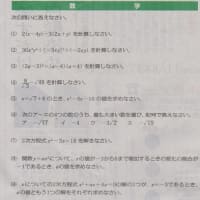


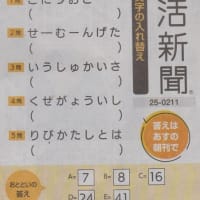


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます