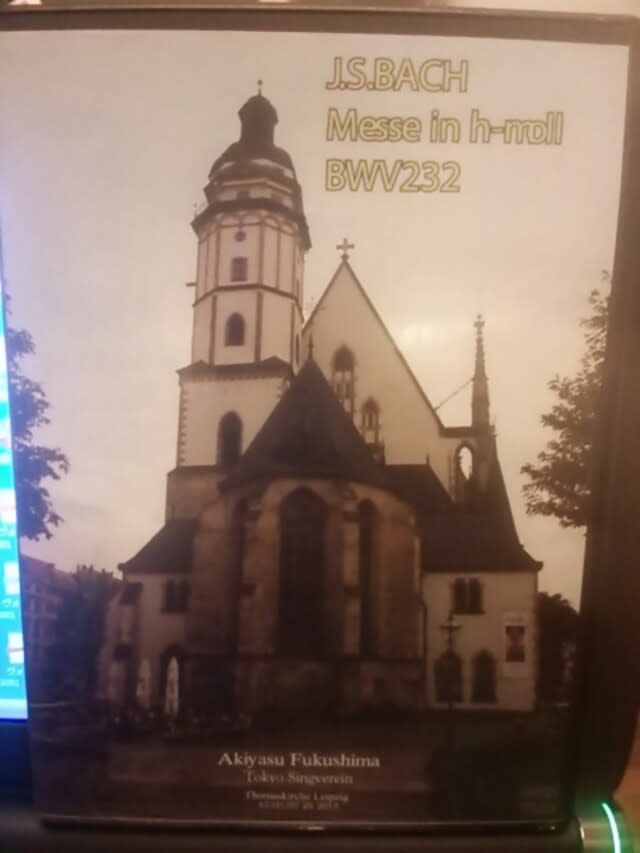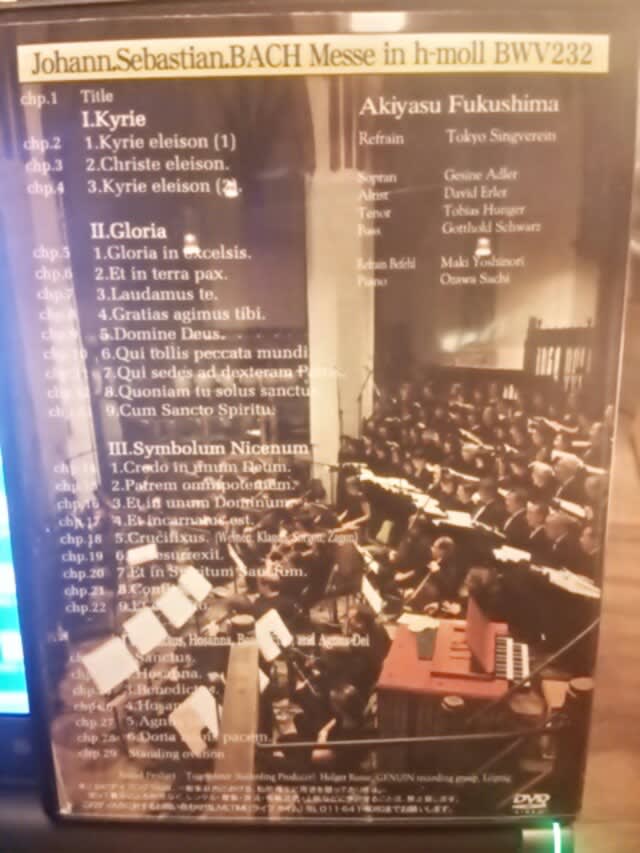「朝比奈の方がずっと良かった。比較にならない」
という記事に関して、本日、以下のコメントを頂戴した。
「音楽を聴く耳をお持ちじゃないですよね。
お気の毒としかいいようがありません。
まぁ、頑張ってください。
ご活躍をお祈り申し上げます。」
甚だ無礼なモノの言いようなので、黙って削除しても良かったのだが、
同じように思われている方もいるかも知れないので、これを与えられた良い機会として私の考えを述べておこう。
まず何といっても、ティーレマンの指揮は良くなかった。
ティーレマンのアプローチが、緩急の極端なテンポ設定など、オールドファッションだったからではない。
フルトヴェングラー流だろうが、クナッパーツブッシュ流だろうが、音楽が良ければ、どうでも良い。
指揮に限らず、すべての器楽、声楽を究めるに於いて、「脱力」は基本である。
音楽のみならず、武術、スポーツ、書道、舞踊・・・、すべての芸事はそうではないであろうか?
それを、あんなに力ずくでオーケストラをドライヴする、というのは、暴力的な快感でしかない。
「ああ。、ウィーン・フィルが悲鳴を上げながら弾いている」と私は感じた。
もっとも、それを好きだ、という人がいても、非難するつもりはないけれど、私は与しない。
しかし、あんなに力の入った棒振りでは、その衝撃から首に掛かる負担は相当だろう。
かつての岩城宏之のように、将来、故障してしまわないか心配になるほどだ。
(しかし、頑丈そうな身体だから大丈夫か?)
さて、朝比奈について。
私は、学生時代から30代のはじめにかけて、熱烈な朝比奈信者であった。
コーラスの一員として、朝比奈の棒で、ベートーヴェン「ミサ・ソレムニス」「第九」、ブルックナー「ミサ曲ヘ短調」を歌った感動も懐かしい。
しかし、自分がプロの合唱指揮者となり、勉強を進めるうちに、朝比奈の音楽に疑問を持つようになった。
その棒も音楽的とは言い難く、むしろ演奏の邪魔をしているようでもあり、
各楽器間のバランスに配慮せず「フォルテはフォルテで」という信条も「音楽づくり」を放棄したような無手勝流。
フォルテにも様々な段階、種類、ニュアンスがあって然るべきだと思うし、
何といってもピアニシモの欠如は演奏の可能性を甚だ狭めている。
シンフォニーのスケルツォのリズムだって重たすぎて、舞曲の原型を留めていない・・・。
ブルックナーが良かったのは、ブルックナーの書法がオルガン的だったため、たまたまピタリと嵌ったのであり、
モーツァルトがよくなかったのは、その裏返しである。
というようなことは、以前もどこかに書いて、宇野先生からは「あんまり悪く書くなよ」とたしなめられたほど。
しかし、それでも、朝比奈の演奏会のあとには、毎回というわけではないけれど、
様々な欠点を超越して、何というかズシリと腸に響くことがあった。
一言でいえば、人間力。ただそこに立っているだけで会場を支配する圧倒的な空気感があった。
これは上記の短所の聞こえてしまう録音では駄目で、コンサート会場限定の感動である。
私が「比較にならない」といったのは、こうしたコンサートの手応えのことであった。
あの一文で、わざわざ語ることもなかろうと、省いたことだが。
こうした考えの整理のできたのも、記事の意図を皆様に説明する機会を得たのも、
冒頭のコメントのお蔭だとすれば、コメント主には、心の片隅で感謝すべきなのかな。
面と向かって「有り難う」と言えるほど、人間は出来ていないけれど。
という記事に関して、本日、以下のコメントを頂戴した。
「音楽を聴く耳をお持ちじゃないですよね。
お気の毒としかいいようがありません。
まぁ、頑張ってください。
ご活躍をお祈り申し上げます。」
甚だ無礼なモノの言いようなので、黙って削除しても良かったのだが、
同じように思われている方もいるかも知れないので、これを与えられた良い機会として私の考えを述べておこう。
まず何といっても、ティーレマンの指揮は良くなかった。
ティーレマンのアプローチが、緩急の極端なテンポ設定など、オールドファッションだったからではない。
フルトヴェングラー流だろうが、クナッパーツブッシュ流だろうが、音楽が良ければ、どうでも良い。
指揮に限らず、すべての器楽、声楽を究めるに於いて、「脱力」は基本である。
音楽のみならず、武術、スポーツ、書道、舞踊・・・、すべての芸事はそうではないであろうか?
それを、あんなに力ずくでオーケストラをドライヴする、というのは、暴力的な快感でしかない。
「ああ。、ウィーン・フィルが悲鳴を上げながら弾いている」と私は感じた。
もっとも、それを好きだ、という人がいても、非難するつもりはないけれど、私は与しない。
しかし、あんなに力の入った棒振りでは、その衝撃から首に掛かる負担は相当だろう。
かつての岩城宏之のように、将来、故障してしまわないか心配になるほどだ。
(しかし、頑丈そうな身体だから大丈夫か?)
さて、朝比奈について。
私は、学生時代から30代のはじめにかけて、熱烈な朝比奈信者であった。
コーラスの一員として、朝比奈の棒で、ベートーヴェン「ミサ・ソレムニス」「第九」、ブルックナー「ミサ曲ヘ短調」を歌った感動も懐かしい。
しかし、自分がプロの合唱指揮者となり、勉強を進めるうちに、朝比奈の音楽に疑問を持つようになった。
その棒も音楽的とは言い難く、むしろ演奏の邪魔をしているようでもあり、
各楽器間のバランスに配慮せず「フォルテはフォルテで」という信条も「音楽づくり」を放棄したような無手勝流。
フォルテにも様々な段階、種類、ニュアンスがあって然るべきだと思うし、
何といってもピアニシモの欠如は演奏の可能性を甚だ狭めている。
シンフォニーのスケルツォのリズムだって重たすぎて、舞曲の原型を留めていない・・・。
ブルックナーが良かったのは、ブルックナーの書法がオルガン的だったため、たまたまピタリと嵌ったのであり、
モーツァルトがよくなかったのは、その裏返しである。
というようなことは、以前もどこかに書いて、宇野先生からは「あんまり悪く書くなよ」とたしなめられたほど。
しかし、それでも、朝比奈の演奏会のあとには、毎回というわけではないけれど、
様々な欠点を超越して、何というかズシリと腸に響くことがあった。
一言でいえば、人間力。ただそこに立っているだけで会場を支配する圧倒的な空気感があった。
これは上記の短所の聞こえてしまう録音では駄目で、コンサート会場限定の感動である。
私が「比較にならない」といったのは、こうしたコンサートの手応えのことであった。
あの一文で、わざわざ語ることもなかろうと、省いたことだが。
こうした考えの整理のできたのも、記事の意図を皆様に説明する機会を得たのも、
冒頭のコメントのお蔭だとすれば、コメント主には、心の片隅で感謝すべきなのかな。
面と向かって「有り難う」と言えるほど、人間は出来ていないけれど。