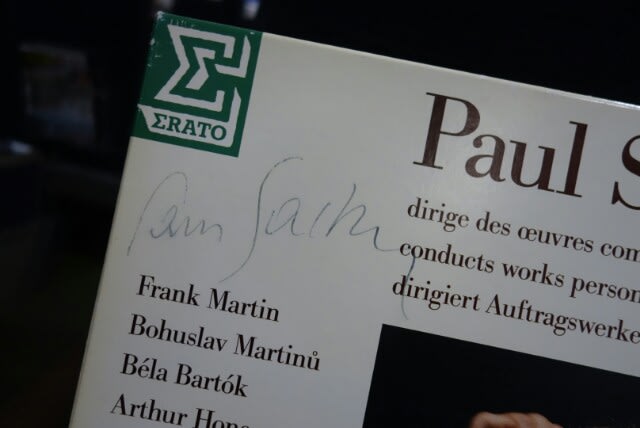「メンゲルベルクの芸術」の第一集と第二集である。テレフンケン原盤、国内盤(キングレコード)各3LP。前者が独メタル、後者が英メタル使用とのこと。
いつ頃リリースされたものか検索してみたところ、なんと1962年7月と9月の「レコード芸術」誌の推薦盤であることが判明した。つまりボクと同い年ということである。なんだか愛おしくなるな。
収録されているのは、チャイコフスキー「5番」「悲愴」、ベートーヴェン「1番」「英雄」「8番」、ブラームス「4番」、フランク「ニ短調」といういずれも定評のある名演ばかり。
これほど長年レコード蒐集をしていても、当然ながら手薄なレパートリーはあって、メンゲルベルクのテレフンケン録音は全く手付かずであった。独プレスや英プレスに越したことはないのだろうが、60年代のキングレコードのプレスは優秀であるし、比較的小さな出費でまとめて聴くには十分であろうと入手したところ。
メンゲルベルクのチャイコフスキー「悲愴」については、中学生時代、当時の国内廉価盤を聴いて、サッパリ理解できなかったのを憶えている。いくら解説の宇野功芳が褒めていても、音は貧しかったし、煩雑なテンポの変化についていけなかった。まあ、齢13や14の少年がメンゲルベルクの耽美に溺れるというのも気持ち悪い話なので、むしろ健全だったと言うべきか(笑)。
いま改めてメンゲルベルクの「悲愴」を聴くと、確かに魂の奥底を揺り動かされるものがある。精神性とか内面性という言葉からは、どちらかというと遠いところにあるチャイコフスキーの音楽から、こういう類の感動を呼び起こすメンゲルベルクは、やはり凄い人だったのだ。
ところで、この第3楽章の大胆に見得を切るようなテンポ設定、突然ローギアに落としたような効果は、朝比奈に影響を与えているような気がする。もっとも最晩年の朝比奈はインテンポに傾斜してしまったので、新日本フィル盤ではなく、新星日響とのライヴ盤をお持ちの方は是非較べてみて欲しい。