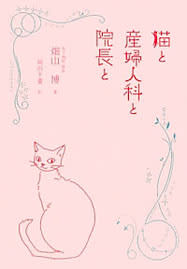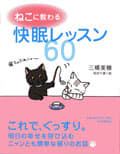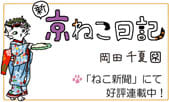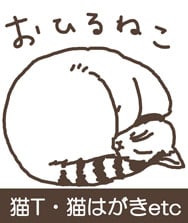ねこ絵描き岡田千夏のねこまんが、ねこイラスト、時々エッセイ
猫と千夏とエトセトラ
カレンダー
| 2007年7月 | ||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 29 | 30 | 31 | ||||||
|
||||||||
本が出ました
| イラスト(427) |
| 猫マンガ(118) |
| 猫じゃないマンガ(2) |
| 猫(512) |
| 虫(49) |
| 魚(11) |
| works(75) |
| 鳥(20) |
| その他の動物(18) |
| Weblog(389) |
| 猫が訪ねる京都(5) |
| 猫マンガ「中華街のミケ」(105) |
| GIFアニメーション(4) |
最新の投稿
最新のコメント
| 千夏/春のお茶会 |
| an/春のお茶会 |
| 千夏/節分 |
| タマちゃん/節分 |
| Chinatsu/銀閣寺~椿の回廊2024 |
| WhatsApp Plus/銀閣寺~椿の回廊2024 |
| 千夏/残暑 |
| タマちゃん/残暑 |
| 千夏/「豊穣」 |
| タマちゃん/「豊穣」 |
最新のトラックバック
ブックマーク
|
アトリエおひるねこ
岡田千夏のWEBサイト |
| それでも愛シテ |
| 手作り雑貨みみずく |
| くろうめこうめ |
| 忘れられぬテリトリー |
| 猫飯屋の女将 |
| 雲の中の猫町 |
| イカスモン |
| タマちゃんのスケッチブック |
| あなたをみつめて。。 |
| 眠っていることに、起きている。 |
| ノースグリーンの森 |
プロフィール
| goo ID | |
amoryoryo |
|
| 性別 | |
| 都道府県 | |
| 自己紹介 | |
| ねこのまんが、絵を描いています。
ねこ家族はみゆちゃん、ふくちゃん、まる、ぼん、ロナ。お仕事のご依頼はohiruneko4@gmail.comへお願いいたします。 |
|
検索
gooおすすめリンク
| URLをメールで送信する | |
| (for PC & MOBILE) | |

猫の視線、子供の視線

まず、身長が全然違うから、見る高さが違う。もうすぐ二歳になる息子は、まだ九十センチくらいの高さであるから、大人が見つけないようなものを見つけたり、大人のくるぶしに止まった蚊を指摘したりする。
だけど、大人と子供の視線の違いは、身長の差から生じる、視線の高さの必然的な違いだけではない。
一緒に教育番組を見ていたら、石畳の広い公園のようなところを背景に、なにやら黄色いオブジェのようなものが画面に大きく現れた。それは再放送で、私は横から赤いボールが飛んでくるのを知っていたから、そのあたりばかりを見ていたら、息子が「でんでん(電車)」と言った。私は「ここには電車でてこないよ」と言おうとして、背景の、はるか遠くに電車が走っていることに気がついた。一回目に見たときも、たぶん、目の前のオブジェばかりに気を取られて、背景を走る電車に気づかなかったのだろう。大人は、経験から画面のどこを見るべきかを推測できるのに対し、子供には、そんな常識は通用しないから、きっと画面のうしろの方まで見ていて、大好きな電車にすぐ気づいたのに違いない。
保坂和志の本に、「季節の記憶」という小説がある。保坂和志も猫好き作家の一人で、文庫本カバーの著者近影では、三毛猫を膝に抱いて写っているが、それは今は関係ないので置いておくとして、この「季節の記憶」は、主人公の「僕」と三歳の息子のクイちゃんと、近所に住む兄妹の物語である。ちなみに、解説によると、このクイちゃんは、著者の飼い猫がモデルになっているという。
あいにく手元に本がないので、記憶をたどっての記述になるけれど、「僕」のクイちゃんに対する教育が、ちょっとユニークなのである。その一つとして、「僕」はクイちゃんになかなか字を教えない。なぜと尋ねる兄妹に、「僕」は、隣の部屋の襖の絵は何の絵だったか覚えているかい、と反対に質問する。毎日見ているはずの襖なのに、大人は誰一人答えることができない。ただクイちゃんだけが、的確にどんな模様だったかを説明することができる。このことを「僕」はこう分析する。つまり、大人は文字という情報伝達の手段を持っているから、文字ばかりに目が行って、襖の絵などは目に入っていても見えていない。ところがまだ文字を知らないクイちゃんは、文字も絵も、同じように見ているのである。小学校にあがれば、否が応でも文字を習う。だからせめてそれまでは、文字を知らないがゆえの視点を失わせたくなくて、クイちゃんに文字を教えないのだと、「僕」は説明する。
成長の過程で、物事を情報化し、膨大な情報の中から必要なものを取捨選択することで、人間は脳の効率化を図っていく必要があるのだけれど、文字も風景の単なる構成要素としか見えない子供の心が受け止める世界は、大人とはずいぶん違って見えることだろう。
近ごろ、いつのまにかアルファベットのAを覚えて、そこらじゅうの物についているAをいちいち指摘している息子に、文字をいつ頃教えるべきだろうかと考えている。
コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )