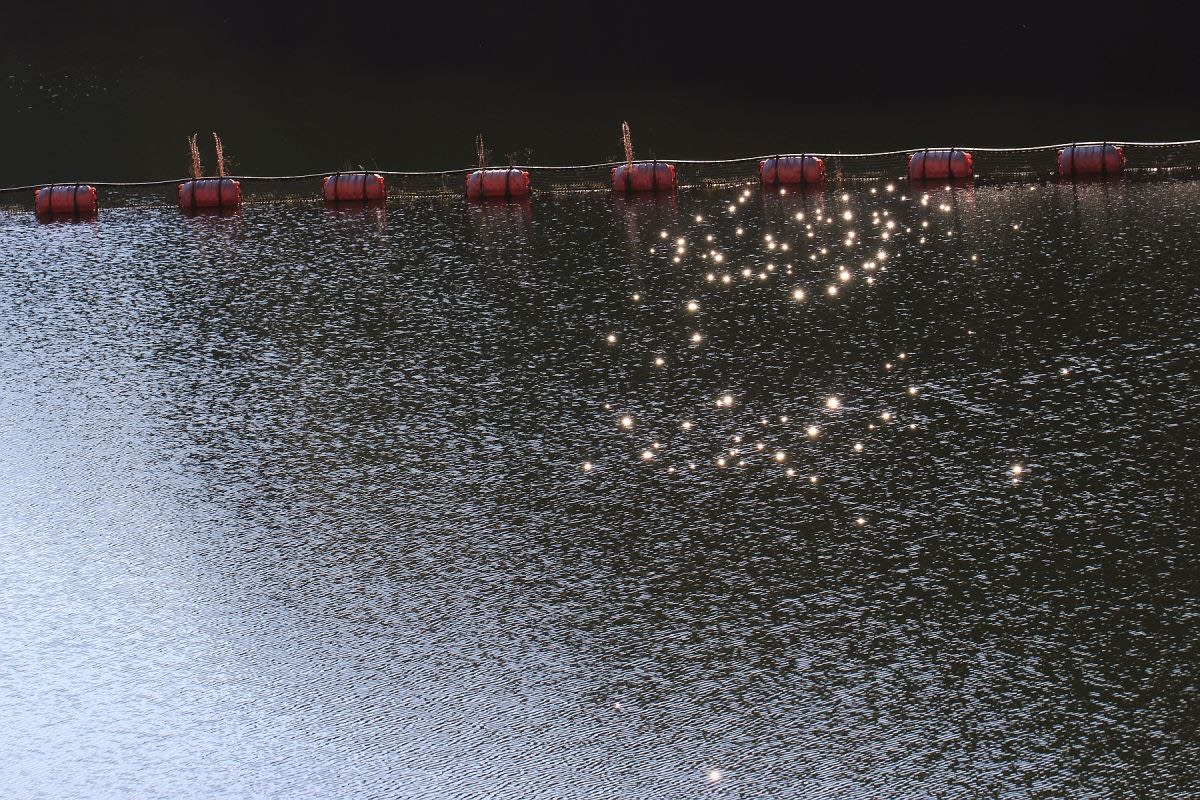赤目渓谷は両側が切り立っていて日が差し込まないので、歩き始めはとても寒かったです "(-""-)"
赤目四十八滝の『赤目』の由来は、役の小角(えんのおづぬ)が滝に向かって行を修めていると、不動明王が赤い目の牛に乗って出現したという伝説から来ています。(サイト「忍者修行の里 赤目四十八滝」)

八畳岩や千手滝のあたりまで来るとようやく日が差し込んできます。

『四十八滝』といいますが、主要な滝は「赤目五瀑」と呼ばれる不動滝、千手滝、布曳滝、荷担滝、琵琶滝の5つのようです。
観光ガイドの説明に「秋の紅葉ではイロハモミジ、カエデ、ヤマザクラなどを楽しむことができ・・・」とあります。

わざわざ「モミジ」と区別して「カエデ」を挙げています。

歩いて見ると分かるのですが「カエデ」と言っているのは このイタヤカエデのことのようです。
紅葉の葉のように切れ込みが深くなく、また黄葉がきれいです。

渓谷入り口

たぶんイロハモミジ

名前が判りません (ToT)

上と同じか? やはり分かりません((´;ω;`)

つる性植物の黄葉がきれいです

トリミングするとこんな粗い鋸歯の葉です。
Google Lensに尋ねてもラチあかないので
このきなんの木掲示板にお伺いしてみました。
「アジサイ科のツルアジサイかイワガラミを思いました。
イワガラミかなぁ・・。」
とのご回答をいただき、検索してみたところ
「丸く大きな鋸歯のイワガラミ、細かいギザギザの鋸歯のツルアジサイ」
との見分け方がありましたので、大きな鋸歯の「イワガラミ」としました\(^o^)/

ふたたびウチワカエデ
歩いているとき見慣れない岩肌だなと思いましたが、赤目渓谷の地質は「溶結凝灰岩(welded tuff)」なんですね。
溶結凝灰岩は火山の火口から噴出した火山ガラスや細かい岩片の入り混じった高温の火砕物質が、高温と自重のため、水飴のようになって流動したあと冷えて固まってできた岩石です。
ということは火山があってそれが噴火してできたわけで、何でも1,450万年前ころ、近畿地方南部を覆いつくすようなとてつもない噴火があったそうな。

溶結凝灰岩の地質とウチワカエデの植生とは関係あるのかしらん?(^^♪

渓谷入り口の山裾に咲いていました。アキチョウジ?
「「滝川」は,水平距離約3300mの間に,約200mもの高度を下げる,という激しい「下刻侵食」を行っています。
このため,滝の上流部では50m程しか無い尾根までの比高が,滝の下流部では200mを超す程になっています。」(日本の地形千景プラス「三重県:溶結凝灰岩に懸かる赤目四十八滝」)
それで渓谷の登り口では陽も差し込まなかったわけですね (^^ゞ


とある土産物屋の立て看板の屋根に生えていた菌類です。
Google Lensで検索したら、一発回答で「コアカミゴケ」と出て来ました\(^o^)/
あるブログ記事に
「コアカミゴケは、ハナゴケ科ハナゴケ属で地衣植物の一種です。」
とありましたが、最近は、菌類は 植物でも動物でもない第3の生物と考えられているんですよね。 きのこは、菌類の一種の「カビ」の仲間だ!なんて (´・ω・)
別の検索記事にいわく
「地衣類の中でもはじめの方で気が付く
盃状のの先端部に赤色の
子器をつける。子器であって花ではないのである。」
(「子器」とは? ・・・って、検索しだすとキリがありません (笑))
.