木の実といっても、種子の落ちたものばかりですが…
サルスベリ

正確には 「シマ」サルスベリです。

シマサルスベリは「中国中部、台湾及び奄美諸島などの亜熱帯に分布するサルスベリの近縁種。」(庭木図鑑 植木ペディア > シマサルスベリ)

サルスベリの学名は Lagerstroemia indica (インドの)
シマサルスベリは Lagerstroemia subcostata (やや主脈ある)

「開花時期はサルスベリと同様の6~8月頃だが「百日も咲き続ける」とされるサルスベリより、花期は短い。また、花の色は白のみで、小枝と花序に毛があるのが特徴。」(同上)

「サルスベリよりも背が高くなる木であり、公園や広い庭、街路などに植えて壮大な樹形を鑑賞するのが基本。」(同上)
@安城デンパーク・花木園
以下、すべて 愛知県緑化センターにて
カツラ


コゲラ

キツツキの仲間です。
造園実習園のいちばん奥のピンオークの木で何やら忙しそうにつついていました。
ドウダンツツジ




上の画像をグレイスケールで。
トサミズキ



メタセコイア


モズ
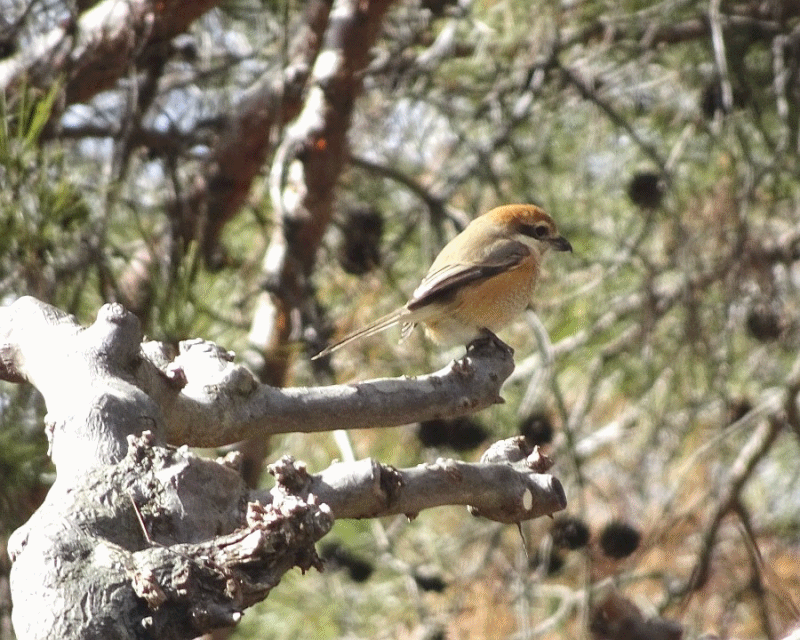
モミジバフウとフウ




ヤマノイモ

ハゼの実を食べるヒヨドリ ツグミ

ハゼの実は美味しいらしく 鳥さんたちに人気があります。

枝かぶり m(_ _)m
サルスベリ

正確には 「シマ」サルスベリです。

シマサルスベリは「中国中部、台湾及び奄美諸島などの亜熱帯に分布するサルスベリの近縁種。」(庭木図鑑 植木ペディア > シマサルスベリ)

サルスベリの学名は Lagerstroemia indica (インドの)
シマサルスベリは Lagerstroemia subcostata (やや主脈ある)

「開花時期はサルスベリと同様の6~8月頃だが「百日も咲き続ける」とされるサルスベリより、花期は短い。また、花の色は白のみで、小枝と花序に毛があるのが特徴。」(同上)

「サルスベリよりも背が高くなる木であり、公園や広い庭、街路などに植えて壮大な樹形を鑑賞するのが基本。」(同上)
@安城デンパーク・花木園
以下、すべて 愛知県緑化センターにて
カツラ


コゲラ

キツツキの仲間です。
造園実習園のいちばん奥のピンオークの木で何やら忙しそうにつついていました。
ドウダンツツジ




上の画像をグレイスケールで。
トサミズキ



メタセコイア


モズ
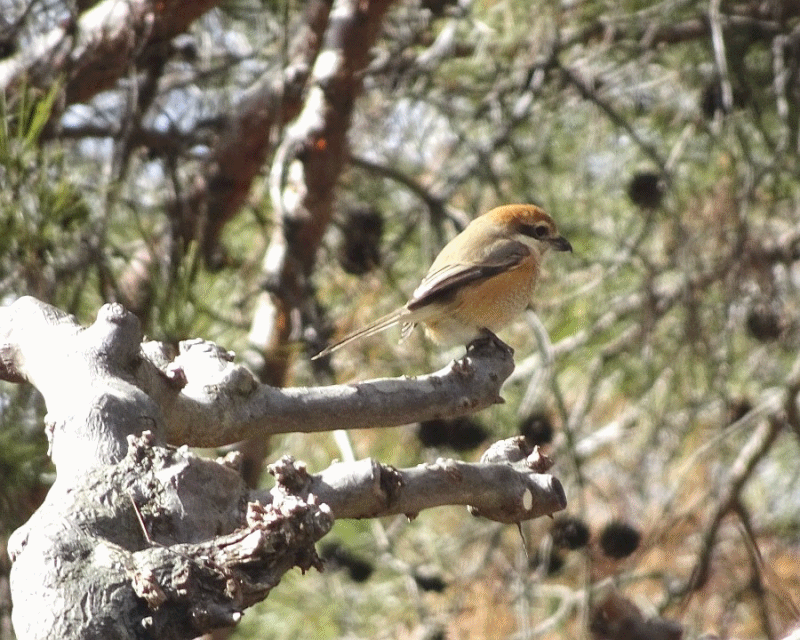
モミジバフウとフウ




ヤマノイモ

ハゼの実を食べる

ハゼの実は美味しいらしく 鳥さんたちに人気があります。

枝かぶり m(_ _)m




















































































