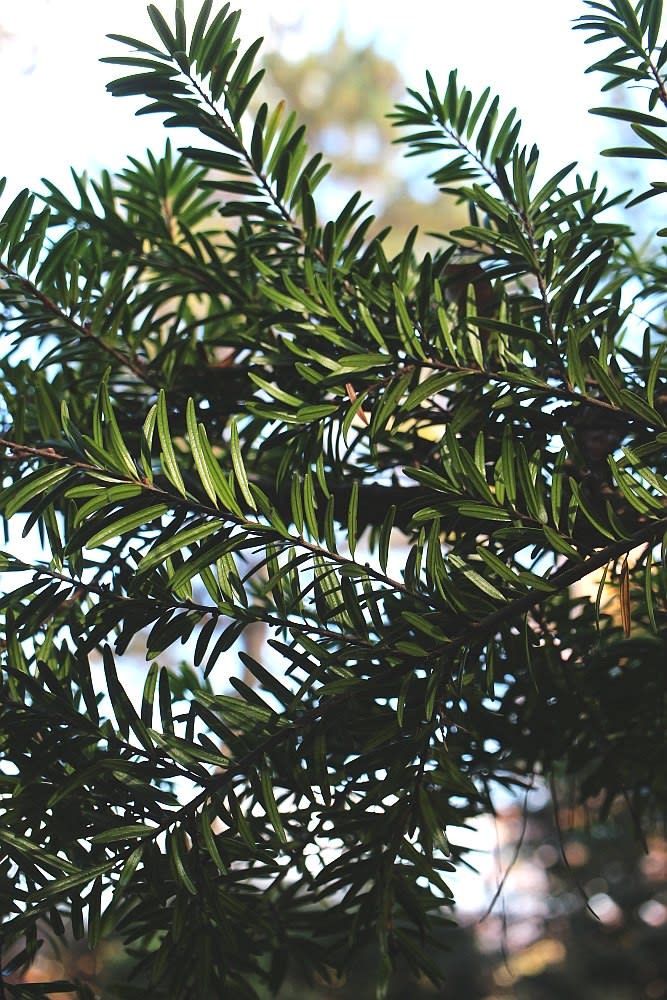今年もあと一時間となりました。
この一年、(コロナウィルスとともに)花のシベや花粉を観察してこられたのも皆さまの応援のおかげです。
ありがとうございました!
この一年を40くらいの画像で振り返ってみます。
1月

ロウバイ
2年前、落語会に行ってかかってしまったインフルエンザ。それからは 予防接種もして用心してたのに、こんどは新型コロナという更なる脅威が全世界を襲いだしました。
2月

スイセン
2月は ある献体の会の新年初顔合わせを西浦温泉で行うはずでしたが、新型コロナが 「密」状態で感染することが認知されだし取りやめとなりました。行く予定のホテルのすぐよこのホテルが 外国人利用者を当て込んでいたため、あえなく倒産しました。新型コロナによる日本初の倒産でした。
3月

クロヤナギ

ハナニラ

スギナ

アオキ

ベニバナスモモ(デンパーク)
3月に入り、年度替わりで各町内の組織は 役員交代の会や 総会を行いますが、軒並み取りやめ。
碧南市の中電のタントピアは3月に入ってすぐ、デンパークも このあと閉鎖します。施設ではもう行くところが無くて困りました。
このころ感染率を整理したことがありますが、20代の女性と50代の男性の感染率が一番高かったころでした。
4月

シジミバナ

アケビ

ナシ
人と会わなければいいのだからということで、このころは もっぱら自転車で近くを回りました。
第1波が下火になってきて、もしかしたら、これで終息するのではと、今から思えば、甘い期待をしていたものでした。
5月

バイカウツギ

トチノキ

エニシダ

ゲンペイシモツケ

セイヨウシャクナゲ

レースフラーワー
日本人の感染率は 欧米に比べて著しく低い。それはなぜか? 「ファクターXを探せ!」と問題提起されました。ところが 欧米に比べ 感染率が低いのは 日本だけでなく 韓国、中国、ベトナム、タイ、ミャンマー、マダガスカル、アフリカ大陸のある地域が 欧米に比べれば 著しく低かったのです。私は 感染率が低い地域が コメ類を主食にしている地域とほぼ重なることを発見しました。コメ(またはソルガム類)を永い間 食べていることによって 新型コロナに強い体質が形成されてきたのではないかと。
6月

ジャカランダ(西尾市憩の農園)

ネムノキ
7月

トウネズミモチ

ヤブガラシ

トウゴマ

ハツユキソウ

カノコユリ(於大公園)
8月

ハマゴウ(布土海岸)

トレニア
9月

木立ベゴニア

ヒャクニチソウ

ウィンターコスモス

ルコウソウ
ルコウソウの花粉のマクロ写真を撮りながら、こんなことを 広報誌に載せました。
ルコウソウの花粉の大きさは110μm マイクロ メートル ありますが、
ウィルスのほうは 120nm ナノメートル と花粉の 1000 分の 1ほどしかありません。
PM2.5( 2.5 μm 以下 、細菌 1 μm前後 、 タバコの 煙 約 0.5 μm は光学顕微鏡で見ることができますが、ウィルスの 姿は電子顕微鏡でないと見ることができません。

キキョウ
10月

アキノノゲシ

キバナコスモス

イタドリ

ソバ(10-11)
ソバは同じ畑で連作すると段々収量が落ちます。肥料が少ないのかとか思いましたが、連作障害のためと分かりました。
ソバはアレロパシー作用といって 他の生物の成長を阻害する成分を出すのですが、実は その成分をソバ自身が取り込んで自家中毒に陥ってしまうらしいのです。

ノボタン

コケ
10月末、高山と新穂高に車で行ってきました。紅葉が盛りで 山は新雪をかぶり絶好の行楽日和でした。
11月

ヒロハフウリンホオズキ

カイノキ

我が家にコミカンソウがやってきました(^^)/
毎年撮りに行ってるポイントが草刈り機できれいさっぱり刈り取られてしまったので、近くのお屋敷の道ばたの生えていたのを自宅に連れて帰りました (^^♪
12月

ノムラモミジ
12月初め、4月に99歳で亡くなった義母の納骨に東本願寺まで行きました。このころ カエデやモミジの種類を 翼果のかたちから判別する方法を知り、京都は 祇王寺と京都府立植物園でたくさんのモミジでそれを実地検証してみました。

今年も 一番多く撮ったのは キク科でしょうか。
キク科の頭花は たくさんの小花から構成されています。小花には、筒状花と舌状花があり、いろんなキク科の花で、それらがどんな格好をしているかを調べるのは 楽しいです (^^♪
最後にもういちど、今年はホントにお世話になりました。
どうかよいお年をお迎えください。
次の年こそ 第3次世界大戦が終息することを願って、おやすみなさい!
この一年、(コロナウィルスとともに)花のシベや花粉を観察してこられたのも皆さまの応援のおかげです。
ありがとうございました!
この一年を40くらいの画像で振り返ってみます。
1月

ロウバイ
2年前、落語会に行ってかかってしまったインフルエンザ。それからは 予防接種もして用心してたのに、こんどは新型コロナという更なる脅威が全世界を襲いだしました。
2月

スイセン
2月は ある献体の会の新年初顔合わせを西浦温泉で行うはずでしたが、新型コロナが 「密」状態で感染することが認知されだし取りやめとなりました。行く予定のホテルのすぐよこのホテルが 外国人利用者を当て込んでいたため、あえなく倒産しました。新型コロナによる日本初の倒産でした。
3月

クロヤナギ

ハナニラ

スギナ

アオキ

ベニバ
3月に入り、年度替わりで各町内の組織は 役員交代の会や 総会を行いますが、軒並み取りやめ。
碧南市の中電のタントピアは3月に入ってすぐ、デンパークも このあと閉鎖します。施設ではもう行くところが無くて困りました。
このころ感染率を整理したことがありますが、20代の女性と50代の男性の感染率が一番高かったころでした。
4月

シジミバナ

アケビ

ナシ
人と会わなければいいのだからということで、このころは もっぱら自転車で近くを回りました。
第1波が下火になってきて、もしかしたら、これで終息するのではと、今から思えば、甘い期待をしていたものでした。
5月

バイカウツギ

トチノキ

エニシダ

ゲンペイシモツケ

セイヨウシャクナゲ

レースフラーワー
日本人の感染率は 欧米に比べて著しく低い。それはなぜか? 「ファクターXを探せ!」と問題提起されました。ところが 欧米に比べ 感染率が低いのは 日本だけでなく 韓国、中国、ベトナム、タイ、ミャンマー、マダガスカル、アフリカ大陸のある地域が 欧米に比べれば 著しく低かったのです。私は 感染率が低い地域が コメ類を主食にしている地域とほぼ重なることを発見しました。コメ(またはソルガム類)を永い間 食べていることによって 新型コロナに強い体質が形成されてきたのではないかと。
6月

ジャカランダ(西尾市憩の農園)

ネムノキ
7月

トウネズミモチ

ヤブガラシ

トウゴマ

ハツユキソウ

カノコユリ(於大公園)
8月

ハマゴウ(布土海岸)

トレニア
9月

木立ベゴニア

ヒャクニチソウ

ウィンターコスモス

ルコウソウ
ルコウソウの花粉のマクロ写真を撮りながら、こんなことを 広報誌に載せました。
ルコウソウの花粉の大きさは110μm マイクロ メートル ありますが、
ウィルスのほうは 120nm ナノメートル と花粉の 1000 分の 1ほどしかありません。
PM2.5( 2.5 μm 以下 、細菌 1 μm前後 、 タバコの 煙 約 0.5 μm は光学顕微鏡で見ることができますが、ウィルスの 姿は電子顕微鏡でないと見ることができません。

キキョウ
10月

アキノノゲシ

キバナコスモス

イタドリ

ソバ(10-11)
ソバは同じ畑で連作すると段々収量が落ちます。肥料が少ないのかとか思いましたが、連作障害のためと分かりました。
ソバはアレロパシー作用といって 他の生物の成長を阻害する成分を出すのですが、実は その成分をソバ自身が取り込んで自家中毒に陥ってしまうらしいのです。

ノボタン

コケ
10月末、高山と新穂高に車で行ってきました。紅葉が盛りで 山は新雪をかぶり絶好の行楽日和でした。
11月

ヒロハフウリンホオズキ

カイノキ

我が家にコミカンソウがやってきました(^^)/
毎年撮りに行ってるポイントが草刈り機できれいさっぱり刈り取られてしまったので、近くのお屋敷の道ばたの生えていたのを自宅に連れて帰りました (^^♪
12月

ノムラモミジ
12月初め、4月に99歳で亡くなった義母の納骨に東本願寺まで行きました。このころ カエデやモミジの種類を 翼果のかたちから判別する方法を知り、京都は 祇王寺と京都府立植物園でたくさんのモミジでそれを実地検証してみました。

今年も 一番多く撮ったのは キク科でしょうか。
キク科の頭花は たくさんの小花から構成されています。小花には、筒状花と舌状花があり、いろんなキク科の花で、それらがどんな格好をしているかを調べるのは 楽しいです (^^♪
最後にもういちど、今年はホントにお世話になりました。
どうかよいお年をお迎えください。
次の年こそ 第3次世界大戦が終息することを願って、おやすみなさい!













 と舌状花
と舌状花 があるのですが、ノボロギクの頭花は 筒状花ばかりで(たまに舌状花混りがあるといいますが)そういう点では キク亜科ではなく、タンポポ亜科のほうに分類されると思っていたのですが、wiki には キク亜科 と書いてあります(´v_v`)
があるのですが、ノボロギクの頭花は 筒状花ばかりで(たまに舌状花混りがあるといいますが)そういう点では キク亜科ではなく、タンポポ亜科のほうに分類されると思っていたのですが、wiki には キク亜科 と書いてあります(´v_v`)