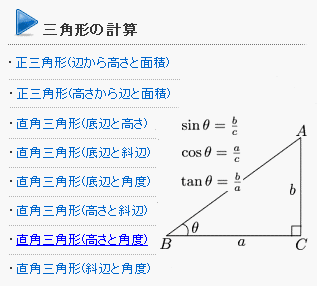「計算サイト」に「つるかめ算(つるとかめ)」というページがあります。
かっこ書きの説明をわざわざ名前につけて載せているのは、名前だけでは何のことなのかわからない人が多いと見てのことでしょうか。

しかし、折角(つるとかめ)と書かれていても、寿命の計算なのかと思ってしまう人もいるでしょう。
つるとかめの頭の合計と、足の合計から、つるとかめがそれぞれ何匹かをはじき出すという計算の必要に、実生活で出逢うことはごく珍しいことと言えます。
これは、算術、算数、初等数学を学ぶための題材として誕生したもののような気がします。
そんな計算など使ったことがないと、茶飲み話のようなことを、講演や公開座談にとりいれるおかたもいらっしゃいますが、それは、話を聴く人の肩の力をほぐそうというつもりなのでしょう。
使ったことがないとは言っても、頭の働きのどこかでほかの形で効き目が出ているのに気付かないだけかもしれません。
人間に限らず、生物はみな、すぐ役に立つことなら、教えられなくても自分で会得します。
使わないから教えない、そんな短絡的な考えを、大真面目に教育改革と思い込む人が出てくるほど、人間の頭は弱ってきているのです。
つるかめ、つるかめ。
「計算サイト」に「フィボナッチ数列」というページがあります。
聞きなれない名前ですが、13世紀初頭に「算盤の書」で、アラビア数学を紹介した、イタリアの数学者レオナルド・フィボナッチの名前がつけられた数列です。
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ・・・
最初は 0 、次は 1 、その次からは前の二つの数を足していくとこの数列になります。

自然界には、花びらの数、花や実に現れる螺旋の数など、この数列がいろいろなところに見られます。
数列の名前になっていても、この数列はフィボナッチさんが考えたものではありません。
「算盤の書」の出版を通じて、こういうものがあると紹介しただけです。
アラビア数学も、父親と一緒にアラブ人から学んだものです。
そのころは、いいや俺が先だと言い出す、グズの癖に図々しい人がいなかったのでしょうか。
「計算サイト」の「約数・倍数の計算」に「公約数」というページがあります。

公約数は、端数のないいくつかの数があっったとき、そのどちらの約数にもなれる整数のことですが、選挙のときに並べた公約の数と間違いそうです。
公である約数と、公約の数。
公約数という三文字熟語も、区切り方で意味がずいぶん違ってきます。
「公」という文字の意味も、共通のもの、共有のものであるということから、個のものでない、どこかに預けてあって適当に扱ってよいものという、いいかげんな色合いが強くなってきています。
公約という言葉も、誰かが、あるいはどこかの党が約束したことなので、その人、あるいはその党がそのことを実現すればよいものだと、思っている人が多いようです。
公約が、いったん認められれば、共通の約束ごとになるので、そうなったからには、それを実現させることに全体の力がそそがれなければ民主主義とは呼べないでしょう。
個の都合次第、気分次第で、それを忘れてしまう人、そう思いたくない人が多いようです。
公約を実現しようという働きに、反対を認めないのは民主主義ではないなどと珍妙な理屈をこねながら騒ぎまくる、おまけのついたおバカさんたちもいます。
記録の上ではこれまでになかった台風一過の豪雨も、公約数の数列でも見つめながら、公約ということをよく考えてごらんという、天の啓示かもしれません。
「計算サイト」に「体積の計算」というページがあります。
⇒ http://www.calc-site.com/


どういうわけか、ここには角ばったものの体積計算しか載っていません。
円いのは面倒なのでしょうか。
切断された円錐形、どんぶり形などの体積計算が、いちばん実用価値が高そうなのですが。
「計算サイト」に「弓形の面積」というページがあります。
⇒ http://www.calc-site.com/areas/segment

日常生活にはあまりかかわりがありませんが、まるく出ているところをそぎ落とすと、面積はどうなるか、では体積は、重さは、となってくれば、体重が気になるかたに、なにかのヒントが生まれるかもしれません。
「計算サイト」に「宝くじの確率」というページがあります。
⇒ http://www.calc-site.com/probabilities/lottery

宝くじに当たる確率がどれほどのものか、教えてくれます。
これくらいの望みは持てるという見方も、これなら当たらなかったのも仕方がないという見方もできます。
どちらにせよ、買わなければ当選率はゼロです。
「計算サイト」の「乱数の計算」に「パスワード生成」というページがあります。
⇒ http://www.calc-site.com/randoms/password_generator
考えてつくったパスワードはすぐ見破られます。
何かしら意味を持っているからです。
意味のないパスワードは考えずにつくれば、いくつでもすぐできあがります。

そのかわり、もし忘れたら、思いだすことはできません。
「計算サイト」の「面積の計算」に、で昨日失敗したので再挑戦です。
⇒ http://www.calc-site.com/maps/area

最初のマーカーの位置を変えてみたら、どうやらまとまりました。
でこぼこの激しい図形の場合は、ちょっとした工夫が必要です。
どういうところから始めればよいのか、それは、やってごらんなさいとしか返事のしようがありません。
始点探査法は、「計算サイト」の埒外ですから。
「計算サイト」に「面積の計算」というページがあります。
⇒ http://www.calc-site.com/maps/area
地図の上に、3点以上マーカーを、クリックしてつけていくと、その範囲の面積が「m2」、「km2」、「坪」で表示されます。

試みに、歯舞諸島の色丹島の次に大きな志発島がどのくらいの広さかと、順にマークをつけていったら、おやおや、着色された領域には、あとからマークをつけられません。
さて、どうしたらよいのでしょう。
「計算サイト」の「長さの換算」は便利です。
⇒ http://www.calc-site.com/units/length
元の長さと単位を書き込んで [長さの換算] ボタンを押すと、28種類の換算値がパッと出てきます。

この中に、鯨尺(クジラジャク)という単位があります。
1m = 2.64 鯨尺というこのものさしは、大まかな寸法を決めるときに、まことに都合よくできています。
ミリでは細か過ぎ、インチでは10進でないから扱いにくい、そんなとき鯨尺は重宝です。
怪しくなった視力でも、パッと見て決められます。
紙、布、板に切断線を入れるときに、目に力を入れなくてもはっきり見えます。
なぜ鯨と呼ぶのかなどはどうでもよく、とにかく人間の目に入りやすい、わかりやすい目盛りです。
「計算サイト」の「文字変換」の部に「文字を文字実体参照に変換」というページがあります。
⇒ http://www.calc-site.com/letters/html_entity_encode
文字実体参照とは、テキストに使う記号を、HTML 用の文字にするための特殊な単語です。
⇒ http://pst.co.jp/powersoft/html/index.php?f=3401
使いみちの多いのは次の文字です。
![]()
「"」 「&」 「<」 「>」 「 」
試しに記号を混ぜた文字列を変換させてみました。

HTMLで記述するとき、記号を思い出しながら、ときには間違いながらパタパタ打ち込むより、これはずっと便利です。
尻尾の「;」を忘れないように。