



普通の人は自分の栄光をなかなか忘れられないものだ。職場を退職しても、まだ上司だった気分がなかなか抜けなかったりする。武士の娘だった人は、身分という誇りをいつまでも支えにし、私だってテニスで不利に追い込まれたりすると、得意の強烈サービス(それは過去のものになったはずなのに)をふるって巻き返そうとする。

こんな私なのにもし、神さまが私を通して大いなる奇跡や癒やしを現されたらどうだろうか? 感激し、まるで自分がワザを起こしたような、そんな有頂天な喜びにしたらないであろうか? もしそうなってしまったら、神の栄光を奪う大罪を犯し、サタンの後を追うことになる。恐ろしいことであるが、人とは弱いものである。賜物を熱心に祈り求めている人の中に、そんな恐れが自分には全く無い、と断定出来る人が、果たして何人いるであろうか?

しかし聖書は興味深いことを書いているし、私は心からアーメンと言う。下記の聖書である。これはパウロに何か重大なとげ(おそらくてんかんとか眼病など、人をつまずかせるような疾病)があって、これを癒やしてくださるよう神に三度祈り求めた時の神の答えである。(パウロ自身は数えきれない人々を癒やし、奇跡を起こして来たにもかかわらず)
しかし主は、「わたしの恵みはあなたこれに十分である。わたしの力は弱さのうちに完全に現れるからである」と言われました。ですから私は、キリストの力が私をおおうために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。(コリント人への手紙 第二12章9節 ©2017)

私はこの偉大な器が、こと本人に限っては癒やされないこと、その弱さを負わされ続けることに、人間の弱さを知り抜いた神の「守り」を見て取る。パウロと言えども人間であって、高慢にならぬよう、一本の杭を、この場合はトゲと表現されているが、与えられている。実は私もトゲが与えられている。これは私を高慢にさせないための、神のムチだと聞かされている。
パウロはこの答えに非常に納得している。完全無欠になるなら、高慢という大きな落とし穴にハマりかねない。これはそれを心配しての神の愛だったのだ。私も神に祈っている。存分にトゲで私を打ち叩いてください、ダビデのように悔い改めさせてください、と。神の栄光を、0.001パーセントでも奪いませんように!
ケパ







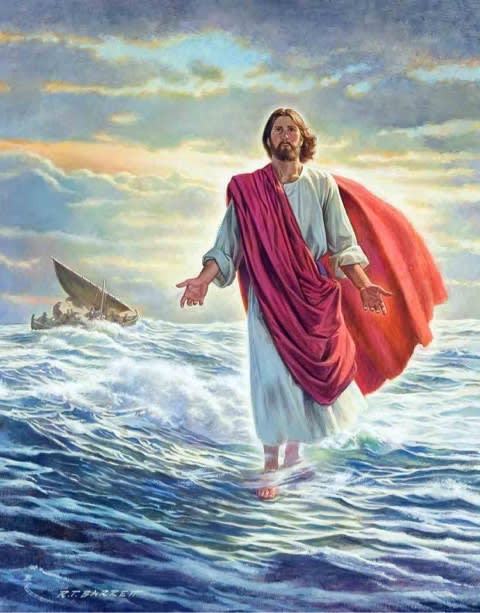




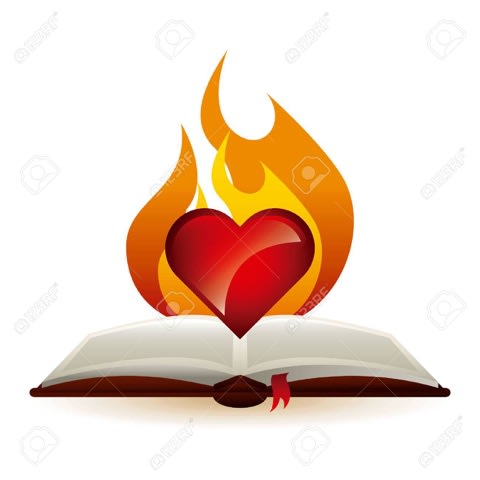
今週の「クリスチャンのキーポイント」1分間動画は「異端」だった。下の青い文字でリンヌされています。

http://movie.antioch.jp/keypoint/%E7%95%B0%E7%AB%AF/
先週も触れたが、ここでもう一度整理しておきたいと思う。人間には心(霊)というものがある。古代から多くの人は肉体は死して滅んでも、霊・たましいは死なない、という霊魂不滅を信じてきた。イデオロギーと宗教の違いは、この霊魂不滅をテーマにしているかどうかである。

霊・たましいをテーマにしている宗教は、その不滅の霊の行き先(来世)が天国(極楽・浄土)と地獄の二箇所あるとほぼ同じことを言っている。この天国と地獄観が各宗教によって大きく異なるのが一つ。そしてどうやって天国へ行かの方法も、各宗教にあい伴ってそれぞれである。日本ではマイナーで除外しなければならないが、グローバルに全世界に展開しており、世界最大の宗教にして、すべての先進国はキリスト教国であることは紛れもない事実である。だからたとえキリスト教徒でないにしても、少なくとも宗教を知り、少しでも関わろうとする人には、キリスト教とはどういうものかを素養として知っておかれることが良いのではないかと思う。
グローバルで世界の先進国の・・・・と言えば、「キリスト教は誰でも分かる、すごい知的で合理的なんだろうな」と思われるだろう。確かに「心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人たちのものだからです」(マタイ伝5:3)などを聞けば、そう思われることだろう。唯一の聖典である聖書は、驚くほど多数の言語に、しかも現代語に訳されており、だれでもいつでも、平易に読むことができ、時に無償で配られてもいる。
しかし実はキリスト教の真実とは、頭や知性ではとうてい理解不可能な、極めて霊的な宗教である。つまり信じてみなければ、本当のことはわからない宗教なのである。これを聞けば「えーっ」と思われるだろうが、安心してください。棄教したら殺すという、世界第二位の宗教と違って、「違う」と思えばいつでも簡単に止められて何の問題も無いのが、正統的な(異端から見れば形骸化していると言う)キリスト教です。真の宗教というものは何よりも自由であり、束縛したり、圧迫をかけてマインドコントロールするはずがないのです。

もう少し一つだけ、異端が出やすい中心的なテーマに説明をしましょう。キリスト教は「三位一体」の神です。ここが一番はじめからなかなか信じられなくて、二千年前の当初から多くの異端が生じました。「使徒信条」というキリスト教ではスタンダードな信仰告白があります。その中に、「乙女マリヤより生まれ」「死してよみがえり、天に昇り」というくだりがあります。処女から子どもが生まれる・・・・なんて言うことがあるでしょうか。それも人ならぬ「神の子」が誕生したと言うのです。つまり母マリヤのDNAも一切ないのです。しかしクリスチャンたろうとするなら、この処女降誕を信じなければならないのです。その他、嵐を静め、湖を歩いて渡り、あらゆる病を瞬時に癒やし・・・・極めつきは二匹の魚と五つのパンで五千人(成人男性の数だけで・・・・つまりこの数倍の人が居た)に給食したということを。
だからキリスト教を常識的で人間的な判断をしようとするなら、最もつまずくところが処女から生まれるはずがないイエスが、神であると同時に完全な人であったという所です。しかしイエス・キリストが単なる人であって、神ご自身でないならば、人間の罪を赦す資格も権利もないことになる。実際聖書には三位一体という言葉だけがないものの、あらゆる箇所で「父なる神、子なる神イエス・キリストキリスト、聖霊なる神は唯一で神である」という内容、つまり三位一体を裏付けている。しかし聖書に従うより、人間的なこれまでの既成観念や常識で判断してしまい、イエスが「神ではなく、人だ」とした時、恐ろしい異端が始まります。
なぜなら、神でなければ人間の罪を赦すことはできないからです。罪を判定し、裁くのは神です。本来、人は罪多く、赦されなければ必ず地獄に行くしかない存在です。が、ここで身代わり(代わりに罪を引き受ける=贖罪)になって、人間の罪を赦そうという神の愛が明らかにされます。イエス・キリストです。断罪する立場にありながら、神ご自身が引き受けて罰されようというのが十字架なのです。宇宙と全世界を創造し、人さえも造られた神でなければ役不足です。人間であれば笑い話でしょう。
つまり三位一体の神を信じなければ、「十字架」による赦しがないので、天国に行くために、<行い>をして自分の力で得ようとするしかありません。聖書で激しく「律法」として責められているものです。夜も昼も教団組織のいう、伝道や集会参加に天国行きを賭けての果てしないレースへと駆り立てられる構図になります。そこに神ならぬ「教祖」「最高権威」「本部組織」が神代行として介在し、マインドコントロールされてしまいます。ところが三位一体を信じる正当なキリスト教の信徒は、イエス・キリストと十字架を信じた時点で天国行きは確実で、心配することは決してありません。なので教会や教団があっても、基本はただそれぞれが祈り、神のみ心に従うことです。神以外の束縛はないので、神の前に自由なのです。
<キリスト者の自由>それがポイントになります。
ケパ





 この友の庭に来る本物のエゾリスにクルミをあげたところ、地中に埋めたまでは良いが、忘れてしまって春になると芽を出してビックリしたとのこと。前から話には聞いていたが、「なーるほど」と思ってしまった。(写真 エゾリスー日本の在来種では最大のもの)
この友の庭に来る本物のエゾリスにクルミをあげたところ、地中に埋めたまでは良いが、忘れてしまって春になると芽を出してビックリしたとのこと。前から話には聞いていたが、「なーるほど」と思ってしまった。(写真 エゾリスー日本の在来種では最大のもの)

