
三浦アルプスを長柄橋から馬蹄形に縦走してきた。
長柄橋 ⇒阿部倉山 ⇒二子山 ⇒乳頭山 ⇒芽塚 ⇒ソッカ山 ⇒仙元山
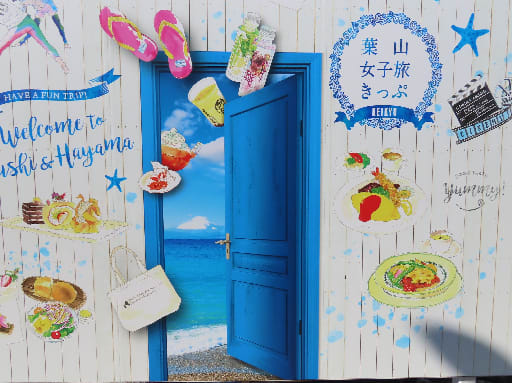
8:40 京急逗子葉山駅スタート ドアは
ドアは 開いていた
開いていた

長柄橋まで歩く、 桜山隧道通過中
桜山隧道通過中

長柄橋交差点、 左折して川久保へ
左折して川久保へ

 白梅と菜の花
白梅と菜の花

川久保交差点を 右へ、阿部倉山です
右へ、阿部倉山です

おはよう

9:10 登山口、下に庚申塔、祠内に馬頭観音牛明神が祀られている
庚申塔:中国から伝わった道教に由来する「庚申信仰」
江戸時代にその他の風習(健康長寿、豊作や家内安全なども願われ)
と結びついて広まった。『路傍の神』

 混
混 生
生 林〜杉林へ
林〜杉林へ

9:25 阿部倉山:161m なんと「
なんと「 陶器製」の表示板
陶器製」の表示板

 江の島と雲に隠れた🗻 @サクラテラス
江の島と雲に隠れた🗻 @サクラテラス
二子山へ急登の道を歩いて下二子山:206m 〜
〜

10:05 二子山:208m 『
『 一等三角点』 何故か
一等三角点』 何故か お賽銭が
お賽銭が


 横浜市内の眺望
横浜市内の眺望

オオイヌノフグリ

 東逗子駅 『桜山』馬頭観音
東逗子駅 『桜山』馬頭観音 乳頭山へ
乳頭山へ

このMapが頼り(道迷いが多い低山です)

10:40 桜山 馬頭観音
馬頭観音
右側に「牛馬安全」左に「文政三年八月=1820年」と読める
馬や牛は農作業や運送などに欠かせないものだった。
江戸中期の人達は死んだ馬の供養塔を建立、牛馬の安全と成長を祈った。

 蜘蛛の巣
蜘蛛の巣

リョウメンシダ

 田浦方面 乳頭山
田浦方面 乳頭山

 青空と
青空と スギ花粉
スギ花粉

11:15 乳頭山(矢落山):220m 通過
通過

 東京湾と
東京湾と 田浦港(横須賀市)
田浦港(横須賀市)

フキ

 アオキの葉
アオキの葉

「芽塚=小ピーク」 へ寄ります
へ寄ります

 乳頭山@芽塚
乳頭山@芽塚

芽塚:212m 植栽が伐採され「山頂標示板」も
植栽が伐採され「山頂標示板」も 見当たらず
見当たらず

大楠山

ヤブツバキのトンネルでした

11:40 ( いつもの)鉄塔下で昼
いつもの)鉄塔下で昼

 食、芽塚です
食、芽塚です

左)阿部倉山 右)二子山

ヤマザクラのトンネル、12:10 大桜通過、 ツアー休憩中
ツアー休憩中

「私製」だが信頼できる標示板

 雨でも降れば歩行困難が想定される道
雨でも降れば歩行困難が想定される道






タブノキ「木の根道」

12:55 観音塚、 撮ってもらいました
撮ってもらいました

ヤブツバキの 幼木「
幼木「 頑張れよ」@観音塚タブノキ
頑張れよ」@観音塚タブノキ

 もうすぐです
もうすぐです

13:25 ソッカ山 (戸根山) 伊豆
(戸根山) 伊豆 大島が見えます
大島が見えます

約200段、降りて登り返します

13:45 仙元山:118m 、
、 雪が舞ってます
雪が舞ってます

カワズザクラ

 雪が舞っているのわかりますか?
雪が舞っているのわかりますか?





行程:累積標高差1154m/15.6km/5.5時間
8:40 京浜急行逗子葉山駅
8:50 長柄橋左折(馬蹄形縦走スタート)
9:10 阿部倉山登山口(庚申塔・馬頭観音牛馬明神)
9:25 阿部倉山:161m
10:05 二子山:208m(一等三角点)
10:40 馬頭観音
11:15 乳頭山:220m(せまい山頂10人は居たか)
11:30 芽塚:212m(伐採が進み山頂標示板も見当たらず)
11:40 鉄塔下:昼食(10分)
12:10 大桜(©ツアー休憩中、足の踏み場もなし)
12:55 観音塚
13:25 ソッカ山(戸根山)
13:45 仙元山:雪が降り始めた
14:20 逗子葉山駅:雪は上がった













 登り納め」の
登り納め」の 金時山以来、一年ぶりになる乙女口
金時山以来、一年ぶりになる乙女口

 残雪あり、アイゼン使うほどではない)
残雪あり、アイゼン使うほどではない)
 ウツギ等の低木が
ウツギ等の低木が





 縦走路
縦走路
 共生(win win)?
共生(win win)? 奇生(parasit)?
奇生(parasit)?
 仙石原分岐)
仙石原分岐)
 左)愛鷹山塊
左)愛鷹山塊


 スカイ
スカイ ライン」が並行しています
ライン」が並行しています



 大涌谷も、
大涌谷も、

 樹
樹



 朽ちて不明、『行政の皆さん
朽ちて不明、『行政の皆さん
 ベンチ、
ベンチ、 ブナ、
ブナ、 芦ノ湖
芦ノ湖

 巻くのか?
巻くのか? 巻きました)
巻きました)
 駒ケ岳も真東に見えています
駒ケ岳も真東に見えています
 駿河湾、手前は
駿河湾、手前は 沼津アルプス
沼津アルプス



 タフな道
タフな道



 ⇒湯本駅BS ⇒小田原駅
⇒湯本駅BS ⇒小田原駅










 滑るよ
滑るよ








 天園
天園 への道を
への道を
 横浜霊園(金沢区)の奥に
横浜霊園(金沢区)の奥に 大平山(鎌倉市)を遠望する
大平山(鎌倉市)を遠望する












 宴
宴

 三角点
三角点





 開
開

 干支ですが、もう終わってるよ
干支ですが、もう終わってるよ







 曇
曇
 金次郎草刈りハイキングコース”
金次郎草刈りハイキングコース” 最乗寺へ、大雄山駅から小田原駅へ戻る
最乗寺へ、大雄山駅から小田原駅へ戻る


 緩やかに上ってます
緩やかに上ってます

 別荘地です
別荘地です






 金次郎腰掛石」
金次郎腰掛石」






 いいね?
いいね?

 オニシバリ:ジンチョウゲ科
オニシバリ:ジンチョウゲ科 坊主」とも呼ばれる
坊主」とも呼ばれる

 落葉樹に変わってきた
落葉樹に変わってきた








 パラ
パラ

 根っこに注意
根っこに注意

 が聞こえてきます
が聞こえてきます



 豆まきに参加します
豆まきに参加します







 :@三ノ塔
:@三ノ塔








 の紹介を
の紹介を 
 大山です
大山です


 下って
下って 上り返し
上り返し



 再整備されてます
再整備されてます 


















 特許”の木段
特許”の木段



















