昨日は、木青会館のきもの教室でした。
谷先生とスタッフの祐村さんがお休みでした。
2週間ほど着物を着なかったので、
今日は、と思って早々に髪をアップにして用事を片付け「さあ」と思ったら
予定外に主人が早く起きてきたりと…結局、洋服になりました。
まず皆さんが練習してきたボディを見せて頂きましたわ。
皆さんボディには時間内に上手に着付けられるようになりましたが
一番大事な留袖の襟元が少し気になったので
長襦袢に着物を羽織らせる時に長襦袢が浮かないか?をお聞きして
浮く人を対象に、はおらせ方をもう一度実践勉強してもらいました。
衿の後を引く手と羽織らせる前の手の力関係もあります。
はおらせる手に力はいりません。
留袖は重みもあるし、比翼がついているので、
この時に比翼をよれよれしない様により気を付けて乗せます。
タイムを計って相モデルで着付けてもらいました。
見ていると先ほど練習したのに、長襦袢の襟元が着物を羽織らせた途端、
乱れている人が「あれっ?」
ご本人も大丈夫と思っていたので…びっくりしたようです。
ここで大分手間取っていましたが、そのあとスピーディになり最終的には、少しオーバーしただけで終わりました。
もう一組は、相手が遅いと思った油断からか? 余裕綽々で・・・結果は時間内ギリギリでした。
長襦袢の襟元が、はだけた感じになった時の応急処置を教えたので、下の写真では分かりませんわ(#^.^#)
応急処置は、身八つ口から手を入れて、長襦袢の襟を横に引きました。




ところで、なぜ、最初に羽織らせ方を練習したのに…?あんなに長襦袢の襟が浮いたのでしょうね(-_-;)
他のスタッフさんもSさんに着物を羽織らせた時に浮いたと言われ
もう一度、わたしがお手本を示したのですが、
スタッフさんの様には、浮きませんが何時もと手ごたえが違い
少し浮いた感じがします。(-_-;)
そこで、気になっていた
最初の補正から見せて頂きました。
Sさんは、鎖骨が少し出ていたのですが、
留袖という事と肩山が凹んでいるという事から
補正は、綿花を左右2枚づつ乗せていたのでより
鎖骨の部分が高くなって浮きやすくなってしまったのです。
でも、こういう方の場合は、鎖骨の出ているところには綿花を乗せません。
出ている鎖骨を除いて綿花を入れます。
紋があるので横に入れる綿花は脇のすく近くまで入れます。
この補正で長襦袢を着付けてみると
長襦袢の襟を後ろから押しても、前の半衿は動き(浮きません)ません。
これなら重たい留袖を着せても大丈夫ですね(^_-)-☆
私は留袖を着付けてもらう時間がありませんでしたが、私にとってもいい勉強になりました。
補正が上手に入っているかを見るには、
長襦袢の襟を後ろからホンの少し押してみたら良いんだわ(#^.^#)
これで浮くようなら着物を乗せるともっと浮きますからね(^_-)-☆
本日も訪問ありがとうございます
応援クリックもよろしくお願い致します





















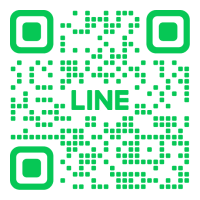














※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます