内村鑑三とその周辺の人々を無教会主義キリスト教の第一世代、塚本虎二、三谷隆正、矢内原忠雄等の諸氏を第二世代、関根正雄、高橋三郎、量義治等の諸氏を第三世代と、仮に言うことが出来るとすれば、現在は第四世代ということになるだろう。まえにこのブログで言及した松本馨さんは、そういう分類でいうならば第三世代に属する。つまり、時代で言えば、戦中戦後の試練の時を生き抜き、敗戦による日本人の価値観の転換を経験した世代である。
ところで、先月、京都の学会で無教会運動の第4世代のひとにお目にかかった。関根正雄先生の弟子であったということだったが、現在は、無教会に飽きたらぬものを感じていると言われた。そして、「無教会運動」は、すでにその歴史的使命を果たしたと言われ、私が「無教会」を過大に評価しすぎであると驚かれていた。
私の無教会に対する関心は、関根正雄先生と量義治氏によるものである。とくに量義治氏の「無教会的神学の構想」「存在のアナロギアと信仰のアナロギア」という二つの論文には大いに触発された。
量義治氏は、無教会的神学の重要性を強調して次のように言う。
この問題提起は、私自身のものでもある。「存在のアナロギア」(トマス)と「信仰のアナロギア」についての量氏の論考については、近い将来にコメントしたいが、無教会は、プロテスタント神学の伝統だけを念頭におくのではなく、「二千年のキリスト教の教会史に無教会はどのように接続するのか(高橋三郎)」という歴史意識にもとづいて、無教会の現在を神学的に思索しなければならぬだろう。
私の基本的立脚点は、「無教会こそ真のカトリック(普遍の教会)」というものである。従来の無教会にたいする既成教会の位置づけは、無教会は終末論や再臨信仰に根ざす、日本の「特殊な」プロテスタント・キリスト教の一形態であるというものであった。これに対して、私は、無教会の特殊性ではなく、その「普遍性」を強調する。そして、この最も普遍的なるものの視点から、個人の信仰の実存の問題を捉えることをキリスト教的思惟の核心にあるものと考える。すなわち、国家とか民族とか教会とか階級とかいうごとき特殊なる「種」や「類」を越える普遍の教会こそ、そなわち「無教会」こそが、「真の普遍の教会」である。それと同時に、その「普遍の教会」は、形あるすべての教会を否定することによって、真に生かすものとなるべきこと、即ち教会を恒に新しく刷新する原理とならねばならない。
無教会の「無」は、相対的な否定の立場ではなく、絶対否定の立場、有を否定する相対的無ではなく、絶対無である。「無」とは如何なる意味でも対象化し得ぬ普遍であり、かかるものの自己限定として我々の個が存在する。「絶対無」こそが、世界内存在にも、国家的存在にも解消されぬキリスト教的な個的実存、すなわち「人格(ペルソナ)」の成立する場所にほかならない。
ところで、先月、京都の学会で無教会運動の第4世代のひとにお目にかかった。関根正雄先生の弟子であったということだったが、現在は、無教会に飽きたらぬものを感じていると言われた。そして、「無教会運動」は、すでにその歴史的使命を果たしたと言われ、私が「無教会」を過大に評価しすぎであると驚かれていた。
私の無教会に対する関心は、関根正雄先生と量義治氏によるものである。とくに量義治氏の「無教会的神学の構想」「存在のアナロギアと信仰のアナロギア」という二つの論文には大いに触発された。
量義治氏は、無教会的神学の重要性を強調して次のように言う。
関根正雄先生は無教会の真理性を確信されていたがゆえに、その伝道のはじめから自己批判としての無教会批判を敢行してこられた。たとえば、無教会は『見ゆる教会』を軽視してはならない、と言われる。あるいは無教会に於ける師弟関係の問題性を指摘される。また、あるいは内村鑑三を相対化する視座の必要性を説かれる。(中略)先生はこうのべておられる。『バルトが神学なき教会は自己批判を怠る結果、晩かれ早かれ異教的となると言った言葉を無教会主義は、他山の石として深く考えなければならない』と。先生のもろもろの無教会批判のなかでの根本的批判は、無教会に於ける神学無用論に対する批判ではなかろうか量義治氏は、このように無教会主義のキリスト教に於ける神学の必要性を強調している。量義治氏が、念頭においているキリスト教神学は、ローマン・カトリックを代表するものとして、トマス・アキナスの神学大全、プロテスタントを代表するものとして、カール・バルトの教会教義学である。この二つの神学に対して、無教会主義キリスト教は、如何なるキリスト教的思惟をもって自己自身を理解し、そして自己を批判する原理となしうるか。
この問題提起は、私自身のものでもある。「存在のアナロギア」(トマス)と「信仰のアナロギア」についての量氏の論考については、近い将来にコメントしたいが、無教会は、プロテスタント神学の伝統だけを念頭におくのではなく、「二千年のキリスト教の教会史に無教会はどのように接続するのか(高橋三郎)」という歴史意識にもとづいて、無教会の現在を神学的に思索しなければならぬだろう。
私の基本的立脚点は、「無教会こそ真のカトリック(普遍の教会)」というものである。従来の無教会にたいする既成教会の位置づけは、無教会は終末論や再臨信仰に根ざす、日本の「特殊な」プロテスタント・キリスト教の一形態であるというものであった。これに対して、私は、無教会の特殊性ではなく、その「普遍性」を強調する。そして、この最も普遍的なるものの視点から、個人の信仰の実存の問題を捉えることをキリスト教的思惟の核心にあるものと考える。すなわち、国家とか民族とか教会とか階級とかいうごとき特殊なる「種」や「類」を越える普遍の教会こそ、そなわち「無教会」こそが、「真の普遍の教会」である。それと同時に、その「普遍の教会」は、形あるすべての教会を否定することによって、真に生かすものとなるべきこと、即ち教会を恒に新しく刷新する原理とならねばならない。
無教会の「無」は、相対的な否定の立場ではなく、絶対否定の立場、有を否定する相対的無ではなく、絶対無である。「無」とは如何なる意味でも対象化し得ぬ普遍であり、かかるものの自己限定として我々の個が存在する。「絶対無」こそが、世界内存在にも、国家的存在にも解消されぬキリスト教的な個的実存、すなわち「人格(ペルソナ)」の成立する場所にほかならない。











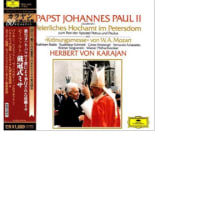

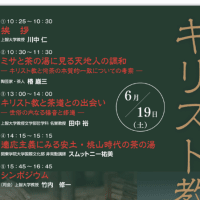










■たしかに、イエスと12使徒の伝統につながる歴史的な教会協働態と無教会の方々がどのように接続するのかを神学的に明らかにする作業が今後の課題だと思います(東京大学大学院の宮本久雄先生は『存在の季節』『他者の原トポス』などで「教会協働態」という新造語を提唱しています。イスラエルの宗教家たちが律法を複雑に規律化し容易に守れないようにすることで人々に対する救いの可能性を狭め融通のきかない自家撞着的で形式的な共同体と化したのに対して、イエスの目指した運動が常にあらゆる人々と連帯しながらダイナミックに開かれた関わりを実現したのであり、そうしたイエスの運動を「協働態」と呼ぶことで過去の旧弊に陥らない自由で寛やかな救いのダイナミズムを説明しようとしています。実は、神の創造のわざ、生成の現事実、ハヤトロギアの視点が強調されています)。
■2000年前、イエスの弟子たちは先生であるイエスに対して、「先生の名前を勝手に使って悪霊を追い出している者がいます、やめさせましょうか」というような進言をしました。つまり、弟子たちの心のなかには「自分たちこそがイエスの直弟子であり、権威がある」という自負心と「自分たちとのつながりのない人々が他の場所で善行をつづけているのを野放しにしておきたくない」という嫉妬に満ちたおせっかいとが潜在していたのかもしれません。しかし、イエスは「寛やかな心」を備えたおかたでした。イエスは弟子たちに対して「誰でも私に敵対しない者は味方である。彼らにまかせて、善行をつづけさせておきなさい」と答えを返したのです。
■イエスは、自分に敵対しない者が遠くで善きわざを行いつづけているのを容認しました。イエスと直接的に生活をともにしていなくても、イエスの伝えようとしていた「神の慈しみ深い想い」と同等の想いで生きようと志し、その想いを実行に移そうと努力している者は神の慈しみにつつまれた家族の一員です。
■ファリサイ派や律法学者たちなど宗教的な権威者たちがイエスに反対したときにも、イエスは明解な答えを返しています。「ここに転がっている石ころからアブラハムの信仰深い生き方と同様の敬虔な生き方をする新たな民をつくりだすことができる」。つまり、神の想いを真摯に受けとめようとする人がいれば、そこから敬虔な信仰共同体が始まっていくのであり、従来の宗教的権威が必ずしも真正な信仰継承者になるともかぎらない、という意味がこめられています。2000年前のイスラエルの宗教家たちは「自分たちこそが神の意志にかなう選ばれた者である」という自負心をもっており、他の人々をまるで「石ころ」(神の声をきくことができない無価値な存在のたとえ)のようにあつかいながら軽蔑していたのでした。イエスは彼らの態度にたいして痛烈な皮肉を述べたのでした。
■教会という組織に属している者は、えてして2000年前のあの弟子たちのようにふるまいがちです。自分たちを正当化し権威づけ、神の想いが広がることを邪魔しようとしてしまうこともあるからです。
■ローマ・カトリック教会は、「イエスと12弟子」をセットで理解しており、①イエスと共同生活し②イエスから遣わされて世界に向かうことをキリスト者の根本的な存在意義であると理解しています。こうした発想は福音書のなかにも出てきます。12弟子はイエスと共同生活したのちに遣わされて「使徒」となり、彼らの伝えたことが教会共同体の基準として「使徒伝承」として今日にいたるまで大切にされています。こうした視点も、イエスの言葉とわざを何とかして可視的に確実に継承していきたいという真摯な意図によって深められてきたものでありますから、認めるべき価値があります。
■結局、「自己正当化」と「可能性を狭めるおせっかい」という行動様式にさえ陥らなければ、「使徒継承の教会共同体」も「無教会の人々」もイエスの意志を受け継ぐ者として貴重な存在意義を備えることになるのでしょう。
2005年9月2日(金)
私は、キリスト教とキリスト教会と教会組織について、矛盾と人権の侵害を強く感じています一人です。
具体的な事実は、牧師に先生の敬称をつけなければならないこと!聖書には先生と呼ばれたがってはいけませんとあるのに、これを実行すればそうとうに憎まれます。しかし、先生と呼ばれたがるひとに共通するのは自己中心的な自分の暮らし向き優先主義と見受けられます!
人は年とともに収入が減ることは多くの人の場合共通すると思いますが、献金がなくなる、少なくなったとき、牧師の態度は可也強烈に信徒の人権を侵害しています。こういう状況に追い込まれる信徒さんは少なくないと思いますが、クリスチャンが1%弱しかいない日本の現状に救済の手段は無いのでしょうか? 森田裕子
>無教会主義キリスト教と関係の深いものというと、どのようなものを読めばよいのでしょうか。
関根正雄自身が、晩年に西田哲学に深い関心を寄せています。関根正雄著作集第18巻 付録(二)「現代聖書・神学の主要問題」 付録(三)「聖書學と神学をめぐって」(373-415頁)をご覧下さい。
>西田哲学というと絶対無ということが、よく言われますが、晩年の西田には絶対の他という表現もあるということ聞きました。このふたつはどのように関係しているのでしょうか。
絶対無というのは「有」に対立する「無」ではなく、有無の対立を越える「無」という意味ですが、「絶対の他」も同じように、自己に対立する他者ではなく、自他の対立を越える「他」という意味です。西田哲学については、これまでは禅宗、それも臨済禅との関わりを強調する人が多かったのですが、じつは、最晩年の彼の宗教哲学は、浄土真宗やキリスト教の絶対他力の立場と深く関連しています。
これは非常に重要な問題ですので、いつか時間のあるときに、ブログの本文であらためて取り上げたいと思っています。
自分の信仰の枝を認識するとき内村鑑三の無教会主義はキルケゴール=有神論的実存主義に由来すると「デンマルク国のはなし」に書いてあります。
実存主義哲学=有神論・・・なかなか理解は難しいですけど此処に接着しようと思い日々模索しています