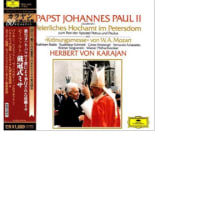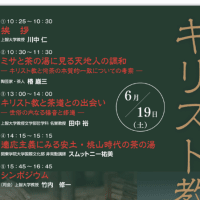夢の如き真實―五十嵐一君の思い出
田中 裕
五十嵐一君と初めて会ったのは、本郷の理学部数学科への進学が決まったあとの駒場の教養課程二年生の秋学期、英語の授業の時であったと記憶している。五〇年以上前のことというと、すべてが夢のようでもあるが、反面、昨日の出来事よりも遙かに強いリアリティをもって思い出されるような気もする。短期記憶のあやしくなった老人の繰り言と思って聴いて頂きたい。
あれは、グレハム・グリーンの短編小説を学生が順番に読むという演習であっただろうか、五十嵐君の番が来たときに、彼は、開口一番、担当の教師にむかって、「先日のシェークスピア学会ではお世話になりました」と言った。大学二年生の時にすでに日本シェークスピア協会の会員だった五十嵐君は、同じ研究者仲間としてその英語教師に挨拶したのだろう。大学院生ではなく学部生、それも理科一類の教養課程の学生が、単なる趣味でシェークスピアを読むというのではなく、学術的な場でシェークスピアについての研究活動を専門家と共にしていたというのは、にわかには信じがたいことのようにも思われようが、それが若き日の五十嵐君だったので、今回想してみるといかにも五十嵐君が言いそうな言葉であった。
当時の駒場の教養課程は、旧制一高の面影をまだ十分に残していて、およそ実用とは縁のない古典のテキストが演習で使われていた。五十嵐君と同じく理科一類から数学科へ進学した私の場合でも、一年生の時に「ハムレット」、二年生の時に「ジュリアス・シーザー」および「十二夜」を講読する英語演習をとったのを覚えている。ジョン・ギールグッドを初めとする名優達の演ずるシェークスピア劇をテープレコーダーで聴かせながら、語学演習を指導する先生達ご自身も楽しみながら授業―というより雑談―をしていた。
五十嵐君には、当時から、どこか「専門家を超えるアマチュア」という趣があった。大泉学園にあった彼の家の書斎には、古今東西の文藝や哲学の古典―それは翻訳ではなくほとんどが原書-がおいてあったにもかかわらず、彼は他人の学説を受け売りするディレッタントとはほど遠い存在だった。自由闊達なプラトン的対話術を身につけ、常に聴くものを楽しませながら古典の世界へと我々を啓発してくれたものである。
本郷の理学部数学科に進学してまもなく、大学がバリケードで封鎖され、安田講堂に立てこもった「全共闘」の諸君が機動隊に排除された「学園紛争」の時代となった。数学科でも同級生のN君が機動隊に逮捕されたので、それを気遣って拘置所まで、仲間と一緒に衣類や日用品の差し入れに行った記憶がある。拘置所から戻ったN君―サルトルを引用した安田講堂での彼のアジ演説は今でもよく覚えている―を囲んで数学科の同級生が一席設けたことがあった。その席で五十嵐君は「ソクラテスはなぜ脱獄しなかったか」という話をしたのである。「中核」や「革マル」のイデオロギー的言説とはほど遠いソクラテスの話を五十嵐君がなぜしたのか、当時の私にはよくわからなかったが、いまにして思えば、要するに、「自分の持ち場を離れず、中途半端な妥協をするな」ということが言いたかったのかもしれない。学園紛争が終焉に向かい始めた時に現れてきた様々な妥協的・偽善的な動きに反発していた五十嵐君は、「衣の下に鎧を隠す」ような「民青」のやり方を嫌い、表裏のない「全共闘」のほうに共感していた。ノンポリであるが故に政治的な過激派以上にラジカル(根源的)たらんとするのが五十嵐君の立ち位置だったのだろう。
学園紛争の時代の五十嵐君の話は、シェークスピアよりもソクラテス、プラトン、アリストテレスのギリシャ哲学であり、ホメ-ロスの叙事詩の世界が中心となっていた。彼は、翻訳や近代語訳を介さずに、所々ギリシャ語原文を引用しつつ、自分自身の言葉で独特のホメ-ロス解釈、プラトン解釈を語ってくれたものである。
卒業が近くなった頃、五十嵐君と私、そしてのちに筑波大学で数学教授となられた木村達夫君の三人で、数学科の伊藤清三先生―ルベーグ積分についての先生の書かれた教科書は今でも使われている-のご自宅でご馳走になったことがあった。そのとき、木村君が披露したベートーベンの「月光ソナタ」のピアノ演奏とともに、五十嵐君のホメ-ロス、とくに「イーリアス」の冒頭部分のギリシャ語による朗唱がきわだって記憶に残っている。木村君が合気道の達人であることは知っていたが、まさかピアノが弾けるとは思っていなかったので、その文武両道ぶりに驚いたわけだが、五十嵐君の「イーリアス」の朗唱もそれにおとらず素晴らしく、まるで平家物語を物語る琵琶法師の物語を聴いているかのような感があった。Klyde Pharr のHomeric Greekを入手して、遅ればせながら私がギリシャ語の学習を始めるようになったのは、全く五十嵐君の影響であった。
ギリシャ語の詩の世界の音韻の美しさもさることながら、プラトンの美学についての五十嵐君の独特の解釈にも大いに惹かれた。プラトンはソクラテスを主人公とする作品を書くことによって、「善のイデア」に向かう自己自身の人生を作品化したのだというのだ。その考え方にもとづいて、「神の友」となったプラトンについて五十嵐君は情熱を込めて語ってくれた。それはプラトン解釈という次元を超えて、各人が作者にして主人公に外ならない自己自身の人生を主題として書く文藝制作の作法(エクリチュール)の機微に触れるものだと思ったものである。
五十嵐君も私も、『国家』の有名な「洞窟の譬喩」や、詩人追放論をどう解釈すべきかという問題に関心があった。ミメーシス(創作的模倣)の達人でもあったプラトンがなぜ詩人のミメーシスを批判したのか?国家のイデア論では、常識人が現実だと思っている世界は、真実在の「影」ないし「模造」である。詩人追放論では、詩人は、そのような感性的な現実の模倣をこととし、「模造」の「模造」を語るが故に、真実から二重に遠ざかるがゆえに追放されるべきだとプラトンが非難しているように見える。しかし、五十嵐君は、そういうのは皮相な解釈だと言っていたように記憶している。「影の影」であっても、下手な詩人の通俗的な仕方ではなく、イデアそのものを影現させ、読者に如実にそれを直観させる新しい語り方、あるいは書き方をプラトンが発見したと言うことだったのだろう。
五十嵐君がなぜ数学科に進学されたのか、ご本人から聞いたことはなかったが、私の場合は非常に単純で、小林秀雄と岡潔の対談『人間の建設』を通じて、数学に関心を持ったからであった。リーマン全集、芭蕉の俳諧、道元禅師の正法眼蔵、そして浄土宗の改革者であった山崎弁栄の「無辺光」を座右の書としていた岡潔に、私は惹かれた。岡の「数学」は、単なる理性を超えた人間の心(情緒ないし霊性的自覚)に根ざしており、それがそのまま文藝と芸術と宗教の世界に通底していたことが一番の魅力だったからである。
理学部数学科を卒業後、五十嵐君は本郷の文学研究科の大学院で美学を専攻され、私のほうは、当時駒場に新設されたばかりの科学史・科学基礎論の大学院で、「科学哲学」を専攻したので、直接的な交流の機会はすくなくなった。ただし、駒場の伊東俊太郎先生の「ティマイオス」演習には、五十嵐君も参加されたので、このプラトンの後期対話篇を共に読むことができた。語学に天賦の才をもっていた五十嵐君とはちがって、「ティマイオス」のギリシャ語は私には難解であったが、数学科出身の我々にとってこの対話篇は、大いに知的想像力を刺激するものであった。五十嵐君も私も、数学を独自の記号言語を駆使して書かれた一種の詩と考える点で共通していた。当時の英米哲学で流行していた論理実証主義や分析哲学の論理は、数学科出身の我々から見ればせいぜい初等数学のレベルであり、そんなものには魅力は感じなかったのである。分析的論理ではなく想像力こそ数学の生命であり、それも事実を再生する二次的な想像力ではなく、新たなる作品を制作する原初的な想像力が数学という営みを支えており、それはプラトンの「ティマイオス」のようなコスモロジーに直結するのである。
私がホワイトヘッドとプラトンの研究に没頭しはじめた頃、五十嵐君はギリシャ語やラテン語の世界だけではあきたらなくなり、日本の哲学者達が無意識のうちに前提している西欧中心的な価値観を相対化するためだったのか、次第にイスラム研究に傾倒するようになった。
大学院修了後、五十嵐君は井筒俊彦先生の推挽でイラン王立アカデミーに留学され、医学・哲学からイスラムの神秘思想に至るまで幅広い学際的研究を継続された。イランで革命が勃発し王制が倒れた後で帰国したが、イスラム革命についての一般向けの啓蒙書を書く傍ら、イブン・スィーナーの『医事典範』の翻訳書、『知の連鎖―イスラムとギリシャの饗宴」「イスラーム・ルネッサンス」などを立て続けに出版し、私のもとにも贈ってくれた。それらの書物は、伊東俊太郎先生のアラビア科学史研究、井筒俊彦先生のイスラム神秘主義研究、井上忠先生のパルメニデス研究などの影響もたしかに認められたが、そういったあらゆる要素が統合されて、まさに五十嵐君でなければ書けない独創的な知的刺激に充ち満ちた本となっていた。
五十嵐君から頂いた本の中で、私が最も好きな本は『神秘主義のエクリチュール』である。「桃李歌壇」という和歌と連歌の結社をWEB上に創設した私もまた、彼と同じように道元の著作と良寛の和歌や漢詩に関心を持っていたからである。
道元の『典座教訓』に収録されている阿育王山の老典座との対話、良寛と貞心尼の相聞歌についての五十嵐君の解釈は、イスラム神秘主義の文献を参照しつつ、文字とは何か、修行とは何か、についての宗教の違いを超えた本物の神秘主義の著作のエクリチュール(文体、書法のエッセンス)を論じていた。
五十嵐君は、日常性を離れた特殊な少数の人にしか体験できない場所に神秘主義を見いだすのではなく、万人が経験しているはずの日常性のただなかにこそ本物の神秘があるといっているように思う。
学術の蘊奥を極めることは神秘主義とは無関係であり、宗教的エリートにのみ許された秘密の奥義の伝授などは「徧界曾て隠さず」と喝破した老典座の境涯とは無縁であり、「文字とは何か」と問われるならば、「一二三四五」のごとき幼児の初心に立ち返る学道にこそ凡てであるという簡明にして肺腑をえぐるような言葉がそこにあった。そこで、『神秘主義のエクリチュール』で引用されている良寛の歌を五十嵐君に捧げて、この思い出の結びとしたい。
それは、
君にかくあひ見ることのうれしさもまださめやらぬ夢かとぞ思ふ
という貞心尼の歌に対する良寛の返歌
夢の世にかつまどろみて夢をまた語るも夢もそれがまにまに
である。
五十嵐君は同書の中で、この歌を
沫雪の中に立ちたる三千世界(みちあふち) またその中に沫雪ぞ降る
という良寛の歌と対比させて論じた歌人上田三四二氏の解釈を長文に亘って引用している。
上田氏の解釈については、五十嵐君はその精緻さに感嘆しつつも、それは「超高級形而上学」の解釈になっているといって批判を加えている。この箇所は『神秘主義のエクリチュール』のなかでも特に興味深いところであるが、空間及び時間の中に無限包摂の「入れ籠構造」を見る上田氏に対して、五十嵐君は、主客の相互溶融、相互浸透という直接経験を重視されたようである。それは、「三千世界」を「一念三千」を説く天台宗の教学などと関係づけずに、「みちあふち」という「やわらかい」訓読を重視する読み方に関係している。五十嵐君に由れば「みち」は「道」であり「あふち」は「お家」である。要は、仏教的解釈よりも、「道」と「家」とそれを見る「私」が雪の中で相互溶解し相互浸透する直接経験の事実を重んじたのだろう。ここで「沫雪」を上田氏とは違って「牡丹雪」ではなく「粉雪」だと指摘しているところも面白かった。
「蓮の露」の相聞歌については、五十嵐君自身は、「(貞心尼のひたむきな情熱を前にして)いささか良寛が照れているのが良い」という以上には言わなかったが、「夢の中で夢を語る」ことは、今、五十嵐君の思い出を語る私自身の心境に何か合致する者があることを感じている。
私も、五十嵐君と同様に、上田三四二氏の歌の釈義には多くの点で共感するけれども、良寛が「夢の中に夢を見る」という場合、「夢の中の夢、その夢の中の夢、・・・・・」というような「入れ籠構造」は無いと思う。
道元の『正法眼蔵』に「夢中説夢」という巻があるが、そこでは、われわれが堅固な実在だと思っている世界が、じつは夢の如きはかなき虚仮の世界であり、真の仏法の世界は、虚仮の世界の住人から見ると逆に「夢」のごとく見えるという趣旨の言葉がある。
プラトンの「洞窟の譬喩」の如く、顛倒世界においては、真実在を説くものは役に立たない夢想家と見なされるが、道元は、むしろ「夢の中で夢を説く」ことの意義を理解しなければ、仏道はわからないと明言している。おそらく、影の影、夢の夢を如実に語るという詩人の行為のなかに、真実在の影現を見ることができるという読み方をするならば、良寛の返歌も、「夢の中で夢を語る」ことの大切さをさりげなく示した歌と言って良いであろう。
ー追記ー
「五十嵐一 追悼集ー未来への知の連鎖に向けて」(五十嵐一追悼集編集局編 非売品)が2018年7月9日に 出版されました。本日、追悼編集局の伊東庄一さんより追悼集を送っていただきました。上記の文章は、この追悼集に私が寄稿したものです。