シリーズで紹介している五島プラネタリウムのリーフレットの第22弾は2000年5月配布のものです。




当月のメインの話題は「活動最盛期に向かう太陽」で、表紙の画像はNASA・ESAの
太陽観測機SOHOが捉えた巨大プロミネンスの画像が採用されてました。ループ状
のイメージが見事です。まっすぐ伸ばすと太陽直径の半分近くになりそうな印象で
地球が数十個並べられそうです。
2ページ目に太陽についての基本的な記述があり、活動には11年の周期があって、
この2000年はちょうど極大を迎える時期にあたっており、我々の生活への悪影響
として電波通信や送電網への障害が危惧される一方、低緯度オーロラが見えること
があるとの説明があります。2024~25年も太陽活動極大期にあたっていて、昨年
も北海道などでオーロラが観測されたりしてました。
その太陽を宇宙空間から観測するSOHOは1995年末に打ち上げられ、これまで数々
の観測成果を上げてきてます。太陽をかすめる彗星の観測にも役立っていたりして
思わぬ場面での活躍もあります。今年で30年が経ちますが、まだ現役で頑張って
いるのは素晴らしいことだなーって思います。
3ページ目の「5月の観望メモ」には、この月の中旬に太陽周辺に5惑星が集合する
という珍しい現象があるとの説明があります。調べてみたらこんな状況でした。
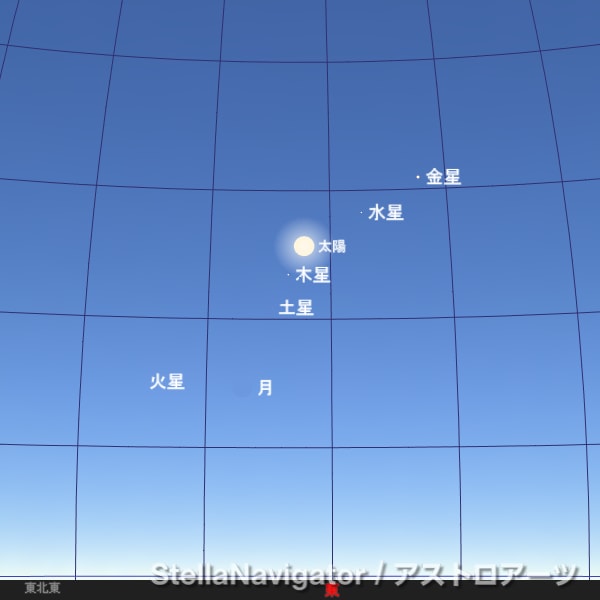
(AstroArts社ステラナビゲータによるシミュレーション)
これは中旬ではなく、こどもの日の朝7時における東天の状況です。月も加わって
1週間分の太陽系内天体が大集合してたんです。但し、太陽と同じ方向に集まって
いるので眼視では全く楽しめない現象であって、観測対象として話題になった記憶
はありません。
4ページ目には悲しいことに翌年3月に閉館するとのお知らせが掲載されてました。
しばらくして東急文化会館自体の消滅を知ることになります。











































