朝の散歩で写した植物です。(十月中旬)
ミゾソバ(タデ科)
☆川の近くに毎秋群生しており、薄いピンク色のつぼみが可愛く、つい毎秋撮っています。

イシミカワ(タデ科)
☆例の和名の由来図鑑によると、イシミカワの名の由来は諸説ある様です。
「薬草としての本種は石見川村(現、河内長野市)のものが良質だったから・・」の説
「石の様な実と皮だから・・・」の説 他。
アサガオ(ヒルガオ科)
☆ぽつんと一輪、爽やか水色でした。
タチバナモドキ(バラ科)の実
☆毎春、真っ白い花をたくさん付けているタチバナモドキ、
秋は真っ赤な実をたくさん実らせています。
コスモス(キク科)
☆種が飛んできたのか一輪だけ。以前は小群生がありましたが、淘汰されたのか・・
やはりセイタカアワダチソウには勝てない様です。
ジュズダマ(イネ科)
和名の由来辞典によると、「壺型の実を包む、硬い苞葉(ほうよう)を糸で
繋ぎ、数珠(じゅず)にした」とありました。
昔は食料として食べていた、とも。
マルバルコウ(ヒルガオ科)
毎秋、方々で群生しています。畑で群生すると害草扱いの
様ですが、マメアサガオ同様、花自体は可愛いと思います。
手持ちの野草図鑑、数冊にはいずれも掲載が無く、
「雑草図鑑」に載っていました。
ヤマメ茶屋から坂ノ谷登山口経由で氷ノ山へ登りました。
GPS軌跡(2度クリックでワイドに拡大されます。)
2021.10.9(土)
 △氷ノ山
△氷ノ山
行程:(往復)神戸三田IC=(中国自動車道)=山崎IC=R29=氷ノ山登山口/ヤマメ茶屋=駐車地ー(坂ノ谷林道)ー坂ノ谷登山口ー△氷ノ山三ノ丸ー△氷ノ山山頂
1/25000地形図:『戸倉峠』『氷ノ山』
宍粟50名山ルートマップ:『1氷ノ山三ノ丸』
メンバー:夫・自分
先月はEバイクで登った道ですが、久しぶりに歩いてみると
忘れかけていた発見が色々とありました。
朝日差す早朝の林道
今日はお天気が良さそうです。
坂ノ谷登山口へと殿下登山口への分岐
坂ノ谷登山口
昨年、伐採作業が行われて作業道が付けられた部分は
土が固められ、登山道の誘導ロープもありました。

地面に・・チャワンタケのなかまでしょうか。
緩やかな登山道は息切れの心配も無く、おしゃべりも弾みます。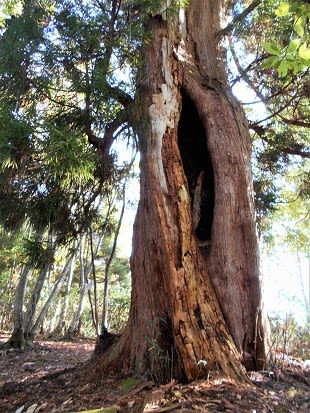
熊の大杉
観音大カツラ

大きな枝を伸ばすブナに、雪原の季節を思い出しました。
殿下登山道への分岐
氷ノ山若狭スキー場への分岐
ネマガリザサが海原の様です。この風景もあと数か月で雪原へ
変わると思うと、季節の変化に驚きます。
三ノ丸避難小屋
氷ノ山三ノ丸(宍粟50名山最高峰) 1464m 到着
今日は晴天で、山頂までくっきり眺められました。
展望櫓からは鳥取の海岸線も見えました。
山頂を目指します。
氷ノ山山頂のトイレ付休憩舎
ソーラー発電設置の為、作業用足場が組まれていました。
△氷ノ山 山頂避難小屋
☆小屋にて休憩。
△氷ノ山 1509.8m 登頂。
△一等三角点
標高:1509.77m
点名:「氷ノ山」(ひょうのやま)
☆7月以来の山頂でした。
下山は往路を戻ります。
ツタウルシの葉が真っ赤に紅葉していました。
小さなキノコも
今日は我が5班の方々とすれ違う予定でした。
どこかで会えると解っていても、姿が見えたら嬉しいものです。
脳みそみたいなキノコ
顔みたいな模様の甲虫(こうちゅう)カミキリムシの仲間でしょうか。
名前を調べ中。
無事、坂ノ谷登山口へ下山し、再び林道をヤマメ茶屋へ歩きます。
檜皮葺を剥いだ跡でしょうか、『檜皮葺』について初めて知ったのも、この場所でした。
車や自転車で通るのもいいですが、歩くと見える風景もありますね・・
足元の幼虫や
林道途中、羊ヶ滝入口横の橋げたには「昭和三十七年十一月架」と
刻まれていました。
橋の名前はひらがなで「そのはし」
更に下の方に架かる橋は「砥潟橋」と刻まれ、
「昭和三十六年十二月架」と。約60年の歴史ある橋だと解りました。
駐車地も近く、今日の登山が終わります。
☆来週に控えた氷ノ山ツアーへの下見を担当班で行う日でしたが、
夕刻早めに帰宅する都合があり、今日は別行動をさせていただきました。















