メタエンジニアの眼シリーズ(97) TITLE: 科学の統一
書籍名;「自然科学と社会科学の統一」 [1973]
著者;フィードラー 発行所;大月書店 発行日;1973.4.26
初回作成日;H30.12.27 最終改定日;H30.12.28
引用先;文化の文明化のプロセス Converging
このシリーズは文化の文明化プロセスを考える際に参考にした著作の紹介です。『 』内は引用部分です。
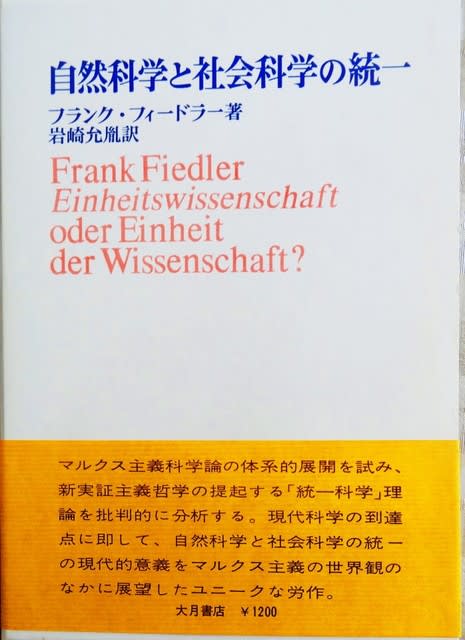
この書の原題は、『「統一科学」か科学の統一か?』で、1971年に発行されている。まだ社会主義と資本主義との勝負が決着していない時期(特に、ソ連が米国に先駆けて人工衛星を打ち上げたことは、資本主義側にとっては驚愕だった)に、どちらも唯物論(すなわち、人類による工業製品の生産競争)と新実証主義(のもごとの科学的な証明)を競っていた。特に、ドイツ社会主義においては、完全な社会の構築のためには、科学の統一により国家を運営することが必須と考えていたようである。
この著書は、「メタ科学」的な思考が盛り込まれている。しかし、本書では、「科学」の中に、「技術諸科学」を含めており、更に生産的機能を含む社会的諸機能を対象としているので、「メタエンジニアリング」の範囲も含んでいると考えるべきと思う。
この著書の狙いは、巻末の「解説」に、訳者の岩崎充胤氏によって述べれている。
『本書の主題が自然科学と社会科学との統一の問題を通じて科学の統一の問題を詳細に研究すること、そのさい、新実証主義の「統一科学」理論を批判しながら、マルクス・レーニン主義的な科学の統一の構想を展開することにある、・・・。』(pp.293)
その狙いを「緒言」では、このように書かれている。
『科学を首尾一貫して社会的再生産過程のなかに含ませ、社会主義的な大規模な研究を発展させ、精神的=創造的諸過程の有効性をそれらの合理化によって向上させる、という目標設定にある。この目標は、社会主義的な科学組織にもとづいてのみ十分に広範に達成することができる。社会主義的な科学組織の最も重要な課題の一つは、問題と過程とにそくして志向された学際的「間分化的」な研究を実現し、これをつうじて、構造諸科学、自然諸科学、技術諸科学およびマルクス・レーニン主義的社会諸科学の統一を全般的に実現するとにある。 』(pp.3)
この表現は、当時のドイツ科学アカデミーの議論とドイツ社会主義統一党の科学政策の委員会での議論に即している。
「科学」に関しては、アリストテレス、ベーコン、デカルト、ライプニッツ、カントなどの名を挙げ、『歴史的な事実は、現在においても科学はその諸規定の全体において哲学の正当な対象である、という結論を示唆しうるかもしれない。 しかし、このような結論にたいしてはとくに二つの決定約な要因が反対している。第一に、科学は根本的な変化を経験してきている。 人間の知識の範囲と科学的認識の発展のテンポとは、驚くべき規模に達している。科学によって代表される人間の知識の貯えは、ひとつの科学―たとえば哲学―によってはもはやつかみえないほどの広がりをもつようになった。この発展と手をたずさえて、すでに特徴づけたような科学の社会約な存在様式の徹底約な変容が進行している。社会の物質的生活の体系における科学の位置が革命的に変えられる。最後に、量的な点でも質的な点でも、科学の諸方法、科学研究の諾道具、科学の概念装置もまた、変化している』(pp.22)
また、「メタ科学」的な記述がある。
『つぎに、オッソウスカとオッソウスキは、科学についての科学を五つの下位区分に分類しようと試みるが、そのさいかれらは、科学者たちのもとでの それまで支配的な分業から出発する。
一、科学の哲学(科学の概念、諸科学の分類、法則、仮説などの諸問題)
二、科学の心理学(科学者の心理的発展、さまざまの研究者タイプ、 科学的活動のさまぎまのタイプと段階などの諸問題)
三、科学社会学(社会の構造や教育制度の組織にたいする科学の依存性、文化生活におよぼす科学の諸影響などの諸問題)
四、科学組織および科学と政治との諸関連の研究
五、科学史』(pp.29)
「統一科学」については、
『かれらがブィルタイとリッケルト の二元論的科学論との論争で一致して強調しているのは、諸科学が統一をなしているということである。かれらは考える、自然諸科学と社会諸科学との対立を主張することは、形而上学あるいは神学の残渣であり、科学が事実としてもっている性格と一致しない。現実には、諸科学は対象と方法によって統一を表している。ますます多くの諸文化への特殊化(専門化)は、もっぱら科学の営為の帰結なのであって、その内容の帰結ではない。認識として科学は、現実が統一的であるように、統一的である。』(pp.108)
「自然と社会」については、
『人間あるいは社会の自然にたいする関係を規定するという問題は、マルクス主義以前の哲学がいくたの試みをおこなってきたにもかかわらず、解決されてはいなかった。ほかならぬこの問題に正しい解答を与えることができるためには、マルクスの天才が必要であった。そのさいマルクスの功績は、まず第一に、かれが人間と自然との統一をたんに肯定し承認しているということにあるのではなく―そのことならマルクス主義以前の唯物論がすでにおこなっていた―、かれが この統一をどのようにとらえているかとつまり、本来的に実践的な関係としてとらえているということにある。』(pp.199)
マルクスの捉え方については、次のようにでてくる。
「マルクスとエンゲルス」の捉え方は。
『マルクスとエンゲルスは人間を自然的な存在として、自然の一部分としてとらえる。たとえばすでに『経済学・哲学手稿』では次のように言われている、「人間の肉体的および精神的な生活が自然と連関しているということの、ほかならぬ意味は、自然が自然自身と連関しているということである。 というのには、人間は自然の一部分であるから」と資本論でマルクスは書いている、』(pp.201)
「マルクス」における、人間と自然の関係は、
『マルクスの場合、人間は自然存在、自然力、あるいはまた自然対象としてとらえられるが、この規定は
自然にたいするなんらの受動的な、観照的な関係をも含んでいない。まったく反対に、人間はその自然と
の統一をただかれ自身の行為によって媒介し、規定し、制御することができる。労働は、人間と自然との
あいだの物質代謝を媒介するための、永続的な自然必然性である。 マルクスは初期の著作のわかりやすい
ことばでこのことを次のように定式化している、「人間は自然によって生きてゆく、という意味は、自然は人間の身体であり、人間は死なないためにはたえずこれとかかわりあっているのでなくてはならないということである」。自然との統一は自然にたいする能動的な関係を含んでいる、逆にいえば、自然にたいする能動的な関係が自然との統一を実現するのである。』(pp.203)
そして結論としては、
『科学の統一は自然科学と社会科学との統一と一致一するものではない。このことはすでにまえに指摘した。 すべての諸科学がこれらの二つの主要グループにはとても包括されえないという事実(例えば、数学やサイバネティックスはどちらのも属さない)が、こうした一致の 不可能なことをすでに明らかにしている。科学の統一は、もっと複雑であり、自然の諾科学と社会の諸科学との統一には還元されない。だが逆に、自然の諸科学と社会の諸科学との統一にもとづいていないような科学の統一も考えることができない。そればかりではなく、自然科学の諸分科と社会科学の諸分科との相互統一は科学の統一一般の根本前提であり、この相互統一の承認は科学の統一のどんな哲学的基礎づけの場合にもその根底をなしている。』(pp.218)
最後に「解説」のなかで、
『次に、本書のなかでフィードラーが協調している基本的な観点をいくつか指摘しておこう。
第一にあげられるのは、ドイツ民主共和国における社会主義体制の形成という根本課題のなかに、この研究を位置づけようというきわめて実践的な観点である。「緒言」のなかでかれは書いている、
「科学の続一は社会主義の社会体制では自然発生的にではなしに「目的意識的に」実現される。しかし他方では、科学の統一は、現在の生産力と科学との発展および社会主義体制一般の形成が無条件的に要求するところである。じっさい、自然科学と社会科学との統一が実現されるただそのときにのみ、科学は社会主義の社会体制におけるその社会的諸機能―科学の生産的機能、その計画と指導の機能、およびその育成と教育の機能―を果たすことができるからである。それゆえ、自然科学と社会科学との統一を意識的に遂行することは、ドイツ民主共和国の科学政策の最も本質的な諸目標のひとつである」。』(pp.295)
(実証主義は神学的・形而上学的なものに依拠せず、経験的事実にのみ認識の根拠を認める学問上の立場であり、19世紀のフランスの思想家・社会学者のオーギュスト・コントによって人類の発展における神学的段階と形而上学的段階の最後に来る実証主義的段階として唱えられた。
哲学の分野では理想主義、構成主義、方法主義などと対立した意味で使われることが多い。20世紀初頭に、哲学も自然科学同様の実証性を備えるべきであるとする主張がウィーン学団によってなされ、彼らは自らの主張を論理実証主義(論理的経験主義、新実証主義)と称した。 Wikipediaより)
(唯物論は、文脈に応じて様々な形をとるが、よく知られたものに以下のようなものがある。
世界の理解については、原子論と呼ばれる立場がよく知られている。これは原子などの物質的な構成要素とその要素間の相互作用によって森羅万象が説明できるとする考え方で、場合によっては、森羅万象がそのような構成要素のみから成っているとする考え方である。非物質的な存在を想定し、時にそのような存在が物質や物理現象に影響を与えるとする二元論や、物質の実在について否定したり、物質的な現象を観念の領域に付随するものとする観念論の立場と対立する。→経験論、現象学も参照のこと
生物や生命の理解に関しては、生命が物質と物理的現象のみによって説明できるとする機械論があり、生気論と対立する。また、生物が神の意志や創造行為によって産み出されたとする創造論を否定し、物質から生命が誕生し、進化を経て多様な生物種へと展開したとする、いわゆる進化論の立場も、唯物論の一種と考えられることがある。
歴史や社会の理解に関しては、科学的社会主義(=マルクス主義)の唯物史観(史的唯物論)が特によく知られている。理念や価値観、意味や感受性など精神的、文化現象が経済や科学技術など物質的な側面によって規定(決定ではないことに注意)されるとする立場をとる。また、社会の主な特徴や社会変動の主な要因が経済の形態やその変化によって規定される、とする。Wikipediaより)
書籍名;「自然科学と社会科学の統一」 [1973]
著者;フィードラー 発行所;大月書店 発行日;1973.4.26
初回作成日;H30.12.27 最終改定日;H30.12.28
引用先;文化の文明化のプロセス Converging
このシリーズは文化の文明化プロセスを考える際に参考にした著作の紹介です。『 』内は引用部分です。
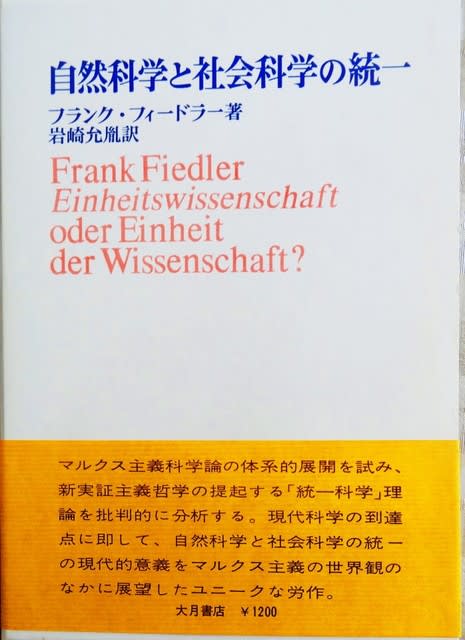
この書の原題は、『「統一科学」か科学の統一か?』で、1971年に発行されている。まだ社会主義と資本主義との勝負が決着していない時期(特に、ソ連が米国に先駆けて人工衛星を打ち上げたことは、資本主義側にとっては驚愕だった)に、どちらも唯物論(すなわち、人類による工業製品の生産競争)と新実証主義(のもごとの科学的な証明)を競っていた。特に、ドイツ社会主義においては、完全な社会の構築のためには、科学の統一により国家を運営することが必須と考えていたようである。
この著書は、「メタ科学」的な思考が盛り込まれている。しかし、本書では、「科学」の中に、「技術諸科学」を含めており、更に生産的機能を含む社会的諸機能を対象としているので、「メタエンジニアリング」の範囲も含んでいると考えるべきと思う。
この著書の狙いは、巻末の「解説」に、訳者の岩崎充胤氏によって述べれている。
『本書の主題が自然科学と社会科学との統一の問題を通じて科学の統一の問題を詳細に研究すること、そのさい、新実証主義の「統一科学」理論を批判しながら、マルクス・レーニン主義的な科学の統一の構想を展開することにある、・・・。』(pp.293)
その狙いを「緒言」では、このように書かれている。
『科学を首尾一貫して社会的再生産過程のなかに含ませ、社会主義的な大規模な研究を発展させ、精神的=創造的諸過程の有効性をそれらの合理化によって向上させる、という目標設定にある。この目標は、社会主義的な科学組織にもとづいてのみ十分に広範に達成することができる。社会主義的な科学組織の最も重要な課題の一つは、問題と過程とにそくして志向された学際的「間分化的」な研究を実現し、これをつうじて、構造諸科学、自然諸科学、技術諸科学およびマルクス・レーニン主義的社会諸科学の統一を全般的に実現するとにある。 』(pp.3)
この表現は、当時のドイツ科学アカデミーの議論とドイツ社会主義統一党の科学政策の委員会での議論に即している。
「科学」に関しては、アリストテレス、ベーコン、デカルト、ライプニッツ、カントなどの名を挙げ、『歴史的な事実は、現在においても科学はその諸規定の全体において哲学の正当な対象である、という結論を示唆しうるかもしれない。 しかし、このような結論にたいしてはとくに二つの決定約な要因が反対している。第一に、科学は根本的な変化を経験してきている。 人間の知識の範囲と科学的認識の発展のテンポとは、驚くべき規模に達している。科学によって代表される人間の知識の貯えは、ひとつの科学―たとえば哲学―によってはもはやつかみえないほどの広がりをもつようになった。この発展と手をたずさえて、すでに特徴づけたような科学の社会約な存在様式の徹底約な変容が進行している。社会の物質的生活の体系における科学の位置が革命的に変えられる。最後に、量的な点でも質的な点でも、科学の諸方法、科学研究の諾道具、科学の概念装置もまた、変化している』(pp.22)
また、「メタ科学」的な記述がある。
『つぎに、オッソウスカとオッソウスキは、科学についての科学を五つの下位区分に分類しようと試みるが、そのさいかれらは、科学者たちのもとでの それまで支配的な分業から出発する。
一、科学の哲学(科学の概念、諸科学の分類、法則、仮説などの諸問題)
二、科学の心理学(科学者の心理的発展、さまざまの研究者タイプ、 科学的活動のさまぎまのタイプと段階などの諸問題)
三、科学社会学(社会の構造や教育制度の組織にたいする科学の依存性、文化生活におよぼす科学の諸影響などの諸問題)
四、科学組織および科学と政治との諸関連の研究
五、科学史』(pp.29)
「統一科学」については、
『かれらがブィルタイとリッケルト の二元論的科学論との論争で一致して強調しているのは、諸科学が統一をなしているということである。かれらは考える、自然諸科学と社会諸科学との対立を主張することは、形而上学あるいは神学の残渣であり、科学が事実としてもっている性格と一致しない。現実には、諸科学は対象と方法によって統一を表している。ますます多くの諸文化への特殊化(専門化)は、もっぱら科学の営為の帰結なのであって、その内容の帰結ではない。認識として科学は、現実が統一的であるように、統一的である。』(pp.108)
「自然と社会」については、
『人間あるいは社会の自然にたいする関係を規定するという問題は、マルクス主義以前の哲学がいくたの試みをおこなってきたにもかかわらず、解決されてはいなかった。ほかならぬこの問題に正しい解答を与えることができるためには、マルクスの天才が必要であった。そのさいマルクスの功績は、まず第一に、かれが人間と自然との統一をたんに肯定し承認しているということにあるのではなく―そのことならマルクス主義以前の唯物論がすでにおこなっていた―、かれが この統一をどのようにとらえているかとつまり、本来的に実践的な関係としてとらえているということにある。』(pp.199)
マルクスの捉え方については、次のようにでてくる。
「マルクスとエンゲルス」の捉え方は。
『マルクスとエンゲルスは人間を自然的な存在として、自然の一部分としてとらえる。たとえばすでに『経済学・哲学手稿』では次のように言われている、「人間の肉体的および精神的な生活が自然と連関しているということの、ほかならぬ意味は、自然が自然自身と連関しているということである。 というのには、人間は自然の一部分であるから」と資本論でマルクスは書いている、』(pp.201)
「マルクス」における、人間と自然の関係は、
『マルクスの場合、人間は自然存在、自然力、あるいはまた自然対象としてとらえられるが、この規定は
自然にたいするなんらの受動的な、観照的な関係をも含んでいない。まったく反対に、人間はその自然と
の統一をただかれ自身の行為によって媒介し、規定し、制御することができる。労働は、人間と自然との
あいだの物質代謝を媒介するための、永続的な自然必然性である。 マルクスは初期の著作のわかりやすい
ことばでこのことを次のように定式化している、「人間は自然によって生きてゆく、という意味は、自然は人間の身体であり、人間は死なないためにはたえずこれとかかわりあっているのでなくてはならないということである」。自然との統一は自然にたいする能動的な関係を含んでいる、逆にいえば、自然にたいする能動的な関係が自然との統一を実現するのである。』(pp.203)
そして結論としては、
『科学の統一は自然科学と社会科学との統一と一致一するものではない。このことはすでにまえに指摘した。 すべての諸科学がこれらの二つの主要グループにはとても包括されえないという事実(例えば、数学やサイバネティックスはどちらのも属さない)が、こうした一致の 不可能なことをすでに明らかにしている。科学の統一は、もっと複雑であり、自然の諾科学と社会の諸科学との統一には還元されない。だが逆に、自然の諸科学と社会の諸科学との統一にもとづいていないような科学の統一も考えることができない。そればかりではなく、自然科学の諸分科と社会科学の諸分科との相互統一は科学の統一一般の根本前提であり、この相互統一の承認は科学の統一のどんな哲学的基礎づけの場合にもその根底をなしている。』(pp.218)
最後に「解説」のなかで、
『次に、本書のなかでフィードラーが協調している基本的な観点をいくつか指摘しておこう。
第一にあげられるのは、ドイツ民主共和国における社会主義体制の形成という根本課題のなかに、この研究を位置づけようというきわめて実践的な観点である。「緒言」のなかでかれは書いている、
「科学の続一は社会主義の社会体制では自然発生的にではなしに「目的意識的に」実現される。しかし他方では、科学の統一は、現在の生産力と科学との発展および社会主義体制一般の形成が無条件的に要求するところである。じっさい、自然科学と社会科学との統一が実現されるただそのときにのみ、科学は社会主義の社会体制におけるその社会的諸機能―科学の生産的機能、その計画と指導の機能、およびその育成と教育の機能―を果たすことができるからである。それゆえ、自然科学と社会科学との統一を意識的に遂行することは、ドイツ民主共和国の科学政策の最も本質的な諸目標のひとつである」。』(pp.295)
(実証主義は神学的・形而上学的なものに依拠せず、経験的事実にのみ認識の根拠を認める学問上の立場であり、19世紀のフランスの思想家・社会学者のオーギュスト・コントによって人類の発展における神学的段階と形而上学的段階の最後に来る実証主義的段階として唱えられた。
哲学の分野では理想主義、構成主義、方法主義などと対立した意味で使われることが多い。20世紀初頭に、哲学も自然科学同様の実証性を備えるべきであるとする主張がウィーン学団によってなされ、彼らは自らの主張を論理実証主義(論理的経験主義、新実証主義)と称した。 Wikipediaより)
(唯物論は、文脈に応じて様々な形をとるが、よく知られたものに以下のようなものがある。
世界の理解については、原子論と呼ばれる立場がよく知られている。これは原子などの物質的な構成要素とその要素間の相互作用によって森羅万象が説明できるとする考え方で、場合によっては、森羅万象がそのような構成要素のみから成っているとする考え方である。非物質的な存在を想定し、時にそのような存在が物質や物理現象に影響を与えるとする二元論や、物質の実在について否定したり、物質的な現象を観念の領域に付随するものとする観念論の立場と対立する。→経験論、現象学も参照のこと
生物や生命の理解に関しては、生命が物質と物理的現象のみによって説明できるとする機械論があり、生気論と対立する。また、生物が神の意志や創造行為によって産み出されたとする創造論を否定し、物質から生命が誕生し、進化を経て多様な生物種へと展開したとする、いわゆる進化論の立場も、唯物論の一種と考えられることがある。
歴史や社会の理解に関しては、科学的社会主義(=マルクス主義)の唯物史観(史的唯物論)が特によく知られている。理念や価値観、意味や感受性など精神的、文化現象が経済や科学技術など物質的な側面によって規定(決定ではないことに注意)されるとする立場をとる。また、社会の主な特徴や社会変動の主な要因が経済の形態やその変化によって規定される、とする。Wikipediaより)












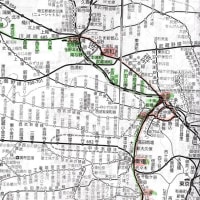


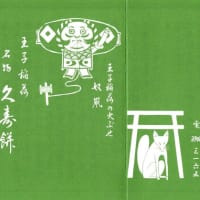




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます