TITLE: 書籍名;「我関わる、ゆえに我あり」 [2012]
著者;松井孝典 発行所;集英社新書 0631G
発行日;2012.2.22
初回作成年月日;H29.2.20 最終改定日;H30.7.21
引用先;文化の文明化のプロセス
Converging & Implementing
このシリーズはメタエンジニアリングで「文化の文明化」を考える際に参考にした著作の紹介です。『 』内は引用部分です。
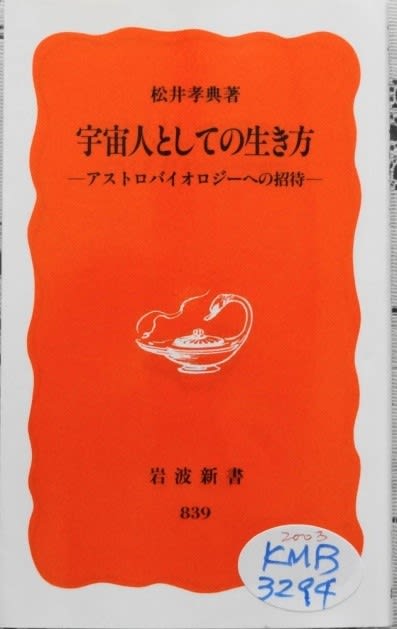
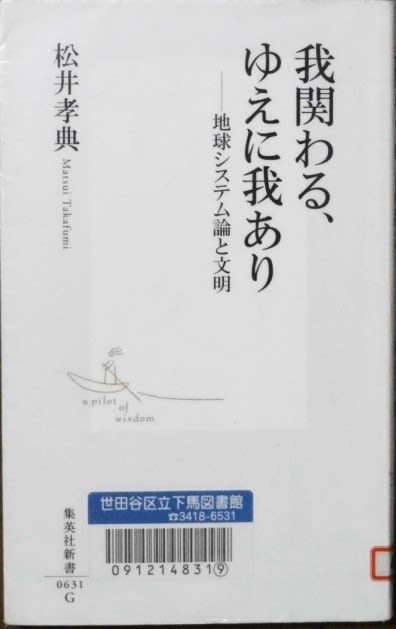
著者の松井孝典氏は、地球惑星科学者を称する東京大学理学部教授で多くの著書がある。150億光年の空間スケールで地球と文明を考えようとする「アストロバイオロジー」を主張する。現代の、環境・人口・食料などの問題を、地球システムの問題として、ひとつの宇宙人の立場で新たな視点を探っている。
彼の著書の3冊目。かなり集大成の感がある。(前2冊は、メタエンジニアの眼(19)で紹介済み。
あとがきより、
『変動の人間圏への影響のことを災害といいます。
人間圏が肥大化すればその変動の影響を大きく受けることになります。人間圏に深刻な影響を及ぼすでしょうし、人間圏と地球システムの調和という問題にはそのことも含まれます。自然災害の巨大化と地球環境問題とは問題の因果関係の裏表に他なりません。それはまた人間圏の駆動力の問題にもつながります。そのために文明とは何かを問い直す視点があってもよい。それはまさに明治維新以来のこの国の形を見直すことにもつながります。』(pp.222)
・ゴーギャンはなぜ文明を問うたのか
ボストン美術館所蔵の有名な「我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くの、か」の絵を示して、『1897年、故郷フランスから遠く離れた南の島タチヒで、描きあげられました。急速に変化を遂げてゆく文明社会に対する懐疑と絶望、そして、そうした文明をつくり上げた人間という存在に対する根源的な問いかけ。それらをゴーギャンは絵画という芸術に見事に昇華させました。』(pp.56)
彼の、前2冊からの持論を纏めた形で
『人間圏と地球システムの関係を、人間圏の発展段階ごとに図にしてみました。』(pp.148)
図1は、「生命の惑星段階」として、中央に「地圏」があり、周囲を「大気圏」、「水圏」、「生物圏」が離れて存在する。人間は、「生物圏」の中の小さな存在としてある。
図2は、「文明の惑星段階」として、3つの圏に重なり部分が生じると同時に、第4の「人間圏」が現れる。
図3は、「地球システムⅡの文明の惑星段階」として、人間圏だけが巨大化して、地球システム全体と等価の大きさに近づく。
図4は、「21世紀の地球システム」として、人間圏が更に巨大化して、地球システム全体を飲み込んでしまう。
図4の解説は次のようにある。
『人間圏はさらに拡大を続けます。駆動力に注目すれば、人間圏は地球システムの駆動力をはるかに超えるようになります。そのため、人間圏と地球システムの関係は非常に不安定になります。一方で、地球システムと調和的な人間圏という意味では、地球システムを超えて大きくなることができないため、その内部で何らかの強制的な変化を求められるようになります。』(pp.152)
結論は、次のように語られている。
『文明の誕生と発展が、我々の認識の時空を拡大し、宇宙における観測者として、その宇宙が存在することに意味をもたらすことになったことは、実は文明とは何かを問ううえで忘れてはならないことです。しかしその存在が一方で、文明の存続にかかわる問題を引き起こしているという「文明のパラドックス」に、我々は挑むしかないのです。』(pp.153)
彼は、これらの集大成ともいえる「全・地球学」を纏めた。その本については、メタエンジニアの眼(69)で紹介しようと思ています。
著者;松井孝典 発行所;集英社新書 0631G
発行日;2012.2.22
初回作成年月日;H29.2.20 最終改定日;H30.7.21
引用先;文化の文明化のプロセス
Converging & Implementing
このシリーズはメタエンジニアリングで「文化の文明化」を考える際に参考にした著作の紹介です。『 』内は引用部分です。
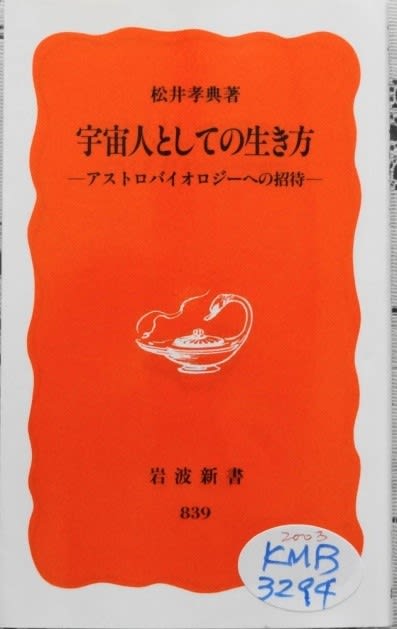
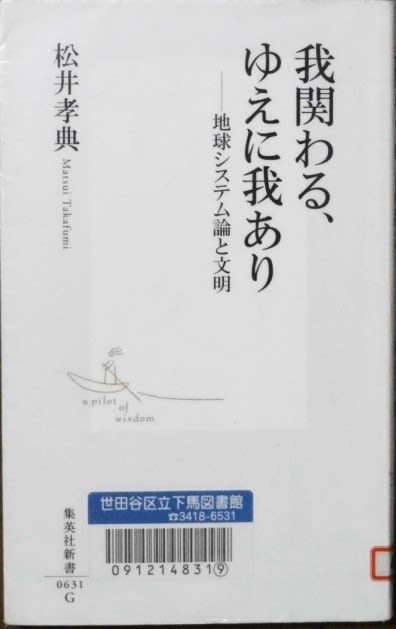
著者の松井孝典氏は、地球惑星科学者を称する東京大学理学部教授で多くの著書がある。150億光年の空間スケールで地球と文明を考えようとする「アストロバイオロジー」を主張する。現代の、環境・人口・食料などの問題を、地球システムの問題として、ひとつの宇宙人の立場で新たな視点を探っている。
彼の著書の3冊目。かなり集大成の感がある。(前2冊は、メタエンジニアの眼(19)で紹介済み。
あとがきより、
『変動の人間圏への影響のことを災害といいます。
人間圏が肥大化すればその変動の影響を大きく受けることになります。人間圏に深刻な影響を及ぼすでしょうし、人間圏と地球システムの調和という問題にはそのことも含まれます。自然災害の巨大化と地球環境問題とは問題の因果関係の裏表に他なりません。それはまた人間圏の駆動力の問題にもつながります。そのために文明とは何かを問い直す視点があってもよい。それはまさに明治維新以来のこの国の形を見直すことにもつながります。』(pp.222)
・ゴーギャンはなぜ文明を問うたのか
ボストン美術館所蔵の有名な「我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くの、か」の絵を示して、『1897年、故郷フランスから遠く離れた南の島タチヒで、描きあげられました。急速に変化を遂げてゆく文明社会に対する懐疑と絶望、そして、そうした文明をつくり上げた人間という存在に対する根源的な問いかけ。それらをゴーギャンは絵画という芸術に見事に昇華させました。』(pp.56)
彼の、前2冊からの持論を纏めた形で
『人間圏と地球システムの関係を、人間圏の発展段階ごとに図にしてみました。』(pp.148)
図1は、「生命の惑星段階」として、中央に「地圏」があり、周囲を「大気圏」、「水圏」、「生物圏」が離れて存在する。人間は、「生物圏」の中の小さな存在としてある。
図2は、「文明の惑星段階」として、3つの圏に重なり部分が生じると同時に、第4の「人間圏」が現れる。
図3は、「地球システムⅡの文明の惑星段階」として、人間圏だけが巨大化して、地球システム全体と等価の大きさに近づく。
図4は、「21世紀の地球システム」として、人間圏が更に巨大化して、地球システム全体を飲み込んでしまう。
図4の解説は次のようにある。
『人間圏はさらに拡大を続けます。駆動力に注目すれば、人間圏は地球システムの駆動力をはるかに超えるようになります。そのため、人間圏と地球システムの関係は非常に不安定になります。一方で、地球システムと調和的な人間圏という意味では、地球システムを超えて大きくなることができないため、その内部で何らかの強制的な変化を求められるようになります。』(pp.152)
結論は、次のように語られている。
『文明の誕生と発展が、我々の認識の時空を拡大し、宇宙における観測者として、その宇宙が存在することに意味をもたらすことになったことは、実は文明とは何かを問ううえで忘れてはならないことです。しかしその存在が一方で、文明の存続にかかわる問題を引き起こしているという「文明のパラドックス」に、我々は挑むしかないのです。』(pp.153)
彼は、これらの集大成ともいえる「全・地球学」を纏めた。その本については、メタエンジニアの眼(69)で紹介しようと思ています。












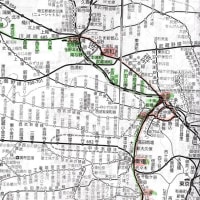


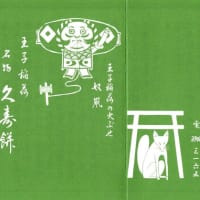




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます