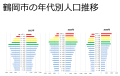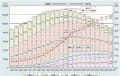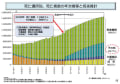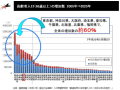4月から、新しい脳卒中地域連携パスが運用されています。
14日(火曜日)に、その門出を祝ってのキックオフ会を行いました。
---------------------------------------
新脳卒中地域連携パスキックオフ会
日時:平成28年6月14日 19:00~20:40
場所:荘内病院講堂
参加者:118名
---------------------------------------
内容については、妻のFBへの投稿を引用し紹介します。
-------------------------------------------------------------------------
今週の火曜日14日は、脳卒中地域連携パス新システムのキックオフ会でした!👍
鶴岡地区は急性期、回復期から維持期までITで全例登録していますが、今回はNet4Uと連動するパスシステムにリニューアルされましたヽ(*´▽)ノ♪
維持期の診療所への紹介も兼ねての新作発表会でしたが、荘内病院脳外科の佐藤先生からは「知っておきたい新脳卒中ガイドライン」湯田川温泉リハビリテーション病院の武田院長からは新ガイドラインと「回復期病院の役割」、荘内病院神経内科で、データマイニングチームのリーダー丸谷先生からは、全例登録のデータからの分析結果と課題、ストローハット社社長の鈴木さんからは新Net4Uパスの特徴、そして維持期代表藤島の石橋先生と看護師さんからは、どんなところが使いやすくなったかを、具体的に実際の画面で教えていただきました。
新ガイドラインで新たな知識を得て、パスデータをしっかり入力することで地域の脳卒中疾患管理に貢献できることを認識し、新システムの使いやすさも分かりました☺
維持期の先生方も、おお、これならやってみようかな?!と思っていただけたのではないでしょうか\(^o^)/
会場いっぱいのご参加、ありがとうございました~👋😃💦
尚、来月7月12日火曜日のパス協議会大懇親会にも、参加費2000円だけ持って、是非ご参加くださいませ(*^▽^)/★*☆♪
-------------------------------------------------------------------------
新しい脳卒中パスのおもな変更点は以下になります。(丸谷先生のスライドから)
・酒田地区との統一パスシステムを構築
→今後庄内全域で病診連携展開を検討
・急性期・回復期の機能評価項目の見直し、認知機能評価の追加
→維持期でのADL低下や再発予防に活かせる情報提供
・バリアンス分析をより簡便化し、パスの改訂につなげる
→パスの質向上、鶴岡みらい健康調査研究との連動などから前向きデータベースへ
・「LDH/HbA1c/CCr」項目の追加・抗血栓療法など主要薬剤投与リストの作成
→リスク管理を含めた再発予防医療の継続・質の担保、向上
・Net4Uを利用したリアルタイムな医療情報共有
・パスと並行する「わたしの健康ノート」を利用した多職種連携
地域連携パスがADL改善や再発予防に効果があるかどうかは明らかでない
→当地区から新たなエビデンスの発信を目指そう!
以下は講演メモ。
1、開会
2、あいさつ
3、講演
1)「知っておきたい脳卒中治療ガイドライン」
荘内病院 統括診療部長 佐藤 和彦 先生
鶴岡地区の脳卒中パス
・救急隊が指導する、超急性期パス
・リハビリ病院へつなぐ、病院間連携パス
・再発予防を地域にお願いする地域連携パス
・「私の健康ノート」
脳梗塞急性期外科治療(5項目)
推奨グレードAは、大脳の開頭外減圧
脳梗塞急性期治療(16項目)
推奨グレードA は、脳梗塞血栓溶解療法、血管内治療の追加、抗血小板療法
脳と心臓の違い:脳では、PCIのような有効性の高い確立した治療がない
脳梗塞慢性期外科治療:推奨グレードAは、頸動脈内膜剥離術(CEA)
抗血小板治療:
無症候性脳梗塞、閉塞・狭窄、無症候性頭蓋内閉塞・狭窄は、推奨グレードC
心房細動には使うべきではない
結語
・脳卒中を疑ったら救急車
・急性期治療は、t-PA(4.5時間以内)
・スピードの重要性がさらに高まった
・2次予防では、他の循環器病も予防(冠疾患予防など)
2)「回復期医療からみた「脳卒中ガイドライン2015」と脳卒中診療における回復期病院の役割」
湯田川温泉リハビリテーション病院 脳神経外科 武田憲夫先生
ガイドラインは、臨床家の裁量権を規制するものではなく、一般的な考え方を示すものと理解すべき
急性期のリハ:できるだけ発症後早期から開始すべき(推奨グレードA)
回復期リハ:(推奨グレードB)
維持期リハ:(推奨グレードA)
地域連携パス:切れ目のない医療を提供するためのツールとして重要(推奨グレードC)
中枢性神経痛に対するリリカ(推奨グレードB)
上下肢の痙攣に対するボツリヌス療法(推奨グレードA)
嚥下障害に対するリハビリテーション:(推奨グレードA)
急性期の嚥下障害に対する胃瘻(推奨グレードB)
言語聴覚療法(推奨グレードB)
回復期病院の役割
1、機能回復
2、合併症予防
転倒転落を減らすさまざまな取り組みで、転倒転落率は、優位に減少した
3、再発予防、
血圧管理、
生活習慣の改善(食事、禁煙、節酒など)
4、社会復帰、生活復帰
自動車運転再開マニュアルを運用
5、薬剤の整理
6、地域医療連携
7、そして
患者さん、ご家族に、希望と元気をあたえよう
希望と元気は、回復のエネルギー
3)地域で支える脳卒中地域連携パスの運用
荘内病院神経内科 丸谷 先生
3500名を超えるデータ分析から
高齢化、女性が増えている
アテローム血栓性脳梗塞が減、心原性、病型不明が増加傾向
67%が在宅復帰、
何らかの障害をもつ患者 73%
維持期では、退院後6か月で改善する例が多い
一方で、退院後6か月以降に、ADL悪化例が軽症例で20%程度みられる、
血圧管理は、73%が達成されていた
一方、新ガイドライン(ラクナ梗塞、抗血栓薬服用中は130/80未満)の条件では、48%の達成率にとどまった
CKDstageの進行に伴い脳卒中の発生率が上昇 脳卒中の40%にCKD
心房細動の既往患者に脳卒中発症率が高い
4)Net4 PATHシステム
(株)ストローハット社 鈴木 哲 氏
新脳卒中パスシステムについての解説
・ブラウザで動作するシステムへ(特別のアプリは必要なくなった)
・ログインは、施設単位からユーザー単位へ
・Net4Uとの連動機能
5)維持期側のチェック・ポイント・活用術
石橋内科胃腸科医院 石橋 学 先生
まだ、運用事例がすくないが、実際使ってみての使い勝手について解説