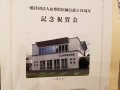4月1日から、新たに「介護予防・生活支援総合事業」が始まることもあり、その説明会を兼ねた「これからの地域のあり方」を考えるという趣旨のフォーラムでした。
厚労省東北厚生局と鶴岡市からの行政説明のあと、温海地域(福栄地区、木野俣)での地域での生きがいづくりの活動、鶴岡市の取り組み、医師会からは「ほたる」の活動について、それぞれ15分程度のプレゼンテーションがあり、大橋氏のコーディネートの下で、パネリスト間で意見交換が行われました。
議論は専ら、「住民主体の地域づくり」をどう実現するかというテーマで進められ、
今後、少子高齢化が進み、ケアする人材(家族も含め)が不足するなか、
自助(自らの健康管理、自分ことは自分でなど)、互助(住民の支え合い、ボランティア活動、生きがい就労など)
が重要ということで、議論が集約したように思います。
--------------------------------------------------------
地域力を引き出すフォーラム
~ 住み慣れた地域で自分らしい暮らしを ~
地域包括ケアと介護予防・日常生活支援総合事業のあり方
日時:平成29年3月22日(水曜日)
時間:18:00 ~ 20:50
会場:出羽庄内国際村ホール
--------------------------------------------------------
1、開会
2、第1部 行政説明
1、介護保険制度の現状等
(1)地域包括ケアシステムと介護予防・日常生活支援総合事業の現状と今後の動向
厚生労働省 東北厚生局 健康福祉部
地域包括ケア推進課 課長 内山 徹 氏
総合事業は地域づくりに移行して終わりではない。
住民の多様な主体が参画して地域の支え合い体制づくりを推進
要支援者に対する効果的かつ効率的な支援を可能とするサービスの充実
地域ケア会議:自立支援を目指した取り組み
(2)鶴岡市における介護予防・日常生活支援総合事業
鶴岡市健康福祉部 長寿介護課 課長 菅原 繁 氏
3、第2部 パネル・ディスカッション
地域包括ケアシステムを支える地域の力について、在宅福祉・在宅医療・地域の実践活動の紹介と報告
コーディネーター:NPO法人 日本地域福祉研究所 理事長 大橋謙策 氏
・住み慣れた地域で自分らしい生活をどうすれば実現できるか
家族がいない人(一人暮らし)を想定して、考えて欲しい
・介護保険料、使わなければ損という意識(発想)を変える必要がある
・社会参加と介護予防効果の関係
地域活動は、認知症予防になる
◇元気な高齢者の「ちから」を活かした地域おこし
事業実践地域代表「福の里」(温海地域)
事務局長:五十嵐 正直氏
・地元学としての村の宝探し
・鶴岡市単独事業の集落活性化事業による「集落振興ビジョン」の作成
1)地域コミュニティーの推進
2)地域資源を活用した生きがいづくり
3)安全、安心な地域づくり
4)生活環境の整備
24-26年 年間50万で事業実施
・高齢者の居場所づくり
-健康相談室の設置と医師の派遣
-健康器具の設置
-なり元気の実施(10回)
-関川地区特産のしな織支援
-あったか弁当
-特産品の加工、販売
-買い物ツアーの実施
-集落センターを寄り所として開放
・より良く継続していくために
-楽しくやりがいのあること
-有償であること、ボランティアではなく
-入会、脱退は自由
-地域づくりを担っていることの自覚
-お年寄りならでは知恵の活用
-他人の悪口を言わない
・目指す理念
-住んでいる人達が、美しく住もうと思って、初めて美し村ができる
-孤独死のない地域 (地域での見守り)
◇介護予防・日常生活支援総合事業:鶴岡市の取り組み
鶴岡市健康福祉部 相澤 康夫 氏
ニーズの増加、
B型 あるいは C型でなんとかなる
生活支援コーディネーターなしで B型が機能するのか
社協との協働を検討してはどうか
基本チェックリスト(全国一律)が鶴岡に合っていないのではないか
高校卒で、介護福祉士の資格をもっているひとを活用してはどうか
難聴とうつ病が関係しているといわれている、
◇鶴岡地区における在宅医療・介護連携推進事業の取り組み
鶴岡地区医師会 三原一郎
・ほたるの介護保険制度上における地域での役割について、設立の経緯や具体的な活動事例を示しつつ概説した。
・在宅療法支援診療所の数
・病院から地域へのコーディネートは誰が担っているのか
・口腔ケアは重要だが、歯科医の往診は
・ショートステイ空きベット情報の利用率は
--------------------------------------------------------------
地域包括ケアシステムとは何ですか
・誰もが住み慣れた家で、誰もが、地域で、安心して暮らし続けられること
地域包括ケアシステムが必要なわけは?
・「ふつうの幸せ」を手にするのが難しい時代になり、誰もが「生きづらさ」を抱えた生活を余儀なくされているから
・生きずらさの根っこにあるのは<ケア=世話>の問題
ケアの問題とは?
・これまで以上にケアが求められる
・にもかかわらず、ケアの提供が減っている
・この問題を浮き彫りにしたのは、急激な少子高齢化
・地域包括ケアシステムを考えるということは、急増するケアにどう対応するかを考えることに他ならない
増大するケアの必要に対して、どうすればいいのですか?
・ケアを必要とする状態をむやみに増やさないようにすること
・ケアに関わる人を増やして、数多くのケアを寄せ集める方法を考える
・寄せ集めケアを、必要としている人に対して効果的に割り当てる
・ケアの問題を家族の内部に留め置かないで、地域や社会で引き受ける
どうしてケアにこだわるのか
・ケアは、すぐに解決できるものから専門的なものまで一続きだから、