TRIO(現KENWOOD)のメンテナンス記事は、いくつか書きました。もう40年以上も昔の無線機なので、いろいろと不具合が出ていたのだが、あまりに古すぎるのでメーカーは面倒を見てくれない。
数か月かかって、苦労の末ほぼ初期の性能に戻しましたが、ランプは手つかずにしておいた。というのも、バンドSW、FIXチャンネルSWのランプは前面パネルの奥の方にあり、交換するとなるとちょー大変なのは分かっていたからなのである。
こないだ電源を入れたら、バンドSWのランプが点灯しないのである。オーマイガー! ついに、その日が来てしまいました。ストロボ焚くと、点灯しているか否かは良く分からなくなりますが、バンドSWのみ消灯してます。(この時は、メインダイヤルのランプは点灯している)

ランプ切れだよなぁ。交換するか・・
上部カバー・下部カバーを取り外し、全面パネルの皿ねじ4個を外すと、パネルが前面に倒れます。その、ずっと奥にランプがあるので、ラジオペンチで注意深く取り外します。

交換用のLEDは、手持ちのELEKIT社の赤色LEDを使用します。

ランプは12V用が使われています。LEDは極性があるので、プラス・マイナスを間違えないように接続します。コードなどは現物合わせにして、余分な部分はカットします。
パネル部分は配線が多く、狭いのでめっちゃ大変です。本当は、その隣のFIXチャンネルのランプも、予防交換をすればいいとは思うのですが、あまりに大変なので諦めました。切れたら、しかたなく作業します。
LED化して組み上げたら、メインダイヤルのランプが点灯しません。
「オーマイガー!、お前もか!!」
メインダイヤル用のランプは、取り出しやすくなっているので、比較的簡単に交換できます。これも、手持ちのLED電球に交換します。電圧は、DC12Vです。

電球をLED化したので、切れる心配は減りましたが、光量が低下しました。電球は広範囲に光を出しますが、LEDだとどうしても指向性が出てくるので、同じDC12Vでも暗くなってしまいます。そうはいっても、使える範囲なので良しとします。
今回、交換したもの。

---------------------------------------------------------------------------
追記
手持ちの赤LEDに交換してみましたが、いまいち色がしっくりきませんので、手持ちの白色LEDに交換することにします。
ジャンク箱にある取り外し品の小型白色LEDに抵抗を接続して取り付けることにします。

LEDの足は、ショートしないようにホットボンドで固めました。(熱収縮チューブの方がいいとは思う)

実験用電源(以前紹介した、格安中華製電源ユニットを組んだもの)で動作テストを行い、LEDが正常に点灯するのを確認します。

もう、ついでなので、FixCh用のランプも同様に白色LEDに交換します。
さらについでに、Sメーターユニットの電球を確認していたら、いきなりランプが切れました。
「お前もか!!」

思えば、すべての電球が経年劣化のため、いつ切れてもおかしくない状況だったので、少しの振動で引導を渡したものと思われます。
短命で終わった中華製LEDランタンの部品があったので、そのLEDを基板から取り外して使うことにします。

すべてのランプがLED化されましたが、緑っぽい色が、青白っぽい色に変化しました。(メーターは白色)バンドSW、FixChスイッチの照明の光具合はいいのですが、Sメーターユニットの光はLEDの光が直線的になるので、明るさの濃淡がはっきりしてしまいます。ダイヤルの部分はLED化して暗くなってしまいましたので、この2か所は電球の方がいい感じにはなります。写真は撮ってみたのですが、うまく表現できなかったので割愛します。
しかし、LEDは電球に比較して長寿命なので、どちらを選ぶかはお好み次第でしょう。個人的にはダイヤル照明は暗すぎるので、手に入れば12V豆電球に交換しようかなと思います。
---------------------------------------------------------------
さらに追記
LEDではメーターダイヤルが暗すぎて見にくいので、電球に交換しました。ホームセンターに行き、自動車補修部品コーナーで、12Vの豆球を発見しました。元々の電球とは若干形状が異なりますが、口金部分(G14/BA9S)が合えば問題ありません。やはり電球の方が、しっくりきます。
左が今回購入したもので、右は交換したLED電球です。

12V豆球x2個セット:250円(TAX込)
----------------------------------------------------------------
もう一つ追記
メーターランプなんだけど、白色ということと光の濃淡が大きいという理由で、ムギ球に交換しました。12V用のムギ豆球はジャンク箱にあったので、それを使いました。

結論
・メーターとダイヤルは電球が良い。
・バンドスイッチ・固定チャンネルスイッチは、LEDでも良い。
・バンドスイッチ・固定チャンネルのランプ交換は、当初めっちゃ大変と思いましたが、コツをつかむとそれほど苦労しなくても交換できます。
おまけ
バンドスイッチ用LEDですが、他の作業中に振動のためか点灯しなくなりました。このLEDはジャンクの取り外し品のため、素性不明で一応480Ωの抵抗を直列に接続していたのですが、取り外したら壊れてました。(順方向電流が流れない)
再度素性不明のLEDに交換したので安全面を考慮して、480Ω+480Ω=960Ωを直列にして点灯させました。これでも十分に点灯します。
数か月かかって、苦労の末ほぼ初期の性能に戻しましたが、ランプは手つかずにしておいた。というのも、バンドSW、FIXチャンネルSWのランプは前面パネルの奥の方にあり、交換するとなるとちょー大変なのは分かっていたからなのである。
こないだ電源を入れたら、バンドSWのランプが点灯しないのである。オーマイガー! ついに、その日が来てしまいました。ストロボ焚くと、点灯しているか否かは良く分からなくなりますが、バンドSWのみ消灯してます。(この時は、メインダイヤルのランプは点灯している)

ランプ切れだよなぁ。交換するか・・
上部カバー・下部カバーを取り外し、全面パネルの皿ねじ4個を外すと、パネルが前面に倒れます。その、ずっと奥にランプがあるので、ラジオペンチで注意深く取り外します。

交換用のLEDは、手持ちのELEKIT社の赤色LEDを使用します。

ランプは12V用が使われています。LEDは極性があるので、プラス・マイナスを間違えないように接続します。コードなどは現物合わせにして、余分な部分はカットします。
パネル部分は配線が多く、狭いのでめっちゃ大変です。本当は、その隣のFIXチャンネルのランプも、予防交換をすればいいとは思うのですが、あまりに大変なので諦めました。切れたら、しかたなく作業します。
LED化して組み上げたら、メインダイヤルのランプが点灯しません。
「オーマイガー!、お前もか!!」
メインダイヤル用のランプは、取り出しやすくなっているので、比較的簡単に交換できます。これも、手持ちのLED電球に交換します。電圧は、DC12Vです。

電球をLED化したので、切れる心配は減りましたが、光量が低下しました。電球は広範囲に光を出しますが、LEDだとどうしても指向性が出てくるので、同じDC12Vでも暗くなってしまいます。そうはいっても、使える範囲なので良しとします。
今回、交換したもの。

---------------------------------------------------------------------------
追記
手持ちの赤LEDに交換してみましたが、いまいち色がしっくりきませんので、手持ちの白色LEDに交換することにします。
ジャンク箱にある取り外し品の小型白色LEDに抵抗を接続して取り付けることにします。

LEDの足は、ショートしないようにホットボンドで固めました。(熱収縮チューブの方がいいとは思う)

実験用電源(以前紹介した、格安中華製電源ユニットを組んだもの)で動作テストを行い、LEDが正常に点灯するのを確認します。

もう、ついでなので、FixCh用のランプも同様に白色LEDに交換します。
さらについでに、Sメーターユニットの電球を確認していたら、いきなりランプが切れました。
「お前もか!!」

思えば、すべての電球が経年劣化のため、いつ切れてもおかしくない状況だったので、少しの振動で引導を渡したものと思われます。
短命で終わった中華製LEDランタンの部品があったので、そのLEDを基板から取り外して使うことにします。

すべてのランプがLED化されましたが、緑っぽい色が、青白っぽい色に変化しました。(メーターは白色)バンドSW、FixChスイッチの照明の光具合はいいのですが、Sメーターユニットの光はLEDの光が直線的になるので、明るさの濃淡がはっきりしてしまいます。ダイヤルの部分はLED化して暗くなってしまいましたので、この2か所は電球の方がいい感じにはなります。写真は撮ってみたのですが、うまく表現できなかったので割愛します。
しかし、LEDは電球に比較して長寿命なので、どちらを選ぶかはお好み次第でしょう。個人的にはダイヤル照明は暗すぎるので、手に入れば12V豆電球に交換しようかなと思います。
---------------------------------------------------------------
さらに追記
LEDではメーターダイヤルが暗すぎて見にくいので、電球に交換しました。ホームセンターに行き、自動車補修部品コーナーで、12Vの豆球を発見しました。元々の電球とは若干形状が異なりますが、口金部分(G14/BA9S)が合えば問題ありません。やはり電球の方が、しっくりきます。
左が今回購入したもので、右は交換したLED電球です。

12V豆球x2個セット:250円(TAX込)
----------------------------------------------------------------
もう一つ追記
メーターランプなんだけど、白色ということと光の濃淡が大きいという理由で、ムギ球に交換しました。12V用のムギ豆球はジャンク箱にあったので、それを使いました。

結論
・メーターとダイヤルは電球が良い。
・バンドスイッチ・固定チャンネルスイッチは、LEDでも良い。
・バンドスイッチ・固定チャンネルのランプ交換は、当初めっちゃ大変と思いましたが、コツをつかむとそれほど苦労しなくても交換できます。
おまけ
バンドスイッチ用LEDですが、他の作業中に振動のためか点灯しなくなりました。このLEDはジャンクの取り外し品のため、素性不明で一応480Ωの抵抗を直列に接続していたのですが、取り外したら壊れてました。(順方向電流が流れない)
再度素性不明のLEDに交換したので安全面を考慮して、480Ω+480Ω=960Ωを直列にして点灯させました。これでも十分に点灯します。










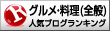















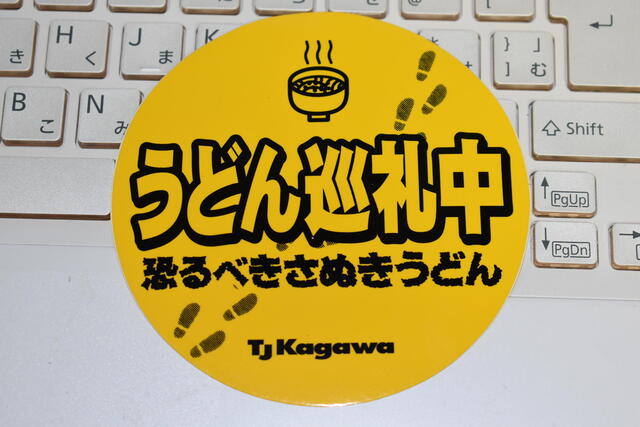

TRIOブランドですね。
KENWOODブランドでもトリオ時代の葉っぱマークの付いた古いロゴの物も多かった時代かな?とも思いました。
(このロゴはどちらかというと北米向けに多い)
それにしてもちょっと見ただけで配線の多い事、多い事。
私が固定機の職場にいた時も固定機だからある程度配線が多いのはやむ負えないと思っていたのですが、工場サイドから言わせれば理由にならない、多すぎ!と散々怒られた記憶があります。品質保証部やサービスからは故障増加が懸念されました。
配線を少なくするには、
1、回路ブロックを徹底的に集約して大きなプリント板を使う。
2、FPC(フレキシブルプリント配線板)を使う。
などがあります。
でも「1、」は工場からダメ!と言われます。理由は大きなプリント板は半田槽に入れた時に熱で反りやすいので、半田付けの前に長辺方向に手作業で「反り防止金具」というものを付ける必要があるのです。
(片面リフロー、片面ディップ半田の場合)
両面リフローの基板も大型は「チップ部品が熱ストレスで割れやすくなる」と怒られます。
でもユニットごとに小分けのプリント板にすると大きな1枚の板から割り取って使うので「作業工数がかかる」と怒られます。
FPCは工場からは作業性悪すぎなので使わないでほしい、ハンディも止めてほしいと言われ、商品企画や営業からはコストが合わなくなるからダメと怒られました。
固定機、大型機は踏んだり蹴ったりでこれは今も同じです。
それとLEDはやはり夢の光源ではありませんね。照らすという部分は丸でダメです。
単なる1つのインジケータでも中心が妙に明るくて違和感を感じることもあります。
でも寿命と低消費電力は魅力ですが。
ムギ球ってもう市場在庫だけなんでしょうかね?
TS-600メンテお疲れ様
まだ動いてるある=すごいですねー
😄😄😄
デザインも良く、今でも見劣りしないリグだと思います。まさに、名機といってもいいと思います。
LEDはいいところが多いのですが、おっしゃるように光がスポット的に出るので、メーター部分には不向きと思いました。複数個にして、光を分散したらいいのかもしれませんが、めんどいので電球に戻しました。ムギ玉は簡単に手に入るので、まだ製造しているのではないでしょうか?なくなれば、それはそれで困ってしまいますが、市場は小さいのでしょうね。
ちょうど台風14号の目に入っていて無風状態です。なんか不気味ですが、もうすぐ吹き返しが発生すると思います。いまのところ、空中線は無事ですが、以前は吹き返しでやられたので気は抜けません。
固定機、モービル、リニアなどの配線がたくさんある機種の「配線の設計」は大変です。
「設計」と言っても実際のコードをケース内に這いまわして余裕は適正か?多すぎないか?などを決めてOKだったら定規で長さを測るのです。
ワイヤーハーネスというやつですが、途中で分岐するものはそれも含めて寸法を決めていきます。計算で求めることは皆無です。自作のセットと同じですね。
そしてOKの長さが出たらそれを図面にしてワイヤーハーネスメーカーに試作発注します。
でも出来て来ると「ここは短くて電線が切れそう」とか「長すぎてコスト無駄。ノイズも拾う」など問題が出て来ます。
これらをプリプロまでに修正するのです。私は担当したことがありませんが、悪しき習慣でその年の新卒によくやらせてトラブっていました。
でも無線機であれほど大変だったと思うと自動車や飛行機、鉄道などだったらどうなる事やら、と心配してしまいます。
まあ誰かがやらなくてはいけませんが、新卒にやらせるにしても電子工学を出た人間の仕事ではありませんね。
今のセットは基板の集積度が上がり、チップ部品が大量に使用されていますが、昔のアナログ回路は大きな部品が多く、基板をつなぐワイヤーが鬼のようにあり、設計も大変だったということが良く分かりました。