人物伝 発明王エジソンはなぜ成功したのか 「成功すべくして成功するには、やはり根性、根気が要る」 今の時代にこそ「運・鈍・根」が必要である
2025.02.17(liverty web)
<picture> </picture>
</picture>
トーマス・エジソン(1847~1931年)は、電話や白熱電球、直流発電機、蓄音機、映画等、生涯に約千三百もの発明や、改良を行った「発明王」として知られる。(イラスト:水谷嘉孝)
発明王のトーマス・エジソンは1914年、研究所として使っていた工場が火事で全焼し、ほぼすべての実験道具や資料などを失ったとき、こう語った。
「これでまたゼロから研究ができる」──。
この時、エジソンは67歳という年齢であったというから驚きである。
本誌3月号記事「エジソンと大平正芳から『「運・鈍・根」の仕事成功学』を学ぶ」では、「1%のインスピレーション」を得るためにエジソンが重ねた努力と、人並み外れた根気について紹介した。
本欄では、エジソンの「考え方」をさらに深掘りすることで、私たちが学べることについて考えてみたい。
「何に挑戦すべきか」を考え抜いたからこそ、失敗してもあきらめずに挑戦し続けられた
後世において、エジソンは、「どれだけ失敗しても諦めなかった偉人」として紹介されることが多い。
冒頭の火事のエピソードのように、それは事実だが、その歩みを丹念に追ってみると、発明に取り組む前の段階で、「何に挑戦すべきか」を考え抜いていたことが分かってくる。
「その発明にどれだけの意義があるか」「その発明は成功させられるか」ということについて考えを詰めていき、「この発明は人々のために必要である」「実現は可能だ」という確信を得ていたからこそ、どれだけ失敗しても、「うまくいかない方法を見つけただけ」と言って、諦めることなく挑戦を続けることができた。
例えば、白熱電球の実用化に挑戦していた頃、エジソンは、この発明が人類にもたらす影響が絶大なものになると確信していた。当時、用いられていたガス灯とアーク灯は重大な欠陥を抱えていたからだ。
街路灯として多く用いられていたガス灯は値段が高く、爆発の危険性もあった。室内で用いると壁が黒ずむだけでなく、酸素を燃やすため、頭痛やめまいに苦しむ人も出てくる。知らぬ間にガス漏れが起きるリスクもあった。
それよりも明るい光を放つアーク灯への期待感が高まっていたが、アーク灯は2本の炭素棒の先端で放電させて発光する仕組みで、炭素棒の強度が低く、燃え尽きてしまうため、寿命が短いという欠点があった。さらに、光量の調節ができず、明るすぎ、最後には燃えさしが飛び散るので室内の使用には適さなかった。
つまり、廉価な白熱電球を普及させれば、誰でも室内で安全な明かりを灯し、夜にも仕事をはじめ様々な活動ができるようになる。その経済効果は、計り知れない規模になることが見込まれていた。
エジソンは1878年にアメリカ西部を旅した際に、とある工場で、発電機を用いて8基の小型アーク灯に光を灯す実験を見学した後、フィラメント(電灯の芯)を用いて多くの白熱電球を灯すアイデアを公表した。










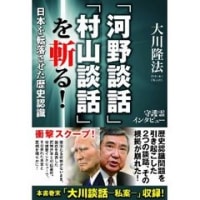






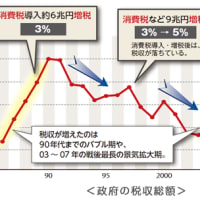
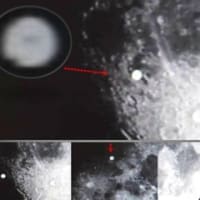
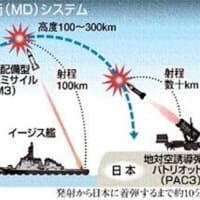

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます