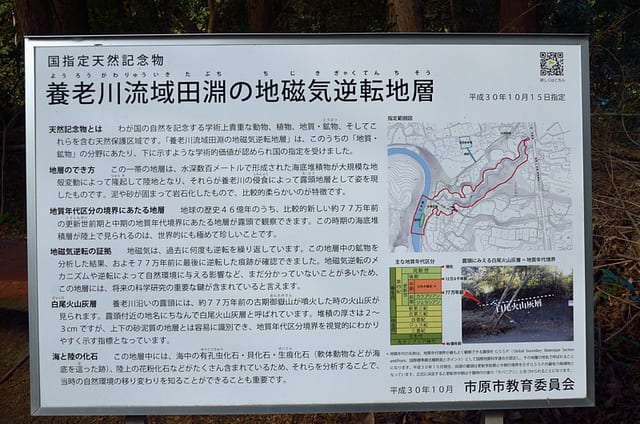千葉県いすみ市大東埼灯台
大東埼(または大東崎・大東岬):海抜58mの断崖上に
1950年に設置された高さ16mの白亜の塔が立つ。
この灯台の光は21海里(28km)まで届くという。
「大東埼燈台クラブ(千葉県NPO)」のメンバーが
ボランティア活動で土・日には欠かさず売店を出し
清掃、花壇の世話、お盆フェスタなどで活動している。

白亜の美しい灯台が豊かな緑に包まれてまぶしく見える。
太平洋の荒波が押し寄せる断崖上にはベンチも整備され
果てしない海原を見渡しながら休むことができる。
また町の灯りも届かないこの岬の上は北から南まで広がる
大空の星座や銀河など、また朝日の出などの撮影ポイント
としても人気があり、写真愛好家も多く訪れる。

南方を見渡すと、いすみ市大原海岸八幡岬までの砂浜が続く。

千葉県(房総半島)の地図で見ると
右上の旭市「刑部岬」からきれいな曲線が南に伸びている。
この間は「九十九里浜」の約66㎞もの砂浜が続いている。
曲線の南端のすこし膨らんだ位置に「大東岬」がある。
房総半島南端の左下南房総白浜には「野島崎灯台」がある。
「大東岬」は「刑部岬」と「野島崎」のほぼ中間にある。
刑部岬から、房総南端の白浜野島崎まで海辺を車で走ると
100㎞をはるかに超える距離があることがわかる。

大東岬頂上付近には駐車場やトイレも整備されている。
建物壁面に房総の天才宮彫師「波の伊八」案内ボードがある。
岬の高台から狭いながらもよく整備された舗装道を下ると
すぐ近くに「飯縄寺(いづなでら)」がある。
その寺では「宮彫師 伊八」の作品を鑑賞することができる。
「波を彫っては天下一」と称された伊八の傑作である
見事な波の彫刻(実物)も目の当たりに鑑賞できる。
この寺には「浪と飛龍」「牛若丸と大天狗」作品がある。
更に同じ市内の「行元寺」には「浪に宝珠」がある。
葛飾北斎の「富嶽三十六景」中の「神奈川沖浪裏」作品と
伊八の荒波を彫った「浪に宝珠」はとてもよく似ている。
伊八の「浪に宝珠」の彫刻では、荒波の中央の位置に
「宝珠」が彫られている。
北斎の「神奈川沖浪裏」は宝珠の位置に富士山がある。
上の案内ボードの図でもわかるように
両者の作品の荒波逆巻く構図は瓜二つといわれている。
南房総で生まれた天才宮彫師波の伊八が葛飾北斎に
大きな影響を与えたことは、いすみ市の二つの寺を
訪ねただけでも十分に理解することができる。
また北斎が房総へ三度旅をしたことも記録に残っている。
そしてその北斎の作品は広く世界に知れ渡り
ゴーギャン、ゴッホ、セザンヌ、モネなど
印象派の多くの画家たちに影響を及ぼした。
房総半島太平洋岸中ほどの海辺を訪ねる小さな旅でも
さわやかな空気と果てしない海、そして星空と日の出
更に驚くほどの感動的出会いを楽しむことができる。
【参考】:「波の伊八」に関する上記以外の施設
*波の伊八生誕地:鴨川市打墨(屋敷・工房跡見学)
大山寺:鴨川市平塚(作品鑑賞)
金乗院:鴨川市打墨( 同 )
石堂寺:南房総市石堂( 同 )
真野寺:南房総市久保( 同 )
長福寺:いすみ市下布施( 同 )
光福寺:いすみ市大野( 同 )
*ほかにも多くの寺院などで波の伊八の作品を鑑賞できる
寺や施設があります。