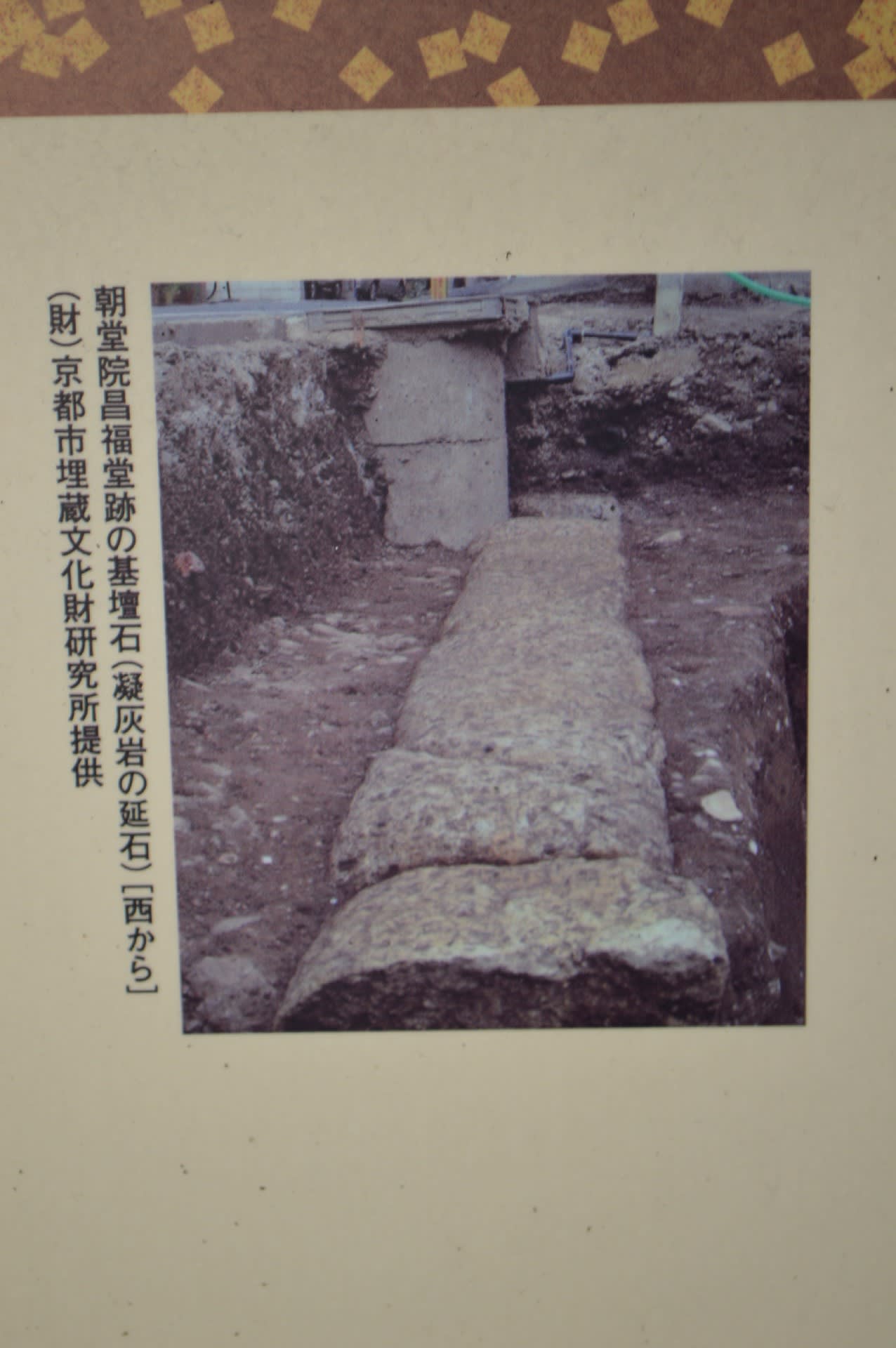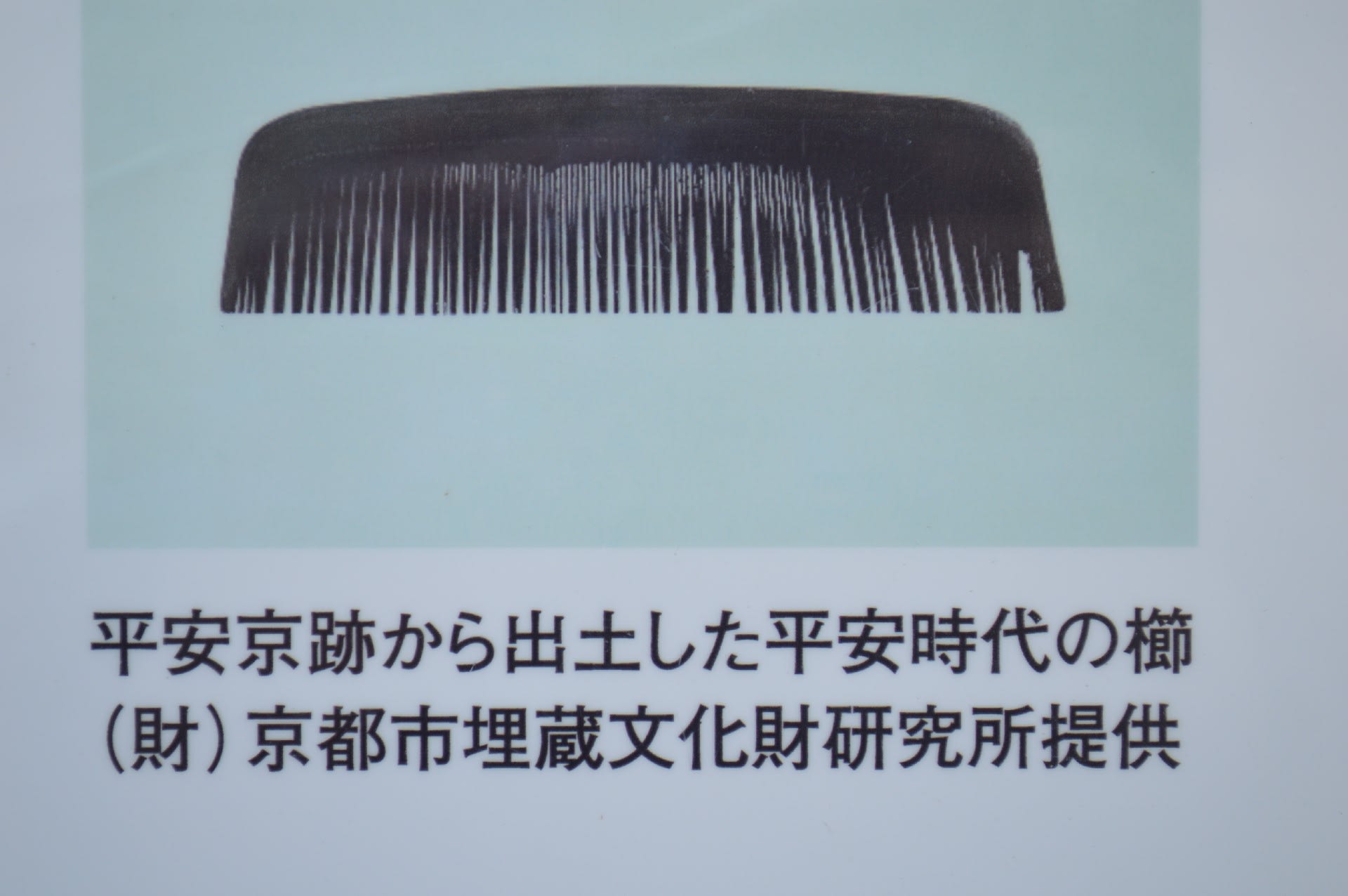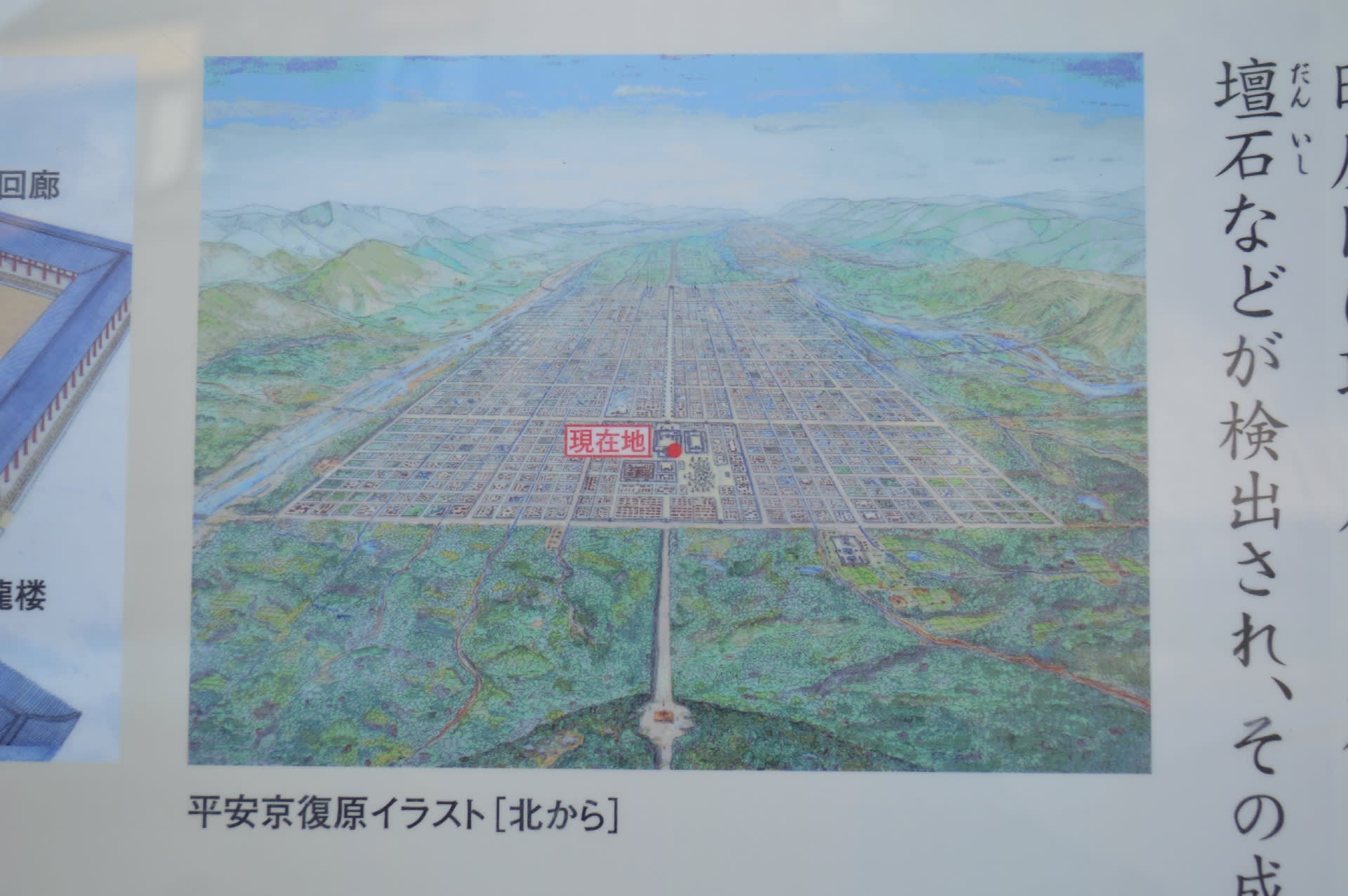『平家物語』によると,近衛天皇(1139~55)の代,毎夜黒雲が立ち込めて御所を覆い,天皇を怯えさせていた。源頼政(1104~80)が,怪しい姿を発見し弓矢で射殺したところ,頭は猿,胴体は狸,尾は蛇,手足は虎,鳴き声がトラツグミ,という怪鳥鵺(ぬえ)であった。この碑は,鵺退治で使用した矢の鏃を頼政が洗ったと伝承される池跡を示すものである。なお,元禄13(1700)年に建てられた原碑が摩滅し,現在では北面の題額部に「鵺池碑」の3字が確認できるだけなので,昭和11(1936)年に復元碑が公園の北に隣接する鵺大明神社内に建てられた。碑文は復元碑による。

鵺池碑

元禄13年(復原碑1936年)
建立者 太田毎資(復原碑出水学区有志)
我源朝臣松平紀伊君在京之日家臣太田毎資亦来居焉其宅後有
一池曰鵺池俗伝以為頼政卿嘗滌射鵺鏃之地矣今毎資者道潅七
世之孫而頼政卿遠裔也故聞斯事喜適居其地且懼其就泯減因使
予録其事上石鳴呼追遠之心不亦美乎遂書銘曰
怪鳥当射 志不可敵 休矣邦彦 其声太逖
元禄庚辰三月望日 松崎正祐記
鵺池碑 碑文の大意
わたし(筆者松崎正祐)の主君であるは丹波篠山藩主松平紀伊守が京都所司代に任じられ京都に赴任していたとき,家臣の太田毎資もまた主君に従い京都に滞在していた。毎資の官舎の庭に池があり,鵺池と呼ばれていた。源頼政卿がかつて鵺を射た矢じりを洗った地だと伝えられていた。
実は毎資は太田道灌の七世の孫で,頼政卿の末裔である。だからその地に居をかまえた事をたいへん喜んだ。それだけではなく,この池の伝承が消え失せることを心配し,石碑を建ててわたしに碑文を書かせた。なんと美しい先祖を思う心情ではないか。この碑文は以上のような次第で書いたものである。(以上原碑の碑文)
この地は昔から鵺池と呼ばれていた。池のほとりに碑がある。しかし徳川氏の世になり京都所司代屋敷の中に取り込まれてしまった。だからその当時出版された京都ガイドブックの類には記されていない。
明治の初めに所司代屋敷跡に監獄が置かれた。それでもなお碑は大切に保存された。ただし雨風にうたれ文字は次第にすり減って見えなくなった。昭和2(1927)年に京都監あらため京都刑務所が山科に移転し,昭和9年,跡地に二条公園が設けられた。そのころにはまったく碑文が読めなくなっていたので,心ある人は残念に思っていた。
ところが元看守長青山咸懐氏という人がいて,在職時に原文を写していた。かすかに残る碑文の跡と青山氏が写した碑文の二つを総合したら碑文がはじめて明らかとなった。そこで有志が相談し,もとの碑とは別に新しい碑を建てて碑文を刻み,後世に伝えるものである。(以上昭和11年復元時の碑文)

此地古来称鵺池池辺有碑詳誌其伝説而及徳川氏執政柄地属所
司代之邸内以故当時所刊行名所誌之類或憚而不記焉維新之初
就邸址而置監獄猶用意於保存但碑石則風餐雨虐文字漸磨滅後
撤獄舎昭和九年新設二条公園之比至不可復読有志以為恨也偶
有元看守長青山咸懐氏在職之間手記原文両者相対照而主文始
歴如恨事乃除矣於是有志相謀更選碑石刻之以伝後世云爾
昭和十一年三月望日 出水学区建碑有志



関連記事 ⇒ 神社下0033 神明神社 鵺退治の矢じりがあります 綾小路東洞院
前回の記事 ⇒ 祠北042 岩倉川 十王堂橋 付近 の草に覆われた祠
下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます