「留学生100万人計画:第2次報告に盛る方向 再生会議」という記事がインターネットの毎日新聞に出ていました。
「具体的方策として」挙げられていることを整理してみます。
① 学部への留学を容易にするため、海外の大学で取得した単位を日本の大学でも認める制度の拡充を提唱。
ふむ。これは、いいかも。ただし、博士号の話に限定せず、いわゆるディプロマミルには警戒しておきたいものです。単位互換制度を国レベルで規定してくれると、やりやすいでしょうね。でも実際には、科目名、科目の扱う範囲などのすりあわせが単純じゃないような気がします。
②日本貿易振興機構など複数の機関が行う外国人への日本語検定の一元化も検討する。
ふむ。これも確かにね、複雑だとやっかいではありますね。ただし、ここでは「外国人」とひとくくりにしてありますが、上級レベル以上は、目的別のテストを用意してもいいかと思います。でもねえ、テストを準備するところが独占状態になるというのは、あんまりいい状態じゃないような気がしますよ。どういった内容が話されているのか、表に出ていないから、これ以上、コメントのしようがないんですが。
③各大学に英語による授業の実施や留学生宿舎の整備を呼びかける。
英語による授業の実施ですか。大学の教員がみんな英語で全ての専門が伝えられる状態ではないのですよ。いや、教員も自分の専門で必要な語学力はあるんですけどね、それが「英語」に限定されると、全員じゃない、ということですよ。確かに、専門の分野になればなるほど、必要な語彙は限定されてきますからね。
でも、授業はともかく、大学の教室を一歩出たら、日本語だけの世界ですよ。大学から一歩も出ないで衣食住、娯楽も完備するつもりであればなんとかなるでしょうが。でも、日本の地域の方との日常的な交流はまず進まないでしょうね。英語を始め、それぞれの語学好きの方に限定された交流になりそう。
100万人留学生を受け入れて、帰国後、日本についてよく分からない、という留学生を生み出すことには抵抗があります。
ゼロレベルで、6か月、毎日5時間近く授業をして初級が終わって、ようやく日本語で最低限の生活ができるんです。日本語教育の期間を無駄だと思わず、最初に6ヶ月間、義務づける方向で行った方がいいと思いますが、どうでしょうか。来日前でもいいですけど。
学生宿舎については、お金の問題だけじゃありません。
徳島大学は、これまでも留学生の宿舎建設地選定に絡んで、地域との摩擦が少なからずありました。100万人の留学生を受け入れることを前提に宿舎を建て増すのであれば、最初は数割程度しか入居する可能性のない建物類を建てていくことになります。これまでは、そんなことが許されませんでしたが、OKになるのかしら。宿舎については、留学生の宿舎賃貸時の保証人の話も解決しそうなので、大歓迎です。
④ 奨学金支給など予算面での支援も必要となるため、再生会議は、高等教育への財政支出を国内総生産(GDP)比で現在の0・5%から各国並みの1%に引き上げることも検討する
う~ん。国費留学生を増やすのかな。そうするのであれば、額は今の半額程度でいいので、より多くの学生が受給できるようにして欲しいです。日本人学生の受ける奨学金は受給ではなく貸与ですよね。日本人学生の方が経済的に大変、ということも見受けられます。いっそのこと、授業料は無償として、大学生には全員一律で生活費を支給してはどうでしょう。防衛大学のように。
高等教育の財政支出を増やすというのは、いいことだと思います。財源はどうするのか、この記事からでは分かりませんが。
留学生を増やすのは構いませんが、受け入れ側の体制ができないうちにスタートするのは止めて欲しいなと言うのが正直な感想です。
体制ができていないところへ留学してくる学生も、そこで学ぶ日本の学生も、地域の方も、大学の教職員も、いやな思いだけするような気がしますから。せっかくの留学です。知日派、親日派を作る、という視点で行きたいですね。
「具体的方策として」挙げられていることを整理してみます。
① 学部への留学を容易にするため、海外の大学で取得した単位を日本の大学でも認める制度の拡充を提唱。
ふむ。これは、いいかも。ただし、博士号の話に限定せず、いわゆるディプロマミルには警戒しておきたいものです。単位互換制度を国レベルで規定してくれると、やりやすいでしょうね。でも実際には、科目名、科目の扱う範囲などのすりあわせが単純じゃないような気がします。
②日本貿易振興機構など複数の機関が行う外国人への日本語検定の一元化も検討する。
ふむ。これも確かにね、複雑だとやっかいではありますね。ただし、ここでは「外国人」とひとくくりにしてありますが、上級レベル以上は、目的別のテストを用意してもいいかと思います。でもねえ、テストを準備するところが独占状態になるというのは、あんまりいい状態じゃないような気がしますよ。どういった内容が話されているのか、表に出ていないから、これ以上、コメントのしようがないんですが。
③各大学に英語による授業の実施や留学生宿舎の整備を呼びかける。
英語による授業の実施ですか。大学の教員がみんな英語で全ての専門が伝えられる状態ではないのですよ。いや、教員も自分の専門で必要な語学力はあるんですけどね、それが「英語」に限定されると、全員じゃない、ということですよ。確かに、専門の分野になればなるほど、必要な語彙は限定されてきますからね。
でも、授業はともかく、大学の教室を一歩出たら、日本語だけの世界ですよ。大学から一歩も出ないで衣食住、娯楽も完備するつもりであればなんとかなるでしょうが。でも、日本の地域の方との日常的な交流はまず進まないでしょうね。英語を始め、それぞれの語学好きの方に限定された交流になりそう。
100万人留学生を受け入れて、帰国後、日本についてよく分からない、という留学生を生み出すことには抵抗があります。
ゼロレベルで、6か月、毎日5時間近く授業をして初級が終わって、ようやく日本語で最低限の生活ができるんです。日本語教育の期間を無駄だと思わず、最初に6ヶ月間、義務づける方向で行った方がいいと思いますが、どうでしょうか。来日前でもいいですけど。
学生宿舎については、お金の問題だけじゃありません。
徳島大学は、これまでも留学生の宿舎建設地選定に絡んで、地域との摩擦が少なからずありました。100万人の留学生を受け入れることを前提に宿舎を建て増すのであれば、最初は数割程度しか入居する可能性のない建物類を建てていくことになります。これまでは、そんなことが許されませんでしたが、OKになるのかしら。宿舎については、留学生の宿舎賃貸時の保証人の話も解決しそうなので、大歓迎です。
④ 奨学金支給など予算面での支援も必要となるため、再生会議は、高等教育への財政支出を国内総生産(GDP)比で現在の0・5%から各国並みの1%に引き上げることも検討する
う~ん。国費留学生を増やすのかな。そうするのであれば、額は今の半額程度でいいので、より多くの学生が受給できるようにして欲しいです。日本人学生の受ける奨学金は受給ではなく貸与ですよね。日本人学生の方が経済的に大変、ということも見受けられます。いっそのこと、授業料は無償として、大学生には全員一律で生活費を支給してはどうでしょう。防衛大学のように。
高等教育の財政支出を増やすというのは、いいことだと思います。財源はどうするのか、この記事からでは分かりませんが。
留学生を増やすのは構いませんが、受け入れ側の体制ができないうちにスタートするのは止めて欲しいなと言うのが正直な感想です。
体制ができていないところへ留学してくる学生も、そこで学ぶ日本の学生も、地域の方も、大学の教職員も、いやな思いだけするような気がしますから。せっかくの留学です。知日派、親日派を作る、という視点で行きたいですね。










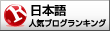

















ところで、科研採択の由、おめでとうございます。昨秋このブログで幸運を祈っていただいたおかげで、私も吉報をもらえました。身の引き締まる思いです(なんて、政治家みたい)。
卒業後、留学生をどう生かしていくのかという視点が欠けているのが気になってなりません。
例えば、医学部、歯学部、薬学部で勉強して帰国する留学生には、大学や国が「日本語で大丈夫です」と日本語で書かれている金属製の立派なプレートを送るんですよ、帰国後自分のクリニックの入り口に掲げてもらえるように。で、『地球の歩き方』や、外務省のホームページでもいいです、日本語で大丈夫な病院というリストを作っていくんですよ。教員になる学生であれば、この国のこの町には日本語が分かる教員が○○名います、とかいう情報をね、どこかで持っておくべきなんです。
話が逸れましたが、呼ぶだけではなくて、その人材を日本のためにどう使うのかという戦略がほしいところです。国民の税金で奨学金制度を維持している以上。
ま、そんなこんなで、いろいろと考えさせられます。
それはそうと、科研、おめでとうございます。
私も研究分担者になっている科研が今までもあったのですが、今回また一つ決まり、忙しくなりそうです。
またお目にかかったとき、色々と教えてください。