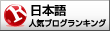成績をつけながら、学生さんの何人かが、最終課題を提出するメールに授業のコメントを付けてくれているのを読むと、新しい知識を得たことに対する喜びというか、感動というか、そんなものが書かれていることがある。それが、教員に対する「おだて」であっても、うれしいもの。
本来、学ぶ、ということは、うれしくて楽しいことのはず。
僕は、はるどんが幼稚園に通い始めるころから、毎日、広告の裏やらいらなくなった紙の裏に、はるどんあての手紙を書いてました。
お父ちゃんの出勤が、はるどんの起きる時間より早かったから。内容は、そんなに大層なことじゃなくて、
「お母さんと、楽しく遊んでね」とか、
「帰ったら、絵本を読むから、選んでおいてね」とか、
「今日は、いっぱい遊ぼうね」とか、
「折り紙を一緒にしようね」とか、そんなもの。全部ひらがなで。
最初は、はるどん、ひらがなは読めなかったから、お母ちゃんが読んで聞かせてたのね。
紙に書かれた文字、きっと不思議だっただろうなあ。
そのうち、返事がかかれるようになりました。ペンやクレヨンで、〇がいくつも書いてあって、はるどんは、自分の言葉をその「〇」で書いてくれてたのね。
そして、ひらがなが拾い読みできるようになってからは、毎朝のお父ちゃんの手紙が、突然、意味のあるものに変わってきたのね。
初めて読めた日は、机の上の紙が目に入るたびに、声を出して読み上げてた、と妻に聞きました。
すごく、すごく、嬉しそうに、何度も何度も。
学ぶ、ということはこういうことなんだ、というのをその時に再認識しました。
まなぶことは、視野を広げること、とても楽しくて、とてもうれしくて、わくわくすること。
自分が教壇に立つようになって、目の前の学生さんにどれだけそんな思いで学んでもらえているのか。
自分が学ぶことの楽しさを実感させられているのか、そんなことをよく考えます。
思えば、ハングルが読めるようになったときも同じだったかな。記号でしかなかったものに、命が宿り、それを書いた人の息遣いが聞こえてくるような。
今日、はるどんと町内会の掃除に行って、はるどんのほうから「私も手伝いに行く」といってくれたのがうれしくて、こんな話を思い出しました。
本来、学ぶ、ということは、うれしくて楽しいことのはず。
僕は、はるどんが幼稚園に通い始めるころから、毎日、広告の裏やらいらなくなった紙の裏に、はるどんあての手紙を書いてました。
お父ちゃんの出勤が、はるどんの起きる時間より早かったから。内容は、そんなに大層なことじゃなくて、
「お母さんと、楽しく遊んでね」とか、
「帰ったら、絵本を読むから、選んでおいてね」とか、
「今日は、いっぱい遊ぼうね」とか、
「折り紙を一緒にしようね」とか、そんなもの。全部ひらがなで。
最初は、はるどん、ひらがなは読めなかったから、お母ちゃんが読んで聞かせてたのね。
紙に書かれた文字、きっと不思議だっただろうなあ。
そのうち、返事がかかれるようになりました。ペンやクレヨンで、〇がいくつも書いてあって、はるどんは、自分の言葉をその「〇」で書いてくれてたのね。
そして、ひらがなが拾い読みできるようになってからは、毎朝のお父ちゃんの手紙が、突然、意味のあるものに変わってきたのね。
初めて読めた日は、机の上の紙が目に入るたびに、声を出して読み上げてた、と妻に聞きました。
すごく、すごく、嬉しそうに、何度も何度も。
学ぶ、ということはこういうことなんだ、というのをその時に再認識しました。
まなぶことは、視野を広げること、とても楽しくて、とてもうれしくて、わくわくすること。
自分が教壇に立つようになって、目の前の学生さんにどれだけそんな思いで学んでもらえているのか。
自分が学ぶことの楽しさを実感させられているのか、そんなことをよく考えます。
思えば、ハングルが読めるようになったときも同じだったかな。記号でしかなかったものに、命が宿り、それを書いた人の息遣いが聞こえてくるような。
今日、はるどんと町内会の掃除に行って、はるどんのほうから「私も手伝いに行く」といってくれたのがうれしくて、こんな話を思い出しました。