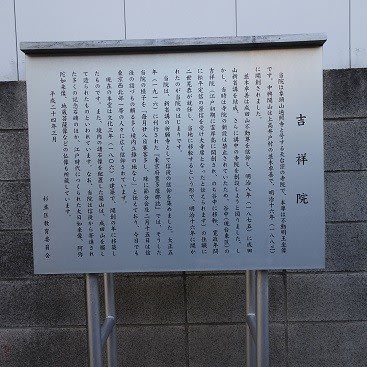こちらの駅へ降りました。

大きく見えますね、西武線の要でもある所沢駅です。さぁ、出発です。


西武バス銀座二丁目バス停とあります、あれっ、銀座へ来ちゃったのかな?

おっと、バスでやって来たのはここ法華寺というお寺でした。このお寺は、調べたところ日蓮宗系のお寺で、明治26年に鬼子母神の教会場として発足、昭和27年に法華寺として一寺と成ったといいます。明治初年に所沢の有志たちによってつくられた法華経信仰の講社の教会場として発足して、当初からお曼荼羅を本尊とし、鬼子母神様が守り本尊として勧請されておりました。当時は「南原(みなみっぱら)の鬼子母神様(きしもじんさま)」として親しまれておりました。その後、明治29年には千葉県中山の法華経寺(日蓮宗大本山)から法華経寺の守り本尊としての子母尊神の御分身をいただき、共に安置されて現在に至っております。当時の記録では、明治29年の世話人は12名、信徒は120名となっております。
第2次世界大戦前までは、信者は所沢町を中心として、川越、三芳、東久留米、東村山、立川、秋川、八王子、入間川、飯能の各方面におり、その数は当時の下足札の数2,000余枚から推測しても大変なものでありました。講社は戦後消滅してしまいましたが、昭和27年には長谷川存佑師が住職となり(現住職は長谷川康榮)、昭和29年には現在の(単立)宗教法人法華寺が発足しました。法華寺は、法華経を所依の教典とし日蓮聖人尊定の大曼荼羅を本尊として、信者を教化育成し、立正安国の聖業に精進することを目的として諸宗教活動を行っております。とのことでした。さて、次へと向かいましょう。

ここは、所沢第一文化幼稚園という場所だそうです。何やら趣のある石像が立ってますね。

少し行くと、これは何でしょう?

立札がありました。「弘法の三ツ井戸」とあります。井戸だったんですね、立札の内容は、「武蔵野台地の中央部に位置する所沢は、地下水位が深いため、昭和12年に上水道がひかれるまでは、大変水利の悪いところでした。近隣の村では「所沢の火事は土で消す」という言葉もあったそうです。そんな水に苦労した所沢にあって、次のような伝説が残されています。 夏のある日、1人の僧が民家に立ち寄り一杯の水を所望しました。そこで機を織っていた娘は、水を汲みに行きましたが、なかなか戻ってきません。不思議に思った僧は、帰ってきた娘にその訳を尋ねました。すると娘は、このあたりが昔から水に不便なこと、井戸まで遠くて苦労していることを語りました。それを聞いた僧は、立ち去る前に娘に三つの場所を杖で指し示し、そこに井戸を掘るようにと言い残していきました。半信半疑ながらも村人達がそこの場所を掘ると、深く掘ることもなく清らかな水がこんこんと湧き出しました。夏でも涸れることのないその井戸を、村人たちは「三ツ井戸」と呼び、誰言うともなくあの僧は弘法大師だという話が広まりました。」という歴史ある井戸だったようです。先ほど見たのは、その碑でした。
つづく