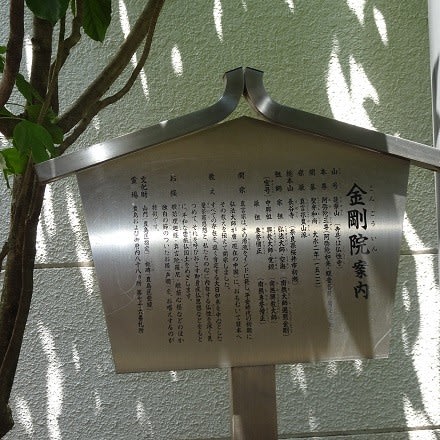大泉学園へと向かったのは、ここへ行きたかったのです。

こことは、東京都練馬区東大泉にある都市公園(植物園)区立牧野記念庭園でした。さぁ、入りましょう。

丁度、アジサイの時期できれいに咲いてます。

こんなきれいなガクアジサイもありましたよ。

おやおや、何でここに郵便ポスト表示があるのでしょう? じつは敷石を見てください。この丸い敷石は、ポストの下にあった石を活用しているんですね。それで、この説明版があったのだ。

今度は、木の下でこんな像がニコニコ笑ってお迎えしてくれました。七福神の布袋尊像かな?

こんな見事な竹林もあります。ところで、練馬区立牧野記念庭園は1958年(昭和33年)に植物学者牧野富太郎の練馬区東大泉の自宅跡に、氏の業績を顕彰する庭園及び記念館として開園したのだそうです。2009年には、国の登録記念物(遺跡及び名勝地)に登録されました。2020年に東京都の名勝及び史跡に指定され、2023年には国の登録記念物は登録が抹消されています。園内には300種近い植物があり、牧野博士が命名したセンダイヤザクラや仙台で発見し亡き妻の名をつけたスエコザサ等が植えられています。現在は、牧野博士の次女・鶴代の孫である一浡(かずおき)が2010年より学芸員として運営に携わっているとのことです。
つづく