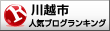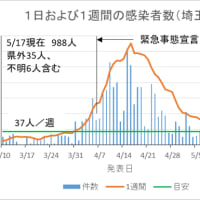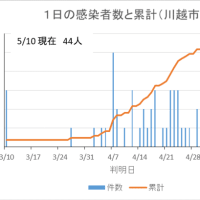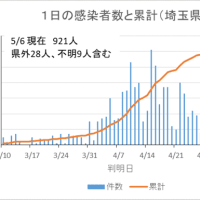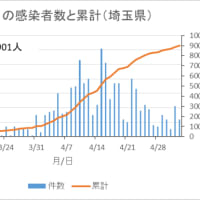大相撲秋場所は、昨日の時点で2敗が4人、3敗が3人と、優勝争いは混沌としている。
相撲好きというほどではないが、ついテレビを見てしまう。
個性的な力士が好きだが、やはり、埼玉県出身の関取の勝敗は気になる。
大栄翔、北勝富士は、ともに4勝7敗と後がないが、なんとか勝ち越して欲しい。
この2力士とも埼玉栄高校の出身だが、他にも同校出身力士が多く、先輩後輩の対決は見ていて楽しい。
大関貴景勝も埼玉栄高校出身で、優勝争いの先頭を並走している。
同じく優勝と大関取りに挑んでいる正代は、いま、非常に気になる存在である。
少し前だが、『武家の棟梁の条件』(野口実 中公新書)を読んでいると、つぎのような記述があった。
「武蔵七党一つである児玉党のながれに、小代氏という小武士団があった。もともと、この家は現在の埼玉県東松山市正代のあたりを本領にしていたのだが、鎌倉時代末期には東国を遥かに離れた肥後国野原荘(現在の熊本県荒尾市・玉名郡長洲町周辺)を根拠地にしていた。」
かなり簡単な記事だが、正代関は熊本県出身なので、何か関連があるのかも知れないと思った。
さらに詳しい資料はないかと、他の本を見ると、
『武蔵の武士団』(安田元久 有麟新書)に、関連する記事を見つけた。
「浅羽氏の祖行業の弟遠広は入間郡小代(勝代)郷に居住し、小代二郎大夫と称した。これが小代氏の祖という。その本拠地の小代郷は、いまの東松山市の東南地区にある正代である。
現在、この地にある青蓮寺及び御霊神社(悪源太義平を祀る)の地域が、小代氏の館跡と伝えるが、ここは比企丘陵の尾根の一つが東にのびた山鼻の平野地に接しようとする突端部で、その東には都幾川と越辺川にはさまれた沃野が、この両河の合流点にまで広がるという景観をもつ地域である。一見して中世武士=在地領主の館跡にふさわしい地形と判断できる、小代氏の故地であることは疑いない。」
東松山市正代の地図を見ると、「小代館跡」と「御霊神社」の表示がある。「青蓮寺」は、この2つの少し北にある。

川越からは、直線で約11.5㎞と、それほど離れてはいない。

さらに、『武蔵の武士団』には、次のように書いてある。
「そして『小代文書』の中に、宝治元年(1247)六月二十三日の地頭職補任状があり、それによると、平内右衛門尉重俊が、子息重康の忠により、肥後国玉名郡の野原庄の地頭になったことがわかる。」
「そして、蒙古襲来に際し、幕府は西国に所領をもつ御家人に対し、それぞれの所領に下向すべきことを命じたが、野原庄内の浄業寺『小代文書』の文永八年九月十三日の関東御教書では、「速かに肥後国所領に下向し、異国の防禦をすべし」と「小代右衛門尉子息等」に命じている。おそらく、この時点では、重俊が死去していたため、「子息等」に変えたのであろう。そして、あとを継いだ惣領重康が実際に現地に下向したのは、文永十二年(1275)であった。これ以後、重俊の系統の小代氏は肥後国に移住したのである。」
正代関の出身地は、熊本県宇土市で、荒尾市とは熊本市を経由して南側にある。
直線距離で約40㎞、川越から東京までと同じくらいの感じかも知れない。

『新編武蔵風土記稿 第九巻』(雄山閣)に、「正代村」が載っている。
「正代(ショウタイ)村
(前略)
地理を察するに、当村は入間の郡境にかゝる村なれば、当時入西に属せしなるべし。又正保改の国図にも、小代村と載たり、今の文字に改めし年月は伝えざれど、元禄改定の国図、及其時の郷帳には、正代村と書きたれば、これより前なること明けし、(後略)」
「小代」から「正代」に変わったことが書かれている。
熊本に移住した「小代氏」が、「正代氏」を名乗るようになった可能性はおおいにある。
そうであれば、正代関のルーツは埼玉県東松山市ということになりそうである。
だいぶ、荒っぽい推理だが、正代関を応援するには、これで十分である。