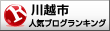石原町のささら獅子舞にとっては、まことに好都合であった。
菓子屋横丁を抜け、通りに出て左に曲がり、高沢橋を渡ると石原町である。
橋を渡り、川沿いに行くと直ぐ右手に観音寺の入口がある。
ささら獅子舞は、観音寺で行われると思っていたので、土曜日の午前11時頃行ってみた。
高沢橋の一つ南の橋へ行くと、観音寺の手前で人だかりがしている。
あわてて、近づいてみるとそこは、材木屋さんの前で、獅子舞の最中だった。
写真を撮ろうをした時、「これで終わりです」という声が聞こえた。

回りの人の輪が切れ、山伏、天狗を先頭に、行列ができ、川沿いの道歩きはじめた。
何が何だか分からず、行列についていった。
少し行って、細い道に入り、途中の家で獅子舞をした後、更に細い道に入った。
その奥に神社があった。八坂神社と書いてあった。
神社に着くと、一行はくつろいだ様子で、天狗は面を取り、獅子は着替えを始めた。
境内は狭いこともあり、祭りに参加する人、見物人で一杯になった。
腕章をつけた、市の広報の人もいた。
私の直ぐ前に、予定表のようなものを見ている女性がいた。
最初に観音寺で、次に材木屋さんの前で、そして今度はこの神社で獅子舞をやるようだった。
着物を着た男性の一人が、「今度は名人が踊るから」と回りの人に言っていた。
どうやら、踊り手も代わり、着替えは、そのためのものらしい。
祭りに参加する子供たちは、小学校低学年と思われる。
女の子は4人、ササラッコと呼ばれ、振袖を着て、黒い筒のようなものを両手に持っている。
これがササラだろうか。
男の子も4人、袴姿で頭に烏帽子をつけ、手に錫杖を持っている。こちらは山の神と呼ばれている。
もう一人男の子がいて、陣羽織を着て、右手に采配、左手に軍配を持っている。
女の子も男の子も口紅をつけ、目の横にも紅を付けている。
準備の途中、ささら獅子舞の保存に貢献した子供たちの表彰式があったが、これらの役を終えた子供たちであろうか。

20~30分ほどして、準備もでき、神社の広場に移動し始めた。
正面には、山伏、天狗と羽織袴の男性が座り、両脇に山の神が立つ。
右手には笛吹き、左手には歌うたいが扇子を持って腰掛けている。
四隅に女の子が立ち、大人が花笠を差し掛けている。
獅子は三頭、両脇に角ついた赤と黒の獅子、真ん中に角のない金色の獅子がいる。
先獅子(雄)中獅子(雌)後獅子(雄)と言うらしい。
その三頭の前に、陣羽織を着て、采配と軍配を持った男の子がいる。
この子が、獅子を指揮する役のようだ。
最初に、マイクを持った人が解説をしたが、一回の踊り(これを一庭というらしい)に40分位かかると言っていた。
獅子舞が始まると、笛に合わせて、三頭の獅子と男の子が舞う。
踊りは12の部分に別れているそうで、場面の間に休みの時間がある。
獅子三頭は腰を落とし、男の子は体を前に倒し、采配と軍配を地面につけた姿勢でとまる。
これを繰り返し、踊りは進んで行く。
歌は途中1回入ったような気がしたが、実際には2回だったようだ。

終盤に入ると、雄の獅子が俄然激しくなる。
二頭が角を付きあわせ、獅子頭を激しく回す場面もある。
写真は、第10場はかみあい。四隅に立っている花笠が中央に出てきて中獅子を囲んで隠している。
夢中でカメラのシャッターを押していると、あっという間に終わってしまった。
広場には青いシートが敷かれ、昼食になるようだった。
本当に天気が良くなって、良かったと思った。

16(日)の新聞にささら獅子舞の記事が出ていたが、材木屋さんの前の写真が載っていた。