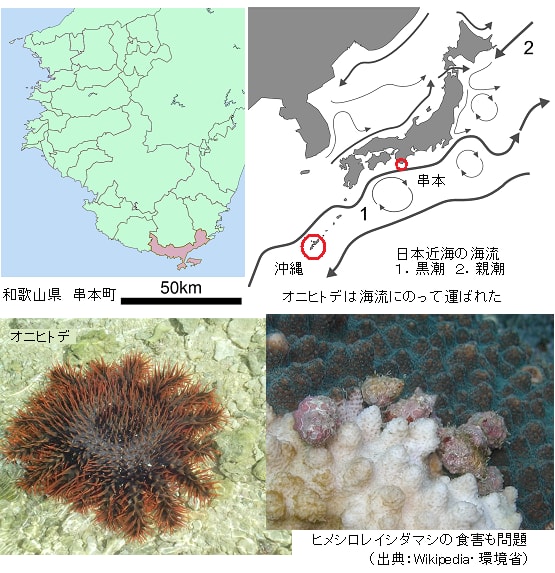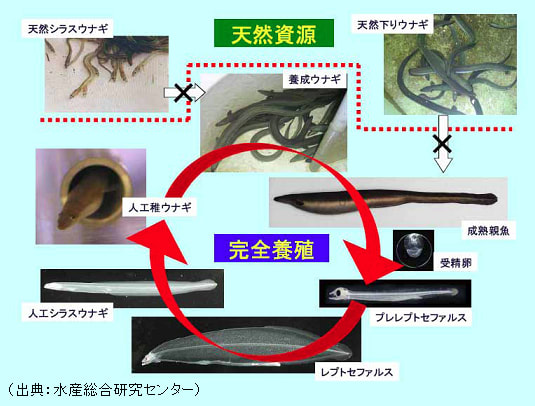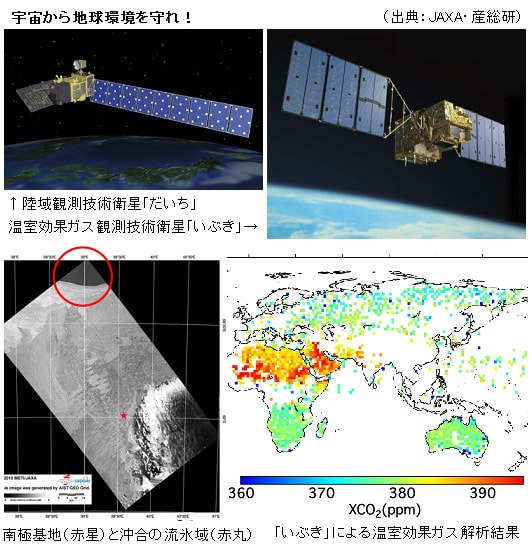最近気になる科学情報を、くわしく調べやさしく解説!毎日5分!読むだけで、みるみる科学がわかる!
最近気になる科学情報を、くわしく調べやさしく解説!毎日5分!読むだけで、みるみる科学がわかる!
放鳥トキ、今年の自然繁殖断念
今年のトキの自然繁殖は残念ながら失敗に終わったようだ。日本のトキの放鳥は、2008年に10羽、2009年に20羽、佐渡で放鳥された。その中の何組かがつがいとなり、巣を作り産卵や抱卵が観察されたが、ヒナがかえることはなかった。
一方、5月24日の新華社電によると、中国陝西省政府は、同省寧陝県で野生復帰を目指して放鳥されたトキの卵が22日、ふ化して2羽のひなが生まれたことを明らかにした。
中国で2007年以降3回にわたって放鳥された計40羽から、野外での繁殖が確認されたのは初めて。同省自然保護区・野生動物管理所の責任者は「2代目のひなが野外で誕生したことは、トキが絶滅の危機を脱したことを示唆している」と話している。
誕生した2羽の父親は同県内で生まれた野生のトキ、母親は人工繁殖後に放鳥されたトキ。このペアのほか、6組のペアも産んだ卵を温めているという。(5月24日 時事通信)

トキ野生復帰への道
さて、今年のトキ野生復帰への取り組みをたどってみよう。
2010年3月11日、日本では2010年秋の第3回放鳥に向けて訓練のため、トキを入れていた順化ケージ内でトキ9羽が死んでいたことが発見された。日本の野生繁殖に暗雲が立ちこめた。
環境省はケージ内の足跡から、トキを襲ったのはイタチ科のテンと判明したと発表した。テンがどこから侵入したのかは不明で、同省は同日朝から現地調査を始めた。専門家を集めて今後の対策も検討するが、原因が判明しない限りトキの訓練は当面見合わせる考え。今秋の放鳥が見送られる可能性も出てきた。
原因究明に相当な時間がかかるとみられ、トキの放鳥前の訓練に十分な期間が取れない上、死んだ9羽に代わるトキを、限られた個体から再選定する必要があるためだ。
仮に中止になれば、国の保護増殖計画も見直しを迫られる。環境省は人工繁殖したトキを2008年から2回、計30羽放鳥。26羽の生存が確認され、今秋の21羽の放鳥が加わることで、来春に初のペア誕生を目指していたが、その可能性は低くなる。(2010年3月11日 読売新聞)
放鳥トキ初の産卵、自然界で31年ぶり
一方、うれしい報告もあった。環境省は3月29日、新潟県佐渡市で放鳥され、巣を作ったトキのペア1組が産卵したことを発表した。
3歳の雄と1歳の雌のうち必ずどちらか1羽が巣に残って座り込む様子が観察されており、卵を温める「抱卵」とみられるという。産卵は、自然界のトキとしては31年ぶりのことであった。
これまで巣作りが確認された放鳥トキは計3組。佐渡トキ保護センターの飼育記録などによると、トキの雌は1日おきに4個ほどの卵を産むという。(2010年3月29日 読売新聞)
トキの赤ちゃん誕生、いしかわ動物園
さらに、佐渡トキ保護センター(新潟県佐渡市)から移送され、石川県能美市の「いしかわ動物園」で分散飼育されているトキのつがいが産んだ卵から、3月25日にひながかえった。飼育員から馬肉やコマツナを混ぜた人工飼料を注射器で少しずつ与えられ、元気に鳴き声を上げた。
同動物園によると、26日、27日にもひながかえり、合計3羽になった。ひながかえったのは8歳雄と6歳雌のペア、他に5歳雄と3歳雌のペアもおり、こちらの方も3個が有精卵でひながかえりそうだという。
同動物園は3月29日から、午前11時半と午後2時半の2回、園内の動物学習センターに設置された大型モニターで給餌風景のライブ映像の公開を始めた。(2010.4.28 産経ニュース)
難しい野生のふ化 専門家「一歩前進」
一方、野生のつがいの方は今年6組ペアができて営巣した。産卵したのは4組みであったが、いずれも、ペアが留守の間に、カラスに襲われたり、無精卵だったりしてかえることはなかった。今年は天候が不順で低温のため、成長が止まった可能性もある。野生の繁殖がいかに難しいかがわかるが、専門家は「想定された事態」と受け止める。
トキは通常、一つの巣に3~4個の卵を産み雄と雌が交代で卵を温め、約28日でひながかえる。佐渡トキ保護センターの集計では、2007~2009年に飼育下で産卵した288個のうち有精卵は146個で、さらにふ化するのは半数余りにとどまる。
中国のトキ保護に詳しい環境文化創造研究所(東京)の蘇雲山・主席研究員によると、中国で1981年から20年間に野生下で巣立ちしたのは1巣当たり1.87羽だった。人工飼育後に放鳥した場合では1.57羽と野生より低かった。
野生復帰を目指して放鳥されたコウノトリも初年度は産卵のみで、ひながかえったのは2年目だった。山階鳥類研究所の尾崎清明副所長は「卵に異常を感じて捨てたのだろう。ひながかえる直前まで抱卵できたのは一歩前進だ」と話す。(毎日新聞 2010年4月29日)
 |
蘇るコウノトリ―野生復帰から地域再生へ 菊地 直樹 東京大学出版会 このアイテムの詳細を見る |
 |
トキ永遠なる飛翔―野生絶滅から生態・人工増殖までのすべて (ニュートンムック) 近辻 宏帰 ニュートンプレス このアイテムの詳細を見る |