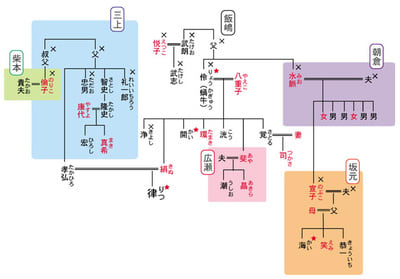ミステリと言う勿れ 田村由美
https://amzn.to/3vJjQo1
失敗って断言して良いのかどうかはさておき、思ったほど盛り上がらなかったと感じたのは私だけではないはずだと思いまして。
端的に言うと、伊藤沙莉が演じる風呂光刑事が不評だった訳ですが、原作からのキャラ変が受け容れられなかった人と伊藤沙莉が気に入らない人は別だよね、という話です。
前者の話として、原作の風呂光さんは、紅一点キャラのステレオタイプである「かわい子ちゃんポジション」の否定からスタートしているキャラだと思います。
それがドラマでは典型的な「かわい子ちゃんポジション」に収まってるんですから、原作ファンから反発食らうのは当然のことと思います。
この「かわい子ちゃんポジション」の否定は、作品全体の大きなテーマの一つである「固定観念を捨てて違う角度からものを見る」事に通じています。
(因みに、「固定観念を捨てる」という思考を突き詰めると高確率でフェミニズムに繋がってしまいます。なぜというなら、固定観念は権力を握った人たちが、自分たちの属性に都合が良いように作り上げて来たものだから。社会の中で権力を握っているのは多くが「大人の男性」すなわち「おじさん」ですね。故に、この漫画ではしばしば「おじさん」に矛先が向いてしまうのです)
風呂光さんのキャラ変が意味するもの、それはこのドラマの製作陣が、原作の大事な所を理解していないという事ではないでしょうか。
尚、伊藤沙莉が気に入らない層は「かわい子ちゃんポジションなんだからもっと可愛い子を出せ」と言ってる訳で、「かわい子ちゃんポジション」そのものは何の疑いもなく受け容れているという意味で、前者とは相容れないというか寧ろ真逆の層だと思います。
何故こんな、誰も得しない改変が行われてしまったのかというと、やっぱりテレビ局なり制作現場のお偉いさんの「おじさん」たちが、無自覚に固定観念にどっぷり浸かっているからなんだろうなと思います。
中身は旧態依然の「かわい子ちゃん」キャラになってしまってるのを、外側だけ実力派(という事に世間ではなっている)伊藤沙莉にして新しいことをしたつもりになってたらそりゃ盛大に滑るよねっていう話。
漫画原作からドラマ化する際、改変が必ずしもダメな訳ではないと思います。
そのまんま忠実に実写化とか物理的に不可能だと思いますし。
例えば「岸辺露伴は動かない」はその辺上手くやっていますよね。バトルもの要素が入った少年漫画なので、実写化のハードルは少女漫画より高いはずですが。
原作ではバラバラの話を大胆に組み合わせて連作に仕立てていますが、原作ファンからも原作未読の人からも概ね好評。
原作では「富豪村」にしか出ない泉京香をレギュラー化しても、露伴先生と京香のキャラや関係性は原作のイメージを壊していない。出番の寡多は問題じゃないんですね。
原作をしっかり読みこんで理解して、変えて良い所とダメな所をちゃんと見極めていれば、原作ファンから無闇な文句は出ないのです。
まあ、一番大きいのは脚本家の力量の差だと思いますが。
ドラマオリジナルで追加された風呂光さん→整くんの恋愛ネタってすごく雑な印象でした。どっかで見たような場面をキャラだけ変えて適当に切り貼りしてる感じで。
この部分はじめ、原作のままの部分とドラマのオリジナル部分のクオリティの差に、脚本家の力のなさが残酷なくらいに現れていると思いました。
原作では、整くんの恋愛ネタはライカさんとの間にしかありません。
どっちも恋愛しそうにない男女が少しずつお互いを探りながら心を開いて行く過程がすごく繊細に描写されていて、恋愛ネタにあんまり興味ない私ですら、「整くんがんばって」と思わされてしまった。
これが少女漫画の大御所・田村由美の実力か…と恐れ入ってしまいました。
風呂光さんも、原作では出番は少ないながら、地に足のついた仕事ぶりで着実に活躍しています。そもそも警察の採用試験に合格して、警官になって、刑事課に配属される段階で十分優秀なはずなので。
だけど配属された先に、薮さんのような上司がいたらその優秀さも発揮できないというのがエピソード1のテーマのひとつ。怒られて自信を無くし、萎縮して積極的に動けなくなり、さらに怒られて…の悪循環から脱出できたのは、整くんの言葉(そしてそれがきっかけの過去事件犯人逮捕)もあるけど、薮さんがいなくなったのも大きいのだろうと思います。
バスジャック以降のエピソードでは、やる気と自信を取り戻した彼女の姿がちょこちょこ登場します。原作10巻の誘拐事件のエピソードとか、最早勇姿と言って良い。
個人的に原作のバスジャック事件の時の風呂光さん好きなんですよね。
原作では犬堂家での出番は2コマくらいですけど、小さい絵でもわかるくらいすごくやる気のある表情をしていて、それだけで頑張ってるんだなっていうのが伝わって来ます。こういうのをさらっと描けるのが流石の田村由美。テレビ局の偉い人にはそれがわからんのです。残念ながら。