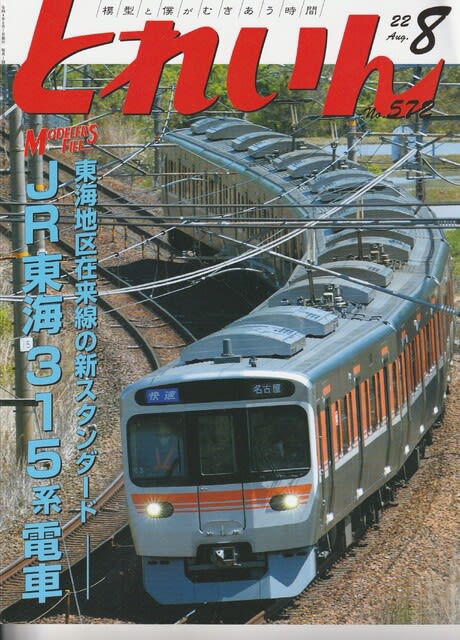「マッハ模型を語る」で購入、 54頁から58頁に掲載されてます。
父に連れて行ってもらったのが旭屋書店時代、1975年の夏休み最後の日曜日でした。 そばに電気工学の本の売り場がありましたが、その本に見入ってしまいました。
マッハの近くにいたのは1976年に津に引っ越すまででした。 阪急沿線に住んでたので梅田で降りて警察の前の階段を上がってエスカレーターで上りました。 型紙や小高の床下機器を買いました。 中村精密のナハ10をお年玉で買いました、その時に「塗るなら屋根とサッシだけ塗ったらええで。」と言ってくれました。 当時のマッハの鉄道カラーが180円でしたがプラ用が300円でかなり高かった記憶があります。 紛失してしまいましたが洋白の阪急2800の中間車のエッチング板を求めました。 窓1個所を抜いただけでした。
津に引越してからは高校受験もあり疎遠になってしまいましたが、高校入学後は工専に行った友人と朝一番の伊勢中川行きの急行に乗って、その車両が折り返して上本町行きの区間快速急行になり鶴橋で環状線に乗り換えて大阪で降りたり、日本橋で工具を求め梅田に向かったこともありました。 初めて真鍮工作の半田鏝を買ったのが日本橋でした。
和歌山に引越してから模型店巡りを覚え、和歌山市駅から新今宮、京橋はええとこですが乗り換えて放出、池田さんの工作を拝見し再び京橋で乗り換えて大阪で降りる、帰りは御堂筋線で難波というルートでした。 井川さんの兄弟喧嘩も「やっとんなー」と思いながら見てましたが、有名だったんですね。
ラジオでマッハ模型が放送されたこともありました。 MBSだったと思いますが大盛況で身動きが取れない状況でした。 「やっぱりすごいお店だ。」と思いました。 関西の模型店全体に言える、関西についてすべていえることかもしれませんが「誂えの文化」が強くお店独自の商品や加工品がありました。 今年で関東に出てきて40年になりますが「離れてわかるそのよさ。」を感じました。 「関西の文化」の一つが消えていきました。