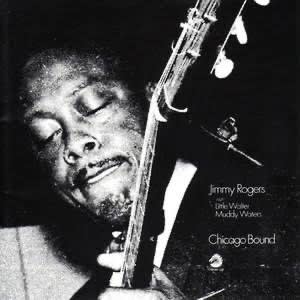2022年12月21日(水)

#402 DEEP PURPLE「MACHINE HEAD」(WARNER BROS. 3100-2)
英国のバンド、ディープ・パープル、72年3月リリースのスタジオ・アルバム。彼ら自身とサイモン・ロビンスンによるプロデュース。
70年の「イン・ロック」、71年の「ファイアボール」と1作ごとに人気が上昇していったディープ・パープル(以下パープル)の、本格的ブレイクの決定打となった一枚である。
全英1位、全米7位、そして日本でも6位と、全世界が深い紫色に染まることとなった。
そして72年8月、彼らはついに初来日を果たし、日本武道館での公演をライブ録音するまでに至る(アルバム・リリースは同年12月)。
英国のハード・ロック・バンドとして は、71年9月初来日のレッド・ツェッペリンに次いで、日本での人気を不動のものとしたのである。
個人的にはガチのZEP派だった当時中学生の筆者は、さほどパープルに思い入れはなかったが、それでもロック・バンドの真似事をやり始めた時期ということもあって、彼らの曲のいくつかをコピーして、レパートリーにしようとしていた記憶があり、なんとも懐かしい。
この「マシン・ヘッド」の大ヒットの理由は、なんといっても「ハイウェイ・スター」「スモーク・オン・ザ・ウォーター」の2大人気曲を収めていることだ。
前者はシングルカットされることはなかったが、後者は翌年米国でシングルとして全米4位、ロッド・エヴァンス時代の「ハッシュ」以来5年ぶりのヒットとなっている。
キャッチーなリフ、あるいはスピーディでカッコよく、かつ覚えやすいギター・ソロ、派手なアーミング。
ハードなサウンド、熱いボーカルに加えて、パープルにはバンド少年たちの、とりわけギター・キッズを虜にする魅力に満ちていた。
オープニングの「ハイウェイ・スター」は、まさにその魅力が凝縮された一曲。スーパー・アップテンポでグイグイ押してくるナンバーだ。
この曲の、間奏のギター・ソロが完コピ出来るかどうかが、当時のハード・ロック系ギタリストの「試験」みたいなもんだった。いやマジで。
リッチー・ブラックモアのあのトリル部分は、ホント、昇天もののカッコよさだった。
「メイビー・アイム・ア・レオ」はジョン・ロードのオルガンが重厚な、ミディアム・テンポのナンバー。ほとんど、ライブではやらないらしい。ちょっと平板で、盛り上がりに欠けるからかな。
「ピクチャーズ・オブ・ホーム」はアップ・テンポのナンバー。毎度のブラックモアやロードの長いソロだけでなく、珍しくロジャー・グローヴァーのベース・ソロまで聴ける。
A面ラストの「ネヴァー・ビフォア」は、ミディアム・テンポのロックンロール。ポップな味付けもあり、シングル・カットされたが、さほどヒットはしなかった。
思うに、ビートがオーソドックス過ぎて、いささか面白みに欠けている。
パープルは、もっと自分たちらしさを出した曲で勝負すべきということなんだろうな。速い16ビートとか、ギターやキーボードの超絶技巧とかで。
B面トップは「スモーク・オン・ザ・ウォーター」。ミディアム・テンポのナンバー。
一見普通のエイト風にみえて、イアン・ペイスのドラミングは芸が細かいので、ドラマーの方はよーく聴いて欲しい。
この曲はそのギター・リフがあまりにも有名だが、ギターを始めたばかりの少年たちにも「これは手が届きやすい」という印象を持たれるからだろうな。確かに、ジミー・ペイジあたりに比べると、聴き取りやすい気がする。
でも、実際に弾いてみると、ブラックモアのような音質、ピッキング・タッチを再現するのは、結構難しいんだけどね。
この「スモーク・オン・ザ・ウォーター」は、うまくギターをプレイするには、スピードよりも、粘りとかタイミングこそが大切さなのだと分からせてくれる。
続く「レイジー」は、7分19秒とアルバム中、最長尺のナンバー。リズムがシャッフルというのが、ハード・ロック・バンドとしてはちょっと珍しい。
でも、プログレッシブ・ロックだろうが、ハード・ロックだろうが、その大元、根本はブルースやジャズなんだから、シャッフルは必修科目みたいなものなんだけどね。
印象的なリフは、エリック・クラプトンがクリームやブルースブレイカーズで弾いていた「ステッピン・アウト」を参考にして作られたらしい。
後半、ボーカルのイアン・ギランがブルース・ハープをちょっと披露してみせるのが、本曲の聴きどころである。
パープルもルーツはブルース・バンド。そのことがよく分かる一曲。
ラストは「スペース・トラッキン」。ヘビーなイントロから始まる、いかにもパープルらしいロック・チューン。ギランのギラつくようなシャウトも絶好調である。
これは彼らのライブの定番曲のひとつで、ラストに数十分、延々とインプロビゼーションを繰り広げるのが常だったらしい。筆者は一度も観ておりませんが(笑)。
ディープ・パープルというバンドの、一番旬な時期(もちろん、第3期以後の方を評価する向きもいらっしゃるでしょうが)を記録した、最高のスタジオ・アルバム。
武道館ライブを合わせて聴けば、皆さんの青春の記憶が鮮やかによみがえるはず。ぜひ、涙して聴いて欲しい。
<独断評価>★★★★
英国のバンド、ディープ・パープル、72年3月リリースのスタジオ・アルバム。彼ら自身とサイモン・ロビンスンによるプロデュース。
70年の「イン・ロック」、71年の「ファイアボール」と1作ごとに人気が上昇していったディープ・パープル(以下パープル)の、本格的ブレイクの決定打となった一枚である。
全英1位、全米7位、そして日本でも6位と、全世界が深い紫色に染まることとなった。
そして72年8月、彼らはついに初来日を果たし、日本武道館での公演をライブ録音するまでに至る(アルバム・リリースは同年12月)。
英国のハード・ロック・バンドとして は、71年9月初来日のレッド・ツェッペリンに次いで、日本での人気を不動のものとしたのである。
個人的にはガチのZEP派だった当時中学生の筆者は、さほどパープルに思い入れはなかったが、それでもロック・バンドの真似事をやり始めた時期ということもあって、彼らの曲のいくつかをコピーして、レパートリーにしようとしていた記憶があり、なんとも懐かしい。
この「マシン・ヘッド」の大ヒットの理由は、なんといっても「ハイウェイ・スター」「スモーク・オン・ザ・ウォーター」の2大人気曲を収めていることだ。
前者はシングルカットされることはなかったが、後者は翌年米国でシングルとして全米4位、ロッド・エヴァンス時代の「ハッシュ」以来5年ぶりのヒットとなっている。
キャッチーなリフ、あるいはスピーディでカッコよく、かつ覚えやすいギター・ソロ、派手なアーミング。
ハードなサウンド、熱いボーカルに加えて、パープルにはバンド少年たちの、とりわけギター・キッズを虜にする魅力に満ちていた。
オープニングの「ハイウェイ・スター」は、まさにその魅力が凝縮された一曲。スーパー・アップテンポでグイグイ押してくるナンバーだ。
この曲の、間奏のギター・ソロが完コピ出来るかどうかが、当時のハード・ロック系ギタリストの「試験」みたいなもんだった。いやマジで。
リッチー・ブラックモアのあのトリル部分は、ホント、昇天もののカッコよさだった。
「メイビー・アイム・ア・レオ」はジョン・ロードのオルガンが重厚な、ミディアム・テンポのナンバー。ほとんど、ライブではやらないらしい。ちょっと平板で、盛り上がりに欠けるからかな。
「ピクチャーズ・オブ・ホーム」はアップ・テンポのナンバー。毎度のブラックモアやロードの長いソロだけでなく、珍しくロジャー・グローヴァーのベース・ソロまで聴ける。
A面ラストの「ネヴァー・ビフォア」は、ミディアム・テンポのロックンロール。ポップな味付けもあり、シングル・カットされたが、さほどヒットはしなかった。
思うに、ビートがオーソドックス過ぎて、いささか面白みに欠けている。
パープルは、もっと自分たちらしさを出した曲で勝負すべきということなんだろうな。速い16ビートとか、ギターやキーボードの超絶技巧とかで。
B面トップは「スモーク・オン・ザ・ウォーター」。ミディアム・テンポのナンバー。
一見普通のエイト風にみえて、イアン・ペイスのドラミングは芸が細かいので、ドラマーの方はよーく聴いて欲しい。
この曲はそのギター・リフがあまりにも有名だが、ギターを始めたばかりの少年たちにも「これは手が届きやすい」という印象を持たれるからだろうな。確かに、ジミー・ペイジあたりに比べると、聴き取りやすい気がする。
でも、実際に弾いてみると、ブラックモアのような音質、ピッキング・タッチを再現するのは、結構難しいんだけどね。
この「スモーク・オン・ザ・ウォーター」は、うまくギターをプレイするには、スピードよりも、粘りとかタイミングこそが大切さなのだと分からせてくれる。
続く「レイジー」は、7分19秒とアルバム中、最長尺のナンバー。リズムがシャッフルというのが、ハード・ロック・バンドとしてはちょっと珍しい。
でも、プログレッシブ・ロックだろうが、ハード・ロックだろうが、その大元、根本はブルースやジャズなんだから、シャッフルは必修科目みたいなものなんだけどね。
印象的なリフは、エリック・クラプトンがクリームやブルースブレイカーズで弾いていた「ステッピン・アウト」を参考にして作られたらしい。
後半、ボーカルのイアン・ギランがブルース・ハープをちょっと披露してみせるのが、本曲の聴きどころである。
パープルもルーツはブルース・バンド。そのことがよく分かる一曲。
ラストは「スペース・トラッキン」。ヘビーなイントロから始まる、いかにもパープルらしいロック・チューン。ギランのギラつくようなシャウトも絶好調である。
これは彼らのライブの定番曲のひとつで、ラストに数十分、延々とインプロビゼーションを繰り広げるのが常だったらしい。筆者は一度も観ておりませんが(笑)。
ディープ・パープルというバンドの、一番旬な時期(もちろん、第3期以後の方を評価する向きもいらっしゃるでしょうが)を記録した、最高のスタジオ・アルバム。
武道館ライブを合わせて聴けば、皆さんの青春の記憶が鮮やかによみがえるはず。ぜひ、涙して聴いて欲しい。
<独断評価>★★★★