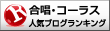2月22日(日)に第22回札幌ヴォーカルアンサンブルコンテストが行われた(偶然ながら2が5つも並んだことに気が付いた人がいたのか?)。全出場団体59の演奏を聞いた(聞かせられた~笑~)。朝から夕方18時過ぎまでの長丁場であったが、楽しく聞くことが出来た。各団体ごとに講評を書くという仕事もあるために、睡魔が忍び寄るという隙も無かった(笑)。全体を通して幾つかの特徴というか、近年の傾向を読み取ることが出来たので触れてみたい。
まず、出場団体数は例年60団体程度のエントリーが固定化されているようだ。一日日程で消化するには最大これくらいまでと思われるが、4人の審査員を見出すのが大変そうにも感じる(私にまでお呼びが掛かるのだから・・・)。審査方法としては順位を出すのではなく、各審査員がそれぞれの団体に金、銀、銅、奨励のいずれかを与えるという方式なので、さほど複雑ではない。しかし、睡魔撃退の切り札(笑)とはなっても、書くという作業が疲労を呼ぶようだ(特に目)。昨日、自分の審査傾向としては疲労が増した後半が何故か厳しい評価になったように感じている。ただし、よほど聞くに絶えない演奏でなければ、基本的に奨励は付けないという方針は最後まで保持したが、銅賞にした団体が多くなったように感じている。
出場団体の構成を見ると、高校生以下の部に30団体のエントリーがありほぼ半数を占めている。内訳は小学生が3、中学生が19、高校生が5、混合(中高、ジュニアなど)が3であった。そして、旭川や千歳、恵庭など、札幌市以外からの参加もあった(団体数に余裕がある場合は他地区からの参加も認めている)。なお、小学生チーム3団体が全て金賞という成績は立派であった。小中高生の参加が増え、演奏内容も向上していることは大変喜ばしいことである。
一方、当コンテストにおいて最も私が期待しているルネッサンス・バロック部門の参加団体が3とは誠に残念である。いつもこの部門への参加は少ないようだが、3団体というのは寂しい限りであり、ルネ・バロに挑戦する団体が少ないという北海道全体の特徴が現れているようだ。その他に特筆すべき傾向としては、参加者の年齢の偏りである。圧倒的に若者が多く、常設合唱団の参加が少ない。大学合唱団の有志とか、最近出来た若者中心の合唱団が多く、ベテランも加わっている一般合唱団の参加が少ない。素晴しい演奏をしている若い合唱団への期待も高いが、年齢構成が多様な一般合唱団の活動も大いに期待したいと強く感じた。
まず、出場団体数は例年60団体程度のエントリーが固定化されているようだ。一日日程で消化するには最大これくらいまでと思われるが、4人の審査員を見出すのが大変そうにも感じる(私にまでお呼びが掛かるのだから・・・)。審査方法としては順位を出すのではなく、各審査員がそれぞれの団体に金、銀、銅、奨励のいずれかを与えるという方式なので、さほど複雑ではない。しかし、睡魔撃退の切り札(笑)とはなっても、書くという作業が疲労を呼ぶようだ(特に目)。昨日、自分の審査傾向としては疲労が増した後半が何故か厳しい評価になったように感じている。ただし、よほど聞くに絶えない演奏でなければ、基本的に奨励は付けないという方針は最後まで保持したが、銅賞にした団体が多くなったように感じている。
出場団体の構成を見ると、高校生以下の部に30団体のエントリーがありほぼ半数を占めている。内訳は小学生が3、中学生が19、高校生が5、混合(中高、ジュニアなど)が3であった。そして、旭川や千歳、恵庭など、札幌市以外からの参加もあった(団体数に余裕がある場合は他地区からの参加も認めている)。なお、小学生チーム3団体が全て金賞という成績は立派であった。小中高生の参加が増え、演奏内容も向上していることは大変喜ばしいことである。
一方、当コンテストにおいて最も私が期待しているルネッサンス・バロック部門の参加団体が3とは誠に残念である。いつもこの部門への参加は少ないようだが、3団体というのは寂しい限りであり、ルネ・バロに挑戦する団体が少ないという北海道全体の特徴が現れているようだ。その他に特筆すべき傾向としては、参加者の年齢の偏りである。圧倒的に若者が多く、常設合唱団の参加が少ない。大学合唱団の有志とか、最近出来た若者中心の合唱団が多く、ベテランも加わっている一般合唱団の参加が少ない。素晴しい演奏をしている若い合唱団への期待も高いが、年齢構成が多様な一般合唱団の活動も大いに期待したいと強く感じた。