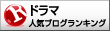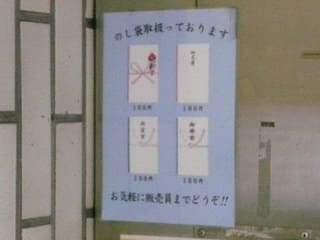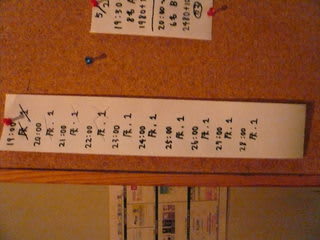ビール(蘭: bier, 英: beer)は麦芽由来の酵素 (アミラーゼ) により、穀物に含まれるデンプンを加水分解して糖化し、酵母により発酵させて作るアルコール飲料の一種。漢字で麦酒(ばくしゅ、ビール)と表記される場合もある。ビールと呼べるのは麦芽使用率25%以上の物だけである。
現代のものは炭酸ガスに由来する清涼感とホップに由来する独特の苦みが特徴となっているが、起源が非常に古いこともあり、歴史的、地域的多様性は高い。
日本では、ビール類似の発泡酒などを含めて、一年を通じて最も消費されているアルコール飲料である。特に枝豆や冷奴とともにビアガーデンでよく冷えたビールを飲むことは夏の風物詩となっている。日本ではビールは季節を問わず必ずよく冷やしてから飲むものとされているが、ドイツなどの国では、ビールを冷やさず室温で飲むことが好まれる。
語源
英語:ビア, beer(en:beer)と、エール, ale(en:ale)の2種類の言葉があり、エールの方が古い
ale系
インド・ヨーロッパ祖語の、alu-(酔う、魔術的な、など)から来ている。([1])
ゲルマン語:aluth-
フィンランド語:olut
エストニア語:õlu
デンマーク語・ノルウェー語:øl
ラトヴィア語/リトアニア語:alus
beer系
ラテン語:bibere(飲む, 動詞)が起源
古英語ではビアとエールは違い、ビアは今のサイダーだったとする説もある
ノルマン・コンクエストの後、一時”beer”は無くなるが、麦芽飲料をさす呼称として間もなく再現する。
スペイン語、ポルトガル語では、ラテン語:cervisia(ケレスの力)から派生
他の西ヨーロッパ語(幾つかの東ヨーロッパ語)は英語:beerと似た言葉を使う
スラヴ語派諸国では、スラブ語:"pivo"の派生系を使う
歴史
その歴史は古く、既にメソポタミア文明のシュメール人により大麦を使い作られていた。ちなみにシュメール人はワインの製法も開発している。紀元前3000年頃に古代エジプトにビールの製法が伝わった。
これらの古代オリエントのビールは、麦芽を乾燥させて粉末にしたものを、水で練って焼き、一種のパンにしてからこれを水に浸してふやかし、麦芽の酵素で糖化を進行させてアルコール発酵させたものであった。大麦はそのままでは小麦のように製粉することは難しいが、いったん麦芽にしてから乾燥させると砕けやすくなり、また消化もよくなる。つまり、ビールは元来製粉が難しくて消化のよくない大麦を消化のよい麦芽パンにする技術から派生して誕生したものと考えられている。穀類を豊富に産したメソポタミアやエジプトでは、こうした背景を持つビールはパンから派生した、食物に非常に近い日常飲料であった。実際、古代エジプトのパピルス文書には、王墓建設の職人たちへの配給食糧として、ビールが記録されている。焼いてから時間のたった固いパンを液体でふやかすという発想は、ヨーロッパのスープの原型となった、だし汁でふやかしたパンとも共通しており、ふやかしたパンの料理という共通系譜上の食物ともいえる。
一方、麦芽の酵素によって大麦のデンプンを糖化させ、その糖液をアルコール発酵させるというビール製造の核心技術は、北方のケルト人やゲルマン人にも伝わったが、彼らの間では大麦麦芽をいったんパンにしてからビールを醸造するという形をとらず、麦芽の粉末をそのまま湯に浸して糖化、アルコール発酵させる醸造法が行われた。また日常の食物の派生形であった古代オリエントのビールと異なり、これらヨーロッパ北方種族のビールは、穀物の収穫祭に際してハレの行事の特別な飲料として醸造が行われる傾向が強かった。
ローマにはエジプトから伝えられたものがジトゥム (zythum) 、北方のケルト人経由で伝わったものがケルウィシア (cervisia) と呼ばれたが、ワインが盛んだったために野蛮人の飲み物視され、流布しなかった。ローマ人や古代ギリシア人の間では、大麦は砕いて粗挽きにしたものを粥にして食べるのが普通であったのである。またアルコール飲料として一般的だったワインも、固いパンを食べやすくするブドウのジュースを長期保存できる形にした日常の食卓の飲料としての性格が強く、酔うためにそのまま飲むのは野蛮人の作法とされ、水で割って飲むのが文明人の作法とされていた。それだけに、祝祭に際して醸造したビールを痛飲して泥酔する北方種族の習俗は、自らを文明人と自認するローマ人、ギリシア人の軽蔑の種にもなっていたのである。
16世紀の醸造所ケルト人やゲルマン人の居住地域が表舞台となった中世ヨーロッパにおいては、ビールは盛んに作られ、その醸造技術の発展には修道院の醸造所が大きな役割を果たした。当時は、子供にもあった飲み物であると考えられていた。ヨーロッパのビール醸造において、古くから発酵を安定させるなどの目的でさまざまなハーブ類を添加する伝統があったが、11世紀のドイツにおいて、その抗菌作用と独特の苦みを利用するために、ホップが最も一般的なビール醸造用のハーブとなっていった。
現代ビールは19世紀後半のカールスバーグ研究所での酵母の純粋培養技術の開発をはじめとした科学技術の利用や缶やビン詰め製法の確立等の流通形態の改革、また、運輸・貯蔵技術の発達等にともなって、大企業が市場を占有するようになった。これらの技術体系の発達は、それまで本来主食とすべき麦をあえて酔うためのアルコール飲料とする、祝祭の飲料の性格が強かったビールが日常の飲料として浸透するという現象をもたらした。それまではむしろワインのほうが本来食事を食べやすくするための葡萄ジュースの保存食として、日常の飲料の性格が強かったが、近代的食品工業によって安価かつ大量に安定供給されるビールのほうが、肩のこらない日常の酒として普及し、ワインとビールの日常文化的位置の逆転を引き起こす結果となった。
その一方で、現在ではアメリカやヨーロッパでは伝統的製法への回帰や自然志向の流れの中で、クラフトビールやマイクロブルワリーが注目されており、日本では法規制が緩和されたこともあり、地ビール醸造所が多く設立されてきている。
25年前、初めての海外旅行で、当時「西ドイツ」ミュンヘンの有名なビアホール・ホッフブロイハウスに行った時、1リットルのジョッキでビールを飲んだ。トイレで便座に座っていたら、「リリー・マルレーン」をみんなで歌っている歌声が聞こえてきて、感動した。暑い夏には冷たいビル。焼肉屋のビールは大ビンでなきゃ。でも、中国やインドではビールは冷やさない。面白い風習である。