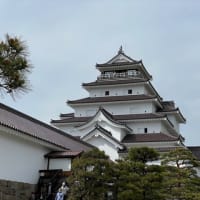まえがき
世の中の人すべてが信じられなくなり、自分すらも信じられなくなった私。擦り切れた心を抱え息苦しい日々が続いていたそんなある日、京の外れの山奥でひとりの隠者に出会った。http://ncode.syosetu.com/n9691p/
本文
心が擦り切れる。きりきりと擦り切れる。うわべばかり繕っているからこうなるのだ。とはいえ、この気持ちは誰にも言えない。妻や親しい友人なら、なおさら話すことなどできない。
自分の気持ちを正直に言ってしまえば、相手の心に負担をかけてしまう。まず、それが怖い。誰だって自分の心をかき乱されたくないものなのだから、優しくいたわってくれる人にそんな迷惑をかけられない。
それに、自分の正直な気持ちが間違いだったらどうしようと思ってしまう。裸の心を見られた、と思っただけでもうだめだ。居たたまれなくなって、自分の足場が崩れ落ちたような気にさせられる。わかってくれないなと変に先読みして、わかってくれるはずがないと思いこんで落ちこんで、やはりわかってくれなかったことに落胆して――。的外れだけどやさしくて、あたたかいけど通り一遍な慰めの言葉がよけいにつらい。理解してもらえないことが、なぜか相手にすまない。
一人ひとり違う人間なのだから、わかってもらえないのは、当然だ。それは重々承知のうえだが、薄々気づいている壁をはっきり認識すれば、さびしくなってしまう。もっとも、理解してもらえたところでどうにもならないことも、わかっている。結局のところ、この擦り切れた心は自分ひとりで背負わなければならないものなのだから。
馬に跨りながら渓間の小道をとぼとぼと進んだ。
いつも同じことを考えては堂々巡りだった。その先を考えたいのに、どうすればいいのかわからない。同じことの繰り返しから抜け出して、どこかへ向かって進みたいのに、出口が見つからない。私《わたくし》という迷宮にはまりこんで、方角を見失ってしまったようだ。空っぽの心《しん》に鉋をかけては、肉も血も削いでゆく。いつも、胸が、圧されたように痛む。
馬に鞭を当てて急いで帰らなければいけないのはわかっている。とはいうものの、とてもそんな気にはなれなかった。なにも知らないで優しく迎えてくれる妻。早く孫ができないかとそればかり気にしている両親。友人からの連歌や食事の誘い。そのどれもがやりきれない。このままずっと独りきりでいるほうがどれだけ気が休まるだろう。いっそのこと、路傍の石になって、なにも感じずに、なにも考えずにいられたらどんなにいいことか。どうせ出口がないのなら、誰にも煩《わずら》わされず、誰も煩わさず、うずくまっていたい。
日が暮れなずむ。
ぼんやりとした夕陽が深い山の谷間に懸かり、木立を吹き抜ける肌寒い風があたりを夕闇色に染める。雪解け水のほとばしる瀬の音がにわかに大きく響いた。ふと、自分の不安が音を立てて砕けるように感じた。
私はもうじき二十四歳になる。京の都の外れでは追剝がはびこり、行き場のない貧民が都の大通りで行き倒れになる乱れた世にあって、屋敷の塀のなかでこれといった不自由もなく育ち、今は宮仕えをしている。自分ではそれなりに努力して勤めに励んでいるつもりだが、友人たちは、私は宮仕えに向かないと言う。確かにそうかもしれない。とはいえ、ほかにできそうなこともなにもない。友には一流の歌人になった者や、高貴な女性を次から次へと口説き落として浮き名を流す者もいるが、私にはこれといった才能も魅力もない。私には平凡な日々がよく似合う。どこにでもいそうな、おっとりとしていて皮膚の薄い青年――それが私なのだから。今日は役所の仕事で都から山を越えた小さな町へ使いに出かけ、今はその帰り道だった。
川の水際まで降り、尻尾を振りながら大人しく水を飲む馬の首をなでた。時々、私はほんとうの想いをこの馬だけに打ち明けた。彼だけは、私を欺いたり、軽蔑しようとしない。ただ黙って話を聞いてくれるのは、ほかに誰もいなかった。
再び馬に乗り、細い道をゆっくり進む。頭のなかは、またさっきの出口のない考えに戻る。
「これが明日も続くのか」
ため息をついてふと頭をもたげると、川沿いの段丘にぽつりと建った草庵の前を行き過ぎようとしていた。質素で小さな造りの庵だが、庭はきれいに掃き清められていて、薄暗いなかにも凛としたすがすがしさがある。水車が静かに回っている。背の高い孟宗竹が風になびき、丸い障子の窓にろうそくの明かりが揺れていた。なんとなく心惹《ひ》かれ、轡《くつわ》を引いて馬を返した。
「お願い申します」
私は馬を降りて呼ばわった。
障子に人影が映る。
すっと障子が開き、黒い袈裟に身を包んだ在家の裟弥《しゃみ》が顔を覗かせた。裟弥とは剃髪して出家したものの特定の寺にも宗派にも属さず世捨て人として過ごしている者のことだ。私は、時が遅くなってしまったので誠に相申し訳ないが一夜の宿を乞いたいと願い出た。
「それはさぞお困りでしょう。こんなところでよければお泊りください」
日頃の読経で鍛えているからだろう、裟弥の声は朗々と響いた。ただ響きが美しいばかりでなく、なにか大切なものへ向かってひたむきに歩いてゆくような、芯の通った確かな声だった。
――羨ましい。
あこがれとあきらめに似た心持ちが心の底にふっと湧き、それがないまぜになる。上辺だけの人間関係をとり繕いながら生きている私とは違い、彼は人として大事なものを守り、本物の生き方をしているように感じられた。
裟弥はふたつ手を叩いて下男を呼び、客人をもてなすよう言いつける。
「恐れ入ります」
私が頭をさげると、
「玄関へお回りください。すこしばかり用事を片付けなければなりませんので、後ほど」
と、裟弥は言って障子を閉めた。
下男の小僧が玄関先で出迎えてくれた。まだ裸のままで寒そうな紅葉の木に馬を繋ぎ、馬の背から外した荷をとりあえず玄関に置く。庵へ上がってすぐ、風呂をよばれた。乾いた風に一日中さらされていた私は埃まみれだった。
一人入るのがやっとの桝形の湯船に半畳ほどの洗い場があるだけの狭い風呂だが、湯船は新しくて清潔だった。檜のあざやかな木目が美しい。木立の香りがほのかな湯気にまじり、ふんわり漂う。
湯をすくおうとして、手にした桶をふととめた。
鮒が一匹泳いでいる。
小さな鮒だった。湯疲れしてしまったのだろうか。水面に突き出した口をせわしなくぱくつかせている。息が苦し気だ。きっと、小僧が横着して井戸の水を汲まずに川の水を直接湯船へ引き入れたために、心ならずもまぎれこんでしまったのに違いない。
「驚かせてすまないね」
そっと湯をすくい、かけ湯をした。湯はいささか熱めだった。
私が湯船に浸かっても、鮒は逃げもせず、やはり水面にしがみつくようにして漂っている。
焚き木が燃えて湯が温もり出した時、この鮒はさぞ腰を抜かしたことだろう。そう思うとなんともいえないおかしみがこみあげてきたが、そんな愉快な気持ちも泡のようにすぐに消えうせた。
両手で鮒をすくった。
鮒はおびえ、あらぬほうを見て弱々しく尾を打つ。
活きのよい鮒なら身をよじって逃げ出そうとするのだろうが、ぐったりしていた。どうにでもしてくれと運命のなされるままに気だるく身を横たえている。
「私に似ているね」
じっと鮒を見つめ、つぶやいた。その声が狭い風呂場でかすかにこだまして、私の心を苦くした。
生煮えの地獄とでも呼べはよいのだろうか。煮えたぎる湯でいっそ息絶えてしまうこともなく、どちらへ向かって泳ごうにも厚い壁に阻まれて進むこともかなわず、狭い湯船のなかで気力を失っている鮒の姿が今の私自身と重なった。心がおぼつかない。
「そのうち湯も冷めるだろうから、もう少し我慢しておくれ」
私は微笑みかけ、湯へ戻した。活かしもせず殺しもしない湯船のほうがまだよいのか、鮒は待ちかねたように湯船の奥深くへと急いで潜りこむ。風呂の湯はすぐにでも冷める。だが、この胸に抱えこんだ生煮えの地獄はいつまでも終わりそうになかった。
(続く)
世の中の人すべてが信じられなくなり、自分すらも信じられなくなった私。擦り切れた心を抱え息苦しい日々が続いていたそんなある日、京の外れの山奥でひとりの隠者に出会った。http://ncode.syosetu.com/n9691p/
本文
心が擦り切れる。きりきりと擦り切れる。うわべばかり繕っているからこうなるのだ。とはいえ、この気持ちは誰にも言えない。妻や親しい友人なら、なおさら話すことなどできない。
自分の気持ちを正直に言ってしまえば、相手の心に負担をかけてしまう。まず、それが怖い。誰だって自分の心をかき乱されたくないものなのだから、優しくいたわってくれる人にそんな迷惑をかけられない。
それに、自分の正直な気持ちが間違いだったらどうしようと思ってしまう。裸の心を見られた、と思っただけでもうだめだ。居たたまれなくなって、自分の足場が崩れ落ちたような気にさせられる。わかってくれないなと変に先読みして、わかってくれるはずがないと思いこんで落ちこんで、やはりわかってくれなかったことに落胆して――。的外れだけどやさしくて、あたたかいけど通り一遍な慰めの言葉がよけいにつらい。理解してもらえないことが、なぜか相手にすまない。
一人ひとり違う人間なのだから、わかってもらえないのは、当然だ。それは重々承知のうえだが、薄々気づいている壁をはっきり認識すれば、さびしくなってしまう。もっとも、理解してもらえたところでどうにもならないことも、わかっている。結局のところ、この擦り切れた心は自分ひとりで背負わなければならないものなのだから。
馬に跨りながら渓間の小道をとぼとぼと進んだ。
いつも同じことを考えては堂々巡りだった。その先を考えたいのに、どうすればいいのかわからない。同じことの繰り返しから抜け出して、どこかへ向かって進みたいのに、出口が見つからない。私《わたくし》という迷宮にはまりこんで、方角を見失ってしまったようだ。空っぽの心《しん》に鉋をかけては、肉も血も削いでゆく。いつも、胸が、圧されたように痛む。
馬に鞭を当てて急いで帰らなければいけないのはわかっている。とはいうものの、とてもそんな気にはなれなかった。なにも知らないで優しく迎えてくれる妻。早く孫ができないかとそればかり気にしている両親。友人からの連歌や食事の誘い。そのどれもがやりきれない。このままずっと独りきりでいるほうがどれだけ気が休まるだろう。いっそのこと、路傍の石になって、なにも感じずに、なにも考えずにいられたらどんなにいいことか。どうせ出口がないのなら、誰にも煩《わずら》わされず、誰も煩わさず、うずくまっていたい。
日が暮れなずむ。
ぼんやりとした夕陽が深い山の谷間に懸かり、木立を吹き抜ける肌寒い風があたりを夕闇色に染める。雪解け水のほとばしる瀬の音がにわかに大きく響いた。ふと、自分の不安が音を立てて砕けるように感じた。
私はもうじき二十四歳になる。京の都の外れでは追剝がはびこり、行き場のない貧民が都の大通りで行き倒れになる乱れた世にあって、屋敷の塀のなかでこれといった不自由もなく育ち、今は宮仕えをしている。自分ではそれなりに努力して勤めに励んでいるつもりだが、友人たちは、私は宮仕えに向かないと言う。確かにそうかもしれない。とはいえ、ほかにできそうなこともなにもない。友には一流の歌人になった者や、高貴な女性を次から次へと口説き落として浮き名を流す者もいるが、私にはこれといった才能も魅力もない。私には平凡な日々がよく似合う。どこにでもいそうな、おっとりとしていて皮膚の薄い青年――それが私なのだから。今日は役所の仕事で都から山を越えた小さな町へ使いに出かけ、今はその帰り道だった。
川の水際まで降り、尻尾を振りながら大人しく水を飲む馬の首をなでた。時々、私はほんとうの想いをこの馬だけに打ち明けた。彼だけは、私を欺いたり、軽蔑しようとしない。ただ黙って話を聞いてくれるのは、ほかに誰もいなかった。
再び馬に乗り、細い道をゆっくり進む。頭のなかは、またさっきの出口のない考えに戻る。
「これが明日も続くのか」
ため息をついてふと頭をもたげると、川沿いの段丘にぽつりと建った草庵の前を行き過ぎようとしていた。質素で小さな造りの庵だが、庭はきれいに掃き清められていて、薄暗いなかにも凛としたすがすがしさがある。水車が静かに回っている。背の高い孟宗竹が風になびき、丸い障子の窓にろうそくの明かりが揺れていた。なんとなく心惹《ひ》かれ、轡《くつわ》を引いて馬を返した。
「お願い申します」
私は馬を降りて呼ばわった。
障子に人影が映る。
すっと障子が開き、黒い袈裟に身を包んだ在家の裟弥《しゃみ》が顔を覗かせた。裟弥とは剃髪して出家したものの特定の寺にも宗派にも属さず世捨て人として過ごしている者のことだ。私は、時が遅くなってしまったので誠に相申し訳ないが一夜の宿を乞いたいと願い出た。
「それはさぞお困りでしょう。こんなところでよければお泊りください」
日頃の読経で鍛えているからだろう、裟弥の声は朗々と響いた。ただ響きが美しいばかりでなく、なにか大切なものへ向かってひたむきに歩いてゆくような、芯の通った確かな声だった。
――羨ましい。
あこがれとあきらめに似た心持ちが心の底にふっと湧き、それがないまぜになる。上辺だけの人間関係をとり繕いながら生きている私とは違い、彼は人として大事なものを守り、本物の生き方をしているように感じられた。
裟弥はふたつ手を叩いて下男を呼び、客人をもてなすよう言いつける。
「恐れ入ります」
私が頭をさげると、
「玄関へお回りください。すこしばかり用事を片付けなければなりませんので、後ほど」
と、裟弥は言って障子を閉めた。
下男の小僧が玄関先で出迎えてくれた。まだ裸のままで寒そうな紅葉の木に馬を繋ぎ、馬の背から外した荷をとりあえず玄関に置く。庵へ上がってすぐ、風呂をよばれた。乾いた風に一日中さらされていた私は埃まみれだった。
一人入るのがやっとの桝形の湯船に半畳ほどの洗い場があるだけの狭い風呂だが、湯船は新しくて清潔だった。檜のあざやかな木目が美しい。木立の香りがほのかな湯気にまじり、ふんわり漂う。
湯をすくおうとして、手にした桶をふととめた。
鮒が一匹泳いでいる。
小さな鮒だった。湯疲れしてしまったのだろうか。水面に突き出した口をせわしなくぱくつかせている。息が苦し気だ。きっと、小僧が横着して井戸の水を汲まずに川の水を直接湯船へ引き入れたために、心ならずもまぎれこんでしまったのに違いない。
「驚かせてすまないね」
そっと湯をすくい、かけ湯をした。湯はいささか熱めだった。
私が湯船に浸かっても、鮒は逃げもせず、やはり水面にしがみつくようにして漂っている。
焚き木が燃えて湯が温もり出した時、この鮒はさぞ腰を抜かしたことだろう。そう思うとなんともいえないおかしみがこみあげてきたが、そんな愉快な気持ちも泡のようにすぐに消えうせた。
両手で鮒をすくった。
鮒はおびえ、あらぬほうを見て弱々しく尾を打つ。
活きのよい鮒なら身をよじって逃げ出そうとするのだろうが、ぐったりしていた。どうにでもしてくれと運命のなされるままに気だるく身を横たえている。
「私に似ているね」
じっと鮒を見つめ、つぶやいた。その声が狭い風呂場でかすかにこだまして、私の心を苦くした。
生煮えの地獄とでも呼べはよいのだろうか。煮えたぎる湯でいっそ息絶えてしまうこともなく、どちらへ向かって泳ごうにも厚い壁に阻まれて進むこともかなわず、狭い湯船のなかで気力を失っている鮒の姿が今の私自身と重なった。心がおぼつかない。
「そのうち湯も冷めるだろうから、もう少し我慢しておくれ」
私は微笑みかけ、湯へ戻した。活かしもせず殺しもしない湯船のほうがまだよいのか、鮒は待ちかねたように湯船の奥深くへと急いで潜りこむ。風呂の湯はすぐにでも冷める。だが、この胸に抱えこんだ生煮えの地獄はいつまでも終わりそうになかった。
(続く)